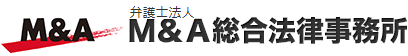種類株式のメリットとデメリット

種類株式とは
株式は大きく分けると、「普通株式」と「種類株式」の2つに分類することができます。
会社が通常の手続きで株式を発行した場合、その株式は「普通株式」として扱われます。
普通株式の持ち主には、会社法105条で認められた株主の権利(①剰余金の配当、②残余財産の分配、③株主総会の議決権)がもれなく認められます。その一方で、これらの権利以上の特典が認められることもありません。
これに対して、「普通株式とは異なる内容の株式」を発行することも認められています。会社法108条が定める9つの項目について、普通株式とは違う権利内容を定めた株式を発行できるのです。普通株式とは異なる種類の株式という意味で、「種類株式」と呼ばれます。
そもそも種類株式とは、「株主平等の原則」に対する例外として認められたものです。そこでまずは、「株主平等の原則」についての解説から始めていきます。
種類株式にも「株主平等の原則」がある
株式には、「株主平等の原則」というものがあります。「すべての株主は、その持ち株数に応じて平等に権利行使できる」という内容の原則です。
たとえば、株主はそれぞれの持ち株数に応じて、株主総会の議決権を持っています。持ち株数が10株であれば10個の議決権が認められますし、持ち株数が1,000株であれば1,000個の議決権を有することになります。
どんな人が株主になったとしても、「持ち株数に応じた議決権が認められる」という扱いは変わりません。このように、持ち株数に応じて平等に扱われるという意味で、「株主平等の原則」という言葉が使われます。
種類株式には「株主平等の原則」が当てはまらない会社もある
もっとも「株主平等の原則」は、株式が自由に売買されることを前提とする原則です。
買い取った株式の種類によって取り扱いが異なるというのでは、安心して株式を買うことができません。つまり「株主平等の原則」とは、株式の自由な売買を促進するためのものなのです。
これに対して、オーナー企業のように、株式の頻繁な売買を予定していない会社もあります。そのような会社では、株式の売買を促進するための「株主平等の原則」を認める必要性が乏しいのです。
むしろ「株主平等の原則」を無理やり当てはめようとすると、かえって不都合が生じてしまいます。
たとえば、あるスタートアップ企業に、二人の共同経営者AとBがいるとしましょう。Aは潤沢な資金を持っており、起業資金の大部分を提供しました。一方のBは資金力に乏しいものの、技術面・知識面ですぐれた能力を持っており、会社の立ち上げを主導する役割を果たしました。
会社の株式の大半は、起業資金の大部分を出資したAが持っているとします。この場合に「株主平等の原則」を形式的に当てはめようとすると、AとBの経営権に大きな差が生じてしまいます。すぐれたアイデアを持つはずのBの意見が、会社運営に反映されなくなってしまう可能性があるのです。
種類株式とは「株主平等の原則」による不都合を修正するためのもの
こうした場合には、「株主平等の原則」を修正する必要があります。そこで登場するのが「種類株式」です。つまり、普通株式とは内容の異なる種類株式を発行することで、株主の権利内容の調整を図るのです。
先ほどのスタートアップ企業の例であれば、たとえば「議決権制限種類株式」という類型の種類株式を活用することができます。
議決権制限種類株式とは、株主の重要な権利である「株主総会の議決権」について、普通株式よりも制限された内容の権利しか認められないタイプの種類株式です。普通株式の持ち主が株主総会の議決権を制限なく行使できるのに対し、議決権制限種類株式の持ち主は議決権の行使が制限されます。
こうした議決権制限種類株式をAに対して発行すれば、会社経営に対するAの影響力を制限することが可能です。
たとえば、Aが900株、Bが100株を保有しているとしましょう。Aが保有している900株のうち、800株を議決権制限種類株式にすることで、AとBの議決権を同等にすることができます。AとBの意見を同等に会社運営へ反映することが可能になるのです。
このように、種類株式をうまく活用することで、「株主平等の原則」によって生じる不都合を修正することができます。
種類株式にはどういう種類の株式があるのか
全9タイプの種類株式を自由に組み合わせることができる
種類株式には、議決権制限種類株式以外にもたくさんのタイプがあります。会社法108条によって、全部で9つの類型が認められています。
しかも、いくつかの類型を組み合わせて、会社の実情に合わせたオリジナルな種類株式を設計することも可能です。複雑化する現代の経営環境に適応するために、工夫を凝らした内容の種類株式を発行することができるのです。
したがって、どのような種類株式を設計できるのか知っておくことは、厳しい経営環境を生き抜くために必須の知識だと言えるでしょう。
それでは、種類株式の基本となる9類型について見ていきましょう。
剰余金の配当
剰余金の配当について、株式の種類によって差を設けることができます。いわゆる「優先株」や「劣後株」がこれにあたります。配当についてどのような差を設けるかは、各会社が自由に設計可能です。
剰余金の配当に関して有利な優先株は、投資家にとって非常に魅力的なものとなります。新株発行の際、より多くの投資家を集める目的で、新株を優先株にして魅力を高めるのが一般的な活用法です。
逆に劣後株は、投資家にとっては不利なものです。主な活用法としては、既存株主の既得権益を損なわずに資金調達を行うために、発行する新株を劣後株にするという使い方が挙げられます。
残余財産の分配
残余財産の分配は、会社が解散した後の話です。会社を解散する際に負債等を整理した後、もし財産が残っていた場合に株主へ分配することを「残余財産の分配」と呼びます。
残余財産の分配についても、株式の種類ごとに差を設けることができます。ここでも、どのような差を設けるかについては、会社ごとに自由な設計が可能です。
株主総会の議決権の制限
先ほど例に挙げた「議決権制限種類株式」のことです。経営権のバランスを調整するために便利なので、様々な場面で非常に重要な役割を果たします。
たとえば、大株主A・B・Cがいる会社において、Aが保有する株式のみ議決権制限種類株式に変更することができます。
あるいは、新株発行による資金調達を行う場面でも活用できます。新たに発行する株式を議決権制限種類株式とすれば、経営権のバランスを変えることなく資金調達をすることが可能です。
なお、議決権をどのように制限するかについても、自由に設計することが可能です。「特定の事項について決議できない」と定めることもできますし、「株主総会に一切参加できない」とすることもできます。各会社の状況に合わせて株式を設計できます。
株式譲渡の制限
譲渡するのに会社の承認が必要である旨が定められた種類株式です。株式の頻繁な売買を予定していない会社において、株式の散逸を防止するために中心的な役割を果たします。
「会社の承認」の具体的な内容については、会社法が定める範囲内で様々な設計が可能です。たとえば、原則として株主総会の承認決議が必要としつつ、代表取締役が承認した場合にも「株主総会の承認決議があったものとみなす」旨を定めることができます。
取得請求権付き種類株式
株主の側が、会社に対して「株式を買い取ってくれ」と請求できる種類株式です。株主の請求があれば、会社は対価を支払って株式を買い取らなければなりません。株主の側に強い力を与える種類株式だと言えるでしょう。
具体的な活用法としては、「議決権制限種類株式」や「譲渡制限種類株式」を発行する際に、同時に取得請求権も付与しておくという方法が考えられます。
というのも、議決権や株式譲渡を制限するだけの種類株式だと、取得する側にとって魅力がなくなってしまいます。そこで、同時に取得請求権も付与して株主の力を強めておくことで、種類株式を取得するインセンティブを高めるのです。
取得条項付き種類株式
「一定の事由が発生したことを条件に、会社が株主から取得できる」という旨を定めた種類株式です。「一定の事由」の内容については、各会社で自由にアレンジすることができます。
会社が株主から強制的に株式を回収できることになるので、会社に対して強い力を与える内容の種類株式だと言えます。
実際にこの種類の株式を発行する際には、同時に剰余金の配当を優先する内容も盛り込むなどして、株主にとっての「うまみ」を付与するのが一般的です。
全部取得条項付き種類株式
「株主総会の決議によって、会社が株主から取得できる」という旨を定めた種類株式です。
前もって取得事由を定めることなく、株主総会の決議があれば自由に株式を取得できるため、取得条項付き種類株式よりもさらに強い力を会社に与えるものと言えるでしょう。
株主からすると不利な株式なので、配当の優先など株主側の「うまみ」も盛り込んで発行されるケースが多くなっています。
拒否権付き種類株式
株主総会や取締役会の決議に対して、拒否権を発動することができる種類株式です。
一定の決議事項について、株主総会や取締役会の決議に加え、種類株式の株主で構成する「種類株主総会」の決議も必要となる旨を定めることができます。この種類の株式を持っていれば、株主総会や取締役会で決定した事項についても否決することが可能となるため、「拒否権付き種類株式」と呼ばれています。
会社の経営に対する強大な影響力を、株主に与えることができます。特定の株主に対して強い経営権を持たせる目的で活用できる種類株式だと言えるでしょう。
取締役・監査役の選任権
取締役や監査役の選任を、種類株式の株主で構成する「種類株主総会」で行う旨を定めることができます。この種類の株式を所有する株主だけが、取締役・監査役を選任できるということになります。
会社組織の決定権を直接持つことができる種類株式であり、株主に対して非常に強い力を与えるものだと言えます。
種類株式と属人的株式との違い
なお、種類株式に似たものとして「属人的株式」があります。そこで、種類株式と属人的株式の違いについても確認しておきましょう。
属人的株式とは
属人的株式とは、「株主ごとに異なる取り扱いを行う旨」を定款で定めた場合の株式のことです。
具体的には会社法109条2項が、①剰余金の配当・②残余財産の分配・③株主総会の議決権について、株主ごとに違いを設けることを認めています。
たとえば、ある会社に3人の株主A・B・Cがいたとします。この場合に、「Aのみが議決権を有し、B・Cは株主総会に参加できない」といった定めを置くことができるのです。
もっとも、属人的株式は「株主平等の原則」に対する重大な例外なので、導入には非常に厳格な要件が定められています。株主総会において、総株主の半数以上が出席したうえで、総株主の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
種類株式との違い
表面的に見ると、種類株式とよく似ているように思えます。しかし、属人的株式は「Aという人物」に注目した定めです。これに対して種類株式の場合は、「株式の種類」に注目した定めとなっています。
この違いは、たとえば相続の場面において大きな影響をもたらします。先ほど挙げた「株主A・B・CのうちAだけが議決権を認められている」という例で考えましょう。
属人的株式は「その人限り」
AとB・Cの違いが属人的株式の定めによる場合は、Aの議決権はあくまでも「Aという人に限り」認められたものと考えられます。
そのためAが死亡した場合には、「その人限り」の属人的な扱い自体が終了することになります。具体的には、すべての株式が普通株式に戻り、B・Cを含むすべての株主が1株につき1個の議決権を有することになるのです。
種類株式は「株式の属性」
これに対して、Aは普通株式を、B・Cは無議決権種類株式を持っていたという場合は、考え方が変わってきます。
Aに認められる議決権は、Aが保有している「普通株式の属性」です。Aという人自体に議決権が認められらているわけではありません。
そのため、Aが死亡した場合の扱いも、属人的株式のケースとは変わってきます。株式の持ち主が変わっても、普通株式は普通株式のまま、無議決権種類株式は無議決権種類株式のままです。つまり、Aから株式を相続した者には議決権が認められる一方で、B・Cの議決権は依然として認められません。
属人的株式のデメリットとメリット
株主が変わる可能性のある場合、属人的株式は不便
以上のように、属人的株式は「その人限り」の扱いを認めるものです。株主が変わることを予定した場面で使うのは適切ではありません。その場合には、種類株式を活用したほうが良いでしょう。
属人的株式は、種類株式よりも柔軟な設計が可能
一方で、属人的株式の場合は、種類株式よりもさらに柔軟な設計が可能です。
たとえば、種類株式の場合、1株に複数の議決権を付与することは認められていません。会社法108条が定める9類型の中に、そのような類型が存在していないからです。
これに対して属人的株式の場合は、①剰余金の配当・②残余財産の分配・③株主総会の議決権に関する限りで、種類株式よりも柔軟に設計できます。種類株式では認められない「1株に複数の議決権を付与する」という定めも、属人的株式なら可能です。たとえば、「社長が保有する株式に限り、1株につき100個の議決権が認められる」と定めることができます。
すなわち、属人的株式には種類株式よりも優れた点があるのです。株主が変わってしまう可能性を慎重に考慮したうえで、種類株式だけでなく属人的株式の活用も視野に入れるべきでしょう。
事業承継における種類株式の使用方法
ここからは、事業承継において種類株式をどのように活用できるのか、具体的に見ていくことにしましょう。
敵対者による株式買収の防止
事業承継の代表的な手法として、「現経営者が保有している株主総会の議決権を、後継者に承継させる」という方法があります。
具体的には、まず後継者に対して新株を発行することで、現経営者と同等の議決権を後継者に付与します。同時に、現経営者が保有する株式については、会社名義に移すことで無議決権株式とします。そうすることで、現経営者が有していた議決権を、実質的に後継者へ承継させるのです。
ところが、せっかく後継者に対して発行した株式を、敵対者に買収されてしまうとどうなるでしょうか。会社の経営権が後継者以外に分散するため、事業承継が失敗に終わってしまいます。
こうしたリスクに備える方法として、「譲渡制限種類株式」を活用することが考えられます。
譲渡制限種類株式の活用
たとえば全部で1,000株の株式を発行している甲社において、現経営者Aが900株を所有しているとしましょう。Aから後継者Bへの事業承継を行うため、甲社ではBへ900株の新株発行を行うとともに、A所有の900株については甲社名義に移したとします。
その際、後継者Bに対して発行する900株の新株を、譲渡制限種類株式にしておくのです。そうしておけば、仮に敵対者がBから甲社株を買い取ろうとしても、譲渡には甲社の承諾が必要になります。その結果、株式の散逸を防ぐことができるのです。
現経営者の不慮の死に備える
現経営者の不慮の死も、事業承継にとってのリスクとなります。
たとえば、現経営者の株式を会社名義へ移す前に、現経営者が想定外の死を遂げたとしましょう。死亡した現経営者が保有していた株式は、相続人の手にわたります。この場合も、会社の経営権が後継者以外に分散し、事業承継が失敗に終わってしまうことになるのです。
こうしたリスクに対しては、「取得条項付き種類株式」や「議決権制限種類株式」を使って備えることが可能です。
取得条項付き種類株式の活用
先ほどの甲社の例で、現経営者Aの所有する900株を甲社名義へ移す前に、Aが不慮の死を遂げたとします。もしAの所有していた株式が普通株式だったなら、Aのもとにあった経営権はAの相続人へと分散してしまい、後継者Bへの円滑な事業承継は失敗に終わってしまいます。
そこで、Aが所有する甲社株をあらかじめ、「Aの死亡を条件とする取得条項付き種類株式」に転換しておくのです。そうすれば、もしAが不慮の死を遂げたとしても、Aの所有していた甲社株は自動的に甲社名義に移されることになります。その結果、甲社の経営権がAの相続人へ分散する心配はなくなります。
議決権制限種類株式の活用
もし、後継者Bが現経営者Aの相続人であるならば、「議決権制限種類株式」を活用することも考えられます。
たとえば先ほどの甲社の例で、後継者Bは現経営者Aの息子だとしましょう。AにはBの他にも2人の子C・Dがおり、さらにAの妻Eも存命だとします。するとAの相続人は、子B・C・Dと妻Eの4人ということになります。
この場合、民法上の相続分は子B・C・Dが6分の1ずつ、妻Eが2分の1ということになります。つまり、事業承継の最中にAが不慮の死を遂げたとすると、Aの所有していた甲社株900株のうち、6分の5にあたる750株が後継者B以外の者へ散逸することになるのです。
すると、甲社株全1,900株(従来からあった1,000株+Bへの新株発行分900株)のうち、Bの手元に残るのは1,050株(新株900株+相続した150株)です。これでは甲社株の3分の2に満たず、甲社の経営権を円滑に承継できません。
そこでAの所有する900株のうち、B以外の相続人の手にわたる可能性のある750株について、あらかじめ「議決権制限種類株式」に転換しておきます。加えて、遺言の中で「Bの相続する株式は普通株式、C・D・Eの相続する株式は議決権制限種類株式」と指定しておけば、甲社の経営権を後継者Bへ集中させることができるのです。
少数株主の排除(スクイーズアウト)
以上は事業承継に伴う株式散逸リスクの回避方法でしたが、それ以外にも種類株式の活用方法が存在します。たとえば、事業承継に反対する立場の少数株主を排除することが可能です。
全部取得条項付き種類株式の活用
具体的には、発行済みの株式すべてを「全部取得条項付き種類株式」に変えてしまいます。その後、現実に全株式を会社が取得したうえで、事業承継に賛成する者に対してのみ改めて新株を発行すれば、反対派の少数株主を排除することができるのです。
たとえ少数株主が一連の手続きに反対していたとしても、心配する必要はありません。種類株式を導入するための定款変更は、「数の力」で実行可能だからです。特に、自社株の大半を経営者自身が保有しているオーナー企業においては、簡単に実現可能な方策だと言えるでしょう。
承継後の経営をモニタリングする
事業承継が完了した後に、後継者による会社運営を前経営者がモニタリングすることも可能です。たとえば、後継者の経験が不足しているような必要に、後継者が暴走しないよう見守るために有効な手段です。
拒否権付き種類株式の活用
具体的には、前経営者が「拒否権付き種類株式」を保有するようにします。そうしておけば、後継者が明らかに失敗する可能性の高い会社運営を提案した場合に、種類株主総会で後継者の提案を否決することができるのです。
なお、拒否権付き種類株式は別名「黄金株」とも呼ばれる、非常に影響力の強い株式です。前経営者の手を離れると、会社経営が危険にさらされてしまいます。たとえば、第三者に買い取られたり、相続人の手にわたってしまうことを防ぐ必要があるのです。
そのためには、拒否権付き種類株式に「譲渡制限」や「前経営者の死亡を条件とする取得条項」も盛り込んでおくと良いでしょう。
種類株式の発行手続き
最後に、種類株式を導入するための手続きについても確認しておきましょう。
定款で定めておく必要がある
種類株式を発行するには、会社の定款に「発行する種類株式の内容」と「発行可能種類株式総数」を定めておくことが必要です。
たとえば議決権制限種類株式を発行するためには、「発行する議決権制限株式の内容」と「発行可能な議決権制限株式の総数」を会社の定款で定めておく必要があります。
会社設立の当初から種類株式の発行を予定している場合は、設立手続きの中で定款に種類株式の定めを記載しておくという流れになります。
定款を変更すれば事後的な導入も可能
一方で、すでに設立が終わり普通株式を発行している会社でも、定款を変更すれば種類株式を導入できます。新たに種類株式を発行するだけでなく、既存の普通株式を種類株式に変えてしまうことも可能です。その旨の定めを定款に置くように変更すればよいのです。
いくつかの種類株式の類型を組み合わせて、自社に最適な種類株式を設計することも可能です。導入したい種類株式の内容とその総数を定款に定めることさえできれば、種類株式を自由自在に活用することができるのです。
なお、定款の変更に必要な手続きは、「株主総会の特別決議(過半数の株主の出席+出席株主の3分の2以上の賛成)」です。多数の株主が存在する上場会社では高いハードルとなりますが、株式の大部分を経営者自身が保有しているオーナー企業であれば決して難しい手続きではありません。