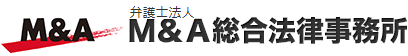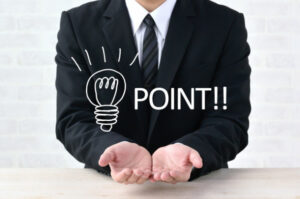【引っ越し済み】事業承継と廃業を徹底比較!中小企業にとってどちらが良いのか解説

中小企業の経営者が引退する際は、「事業承継」か「廃業」のどちらかを選ぶ必要があります。
しかし、どちらを選べば良いのか判断するのが難しいと悩む方も少なくありません。
そこで、この記事では事業承継と廃業を徹底比較し、手続きの違いやスムーズに進めるためのポイントなどを解説していきます。
「事業承継」か「廃業」かで、悩んでいる方は参考にしてみてください。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
事業承継と廃業の比較
事業承継と廃業の内容やメリット・デメリットを以下の比較表にまとめたので確認してください。
| 内容 | メリット | デメリット | |
| 事業承継 | 会社が残る | ・会社を残せる ・株式を売却することで譲渡益を獲得できる ・従業員の雇用を確保できる |
・後継者を探し育成する必要がある ・後継者に資金面での負担がある ・時間がかかる可能性がある |
| 廃業 | 会社がなくなる | 会社に関する精神的な負担から完全に解放される | ・従業員の雇用が確保できない ・取引先などに迷惑がかかる ・会社が蓄積した知的財産が失われる ・個人資産を売却して借入の返済に充てる必要がある |
上記の比較表を参考に、廃業と事業承継どちらが自身の思いに則しているのか、目安をつけてみましょう。
事業承継とは
事業承継とは会社の経営を後継者に引き継ぐことです。
引き継ぐ経営資源には、「経営権・資産・負債」だけでなく、経営理念や取引先などの知的資源も含まれます。
したがって、事業承継したからといって、今まで育んできたものが無くなるわけではありません。
自身の引退後も思い入れのある会社を存続させたいと考えている方は、事業承継を選択肢にいれてみてください。
なお、近年の日本では中小企業経営者の高齢化が進んでおり、廃業による雇用や技術の喪失が懸念されています。
実際、2020年に中小企業庁が公表しているデータによると、2025年までに70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者の約127万人が「後継者がいない」と回答しました。
出典:中小 M&A ガイドライン -第三者への円滑な事業引継ぎに向けて
上記のような事態を防ぐためにも、事業承継は非常に重要な手段と言えます。
親族内の事業承継
親族内の事業承継は、その名前の通り経営者の親族から後継者を選んで行う事業承継です。
事業承継の中では最も一般的な方法ですが、近年は少子化や価値観の変化などにより後継者がいなかったり後継者が拒否したりして、減少傾向にあります。
実際、中小企業庁が公表している「令和元年度(2019年)の小規模事業者の動向」によると2017年に「41.6%」であった親族間の事業承継が、2019年には「34.9%」まで減少しました。
とはいえ、それでも他の事業承継の方法よりも親族間の事業承継が最も多いのは変わっていません。
出典:2020年版「小規模企業白書」 第1部第3章第2節 経営者の高齢化と事業承継
親族内に事業継承できそうな方がいる場合は、後継者候補にするといいでしょう。
なお、親族内の事業承継のメリットは以下の通りです。
- 後継者を見つけやすい
- 社員や取引先が後継者として受け入れやすい
- 経営権の移譲に必要な株式を贈与や相続で取得できる
- 後継者を教育・訓練する期間が確保できる
特に、親族間の事業承継は親族という安心感や信頼感から、従業員や取引先も選ばれた後継者を受け入れやすくなるのが最大のメリットと言えます。
また、後継者を役員などに選任しておくことで、じっくりと時間をかけた後継者教育ができることも嬉しいポイントです。
ただし、下記のデメリットがあることも知っておくようにしてください。
- 後継者を決める親族間の対立が起きる可能性がある
- 後継者候補がその仕事に興味を示さない可能性がある
- 親子の場合は感情のもつれが起きやすい
上記の中で最も重要なのが、後継者が役割を担う意欲です。
意欲がない方に無理に事業承継させても業績が悪化する可能性が高いため、任命された後継者が組織のリーダーになることを決意しているかどうかを見極めるようにしましょう。
従業員への事業承継
従業員への事業承継は、会社で働いている社員を後継者として選び、事業承継する方法です。
親族に後継者がいない場合に実行されることが多い方法になります。
中小企業庁が公表している「令和元年度(2019年)の小規模事業者の動向」でも、従業員への事業承継は「33.4%」で、親族間の事業承継の「34.9%」についで高い割合でした。
出典:2020年版「小規模企業白書」 第1部第3章第2節 経営者の高齢化と事業承継
親族に後継者がいない場合は、従業員による事業承継を検討してみてください。
なお、従業員の事業承継のメリットは以下の通りです。
- 会社について熟知している候補者を確保できる
- 親族間の事業承継に比べて候補者が多い
- 後継者の育成期間が短くすむ
- 企業理念を継承しやすい
- 取引先や従業員の理解が得られやすい
- 株式売買で資金を得られる
特筆すべきは、会社の業務や考え方を熟知している人材なので、教育期間を短縮できる点です。
このため、事業承継がスムーズに進む可能性が高くなります。
ただし、以下のデメリットがあることも理解しておかなくてはいけません。
- 株式を買い取る必要がある
- 親族から反感を買う可能性がある
- 大胆な改善ができない可能性がある
- 優秀な人材が必ずしも経営者として優秀とは限らない
特に、経営権の移譲に必要な株式を従業員に買い取ってもらうハードルが高く実現しないことがよくある点には注意が必要です。
従業員への事業承継を検討する際は、株式を買い取るための資金が用意できるのかを、よく確認するようにしてください。
第三者への事業承継
第三者への事業承継は、外部から後継者を招聘する方法です。
実は、後継者不足により、M&Aや社外の第三者を招聘しての事業承継を検討する方が増えています。
実際、中小企業庁が公表している「令和元年度(2019年)の小規模事業者の動向」でも、外部招聘による事業承継は、2017年に「7.4%」であったものが、「8.5%」まで増えていました。
出典:2020年版「小規模企業白書」 第1部第3章第2節 経営者の高齢化と事業承継
また、同じく中小企業庁が公表している「2022年中小企業白書」でも、2021年のM&A件数が過去最高の4,280件を記録しています。
出典:令和3年度(2021年度)の 中小企業の動向
このことからも、第三者への事業承継が増えているのは間違いありません。
後継者不足に困っている方は、第三者への事業承継を検討してみるといいでしょう。
なお、そんな第三者の事業承継のメリットは以下の通りです。
- 幅広く後継者に適した人材を探せる
- 独自の価値観やスキルを持った多くの後継者を発掘することができる
- 買い手の組織とのシナジー効果によりビジネスチャンスが増える
- 株式の売却により資金などの収益を得ることができる
- 買い手の企業価値を向上させることが期待できる
一方で、以下のようなデメリットも存在します。
- 信頼できる人材を探すのが難しい
- 希望する条件で事業承継できない可能性がある
- 手続きが煩雑で時間がかかりやすい
- 「企業理念・企業文化・労働条件」が変化し、従業員や役員の不満が募る可能性がある
上記のように、信頼できる後継者を見つけるのが難しいというデメリットがあるものの、大胆な改革や事業の拡大など会社がより発展する可能性があるという大きなメリットがあります。
したがって、企業価値を向上させたい方は、第三者への事業承継を検討してみてもいいでしょう。
廃業とは
廃業とは経営者判断で法人格を消滅させ、清算することです。
資金繰りが悪化して債務を法的に清算する「倒産」とは違って、廃業は単に会社をたたむことを指すため、経営状態は関係ありません。
経営状態が良くても決められた手続きを行うことで、廃業することが可能です。
ちなみに、近年廃業する企業は増加傾向にあります。
東京商工リサーチの「2021年休廃業・解散企業動向調査」によると、2013年は休廃業・解散をした企業の件数が「34,800件」だったのに対して、2021年は「44,377件」と「9,577件」も増加しました。
出典:令和3年度(2021年度)の 中小企業の動向
このように、中小企業の廃業が増えていることを覚えておいてください。
中小企業が廃業する理由
中小企業の廃業には、「事業承継せずに自身の代で会社を終わらしたい」や「事業に将来性がない」というケースもありますが、廃業を望んでいなくても廃業せざるを得なかったというケースも少なくありません。
日本の中小企業の多くは経営者の高齢化が進んでおり、後継者が見つからず廃業する会社が増えています。
実際、日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2020年)」によると、後継者がいないことで廃業した企業の割合は約3割程度です。
この数字は、「事業承継の意向がない」という理由に次いで2番目に多い数字となります。
このように、中小企業の方が廃業する理由には、後継者が見つからず仕方なく廃業したという理由が多いことを理解しておきましょう。
なお、廃業している会社の「61.5%」は黒字状態で廃業しています。
出典:中小企業庁:財務サポート「事業承継」
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
中小企業が廃業するメリット・デメリット
中小企業が廃業するメリット・デメリットと下記で解説する事業継承メリット・デメリットを理解しておけば、比較してどちらが自身に向いているのかを判断できます。
ここでは、中小企業が廃業するメリット・デメリットについて解説しますので、参考にしてください。
廃業のメリット
廃業のメリットは、会社の経営から退けることです。
事業承継でも会社の経営から退くことはできますが、会社は存続しているため、経営状況などが気になってしまう方も少なくありません。
その点、廃業の場合は会社が消滅してしまうため、そのような精神的な負担をなくすことが可能です。
会社に関する精神的な負担から完全に解放されたいという方は、事業承継よりも廃業を選ぶといいでしょう。
廃業のデメリット
中小企業が廃業すると、さまざまなデメリットがあります。
主なデメリットは以下の通りです。
- 会社が存続しないため従業員の雇用が継続できなくなる
- 懇意にしていた取引先や顧客との関係がなくなり、場合によっては迷惑がかかる
- 会社が今までの企業活動で蓄積したノウハウや技術などの知的財産が失われる
- 廃業は買掛金や借入金などの負債を完済する必要があるため、場合によっては個人資産を売却して借入金の返済に充てる必要がある
- 賃貸の場合は原状回復費用や在庫を処分する費用など、廃業するための資金が必要になる
中でも、長年一緒に働いてくれた従業員を雇用できなくなることを大きな精神的負担と感じる方は非常に多いです。
それに加え、清算後に個人保証のある負債が残っている場合には、経営者が返済しなければならないという経済的な負担もあります。
このように、多くのデメリットがあるため、基本的に廃業はおすすめしません。
どうしても廃業する必要がある場合には、取引先や従業員への負担を減らすためにも、しっかりと準備して行うようにしてください。
中小企業が事業承継するメリット・デメリット
廃業と事業承継を比較して検討するためには、事業承継のメリット・デメリットも理解しておく必要があります。
ここでは、中小企業が事業承継するメリット・デメリットについて解説します。
事業承継のメリット
中小企業が事業承継を行うことには多数のメリットがあります。
主なメリットは以下の通りです。
- 会社を残せる
- 株式を売却することで譲渡益を獲得できる
- 従業員の雇用を確保できる
特に、今まで培ってきたノウハウや技術を残すことができるのは大きなメリットです。
自身が思い入れのある会社を残せるだけでなく、会社がもたらしている社会的な価値も存続できます。
また、従業員の雇用の面や資金面からみても、廃業よりも事業承継のほうが経営者にとってメリットが大きいと言えるでしょう。
事業承継のデメリット
中小企業が事業承継する主なデメリットは以下の通りです。
- 後継者を見つけて育成する必要がある
- 株式を買い取ってもらい経営権を移譲する場合、後継者に資金面での負担がある
- 廃業に比べると時間がかかる可能性がある
上記のようなデメリットがありますが、事業承継の準備をしっかりと時間をかけて行うことで、スムーズな事業承継が可能です。
事業承継か廃業かを選ぶ方法
廃業よりも事業承継のほうが、メリットが多いため特別な理由がない限りおすすめしたい方法です。
しかし、会社の財務状況や業界の将来性によっては、廃業を選んだほうが良い場合もあります。
例えば、業界に将来性がなく会社の業績も悪化していく可能性が高い場合は、事業承継するよりも廃業を選ぶほうが良いでしょう。
他にも、多額の負債を抱えており立て直せる見込みがない場合も、後継者に承継しても負担になり余程の経営手腕や胆力がなければ会社を立て直すことは困難です。
そのため、廃業をしたほうが良い可能性が高いでしょう。
このように、会社の将来性や財務状況によって選ぶべき選択肢が変わってくることを理解しておく必要があります。
事業承継と廃業の手続き
事業承継や廃業をスムーズに行うためには、それぞれの手続きの手順を理解しておく必要があります。
ここでは、事業承継と廃業の手続きをそれぞれ詳しく解説していきましょう。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
事業継承の手続き
親族内・従業員への事業承継の手順は以下の通りです。
- 会社の財務状況など現状を把握する
- 経営に問題がある場合は事業承継をしやすいように経営改善する
- 後継者候補を見つける
- 事業承継計画書を作成する
- 事業承継を実行する
一方で、第三者への事業継承は以下の手順を踏みます。
- 会社の財務状況など現状を把握する
- 経営に問題がある場合は事業承継をしやすいように経営改善する
- 買い手企業を見つけてM&Aを実行する
ちなみに、事業承継計画書に関しては作成しなくても問題ありません。
しかし、事業承継は数年〜10年程度かかるケースもあり、長期化する可能性もあるため、失敗するリスクを軽減するためにも作成することをおすすめします。
なお、中小企業の事業承継の手順に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある方は参考にしてください。
廃業の手続き
廃業の流れは以下の通りです。
- 解散決議および清算人を選任する
- 選任登記を届出る
- 解散届を提出する
- 廃業する旨を公告する
- 資産・負債の清算手続きをする
- 決算書類を提出する
- 確定申告を行う
- 清算結了登記する
上記のように、廃業は事業承継と違い後継者を育成するなどのプロセスが必要ありません。
そのため、事業承継と比較すると短期間で手続きを行うことが可能です。
中小企業の廃業を防ぐ事業承継の進め方
中小企業の経営者の方が事業承継を考えているなら、すぐに行動する必要があります。
仮に自身が元気でまだまだ働けるからといって先延ばしにしてしまうと、後継者が見つからなかったり、後継者育成をする時間がなかったりして、廃業せざるを得ない事態になりかねません。
また、業績が悪化してしまいM&Aが難しくなったり、後継者候補が事業承継を拒否したりする事態になる可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、事業承継は会社の業績が良く、自身も元気なうちから数年をかけて準備しておくことが重要です。
事業承継・廃業をスムーズに進めるポイント
廃業や事業継承は手続きが複雑なため、ポイントを理解しておかないとスムーズに進めることができません。
ここでは、廃業・事業承継をスムーズに進めるポイントを解説するので、参考にしてください。
廃業をスムーズに進めるポイント
廃業をスムーズに進めるポイントは以下の通りです。
- 財務状況を把握する
- 早期に債務整理する
- 廃業資金を確保しておく
- 専門家に相談する
廃業をするためには、買掛金や借入金を完済する必要があるため、財務状況を把握して廃業資金を確保しておくことが非常に重要です。
資金的な問題がクリアできれば、廃業手続きを行うだけになります。
ただし、手続きが複雑で自身で廃業するのは難しいと感じているなら、専門家への相談を検討してみてもいいでしょう。
事業承継をスムーズに進めるポイント
事業承継をスムーズに進めるポイントは以下の通りです。
- 時間に余裕を持つ
- 中小企業の事業承継をサポートする制度を利用する
- 専門家に相談する
事業承継をスムーズに行うためには、なによりも時間に余裕を持つことが重要です。
特に、後継者教育を行う場合には、事業承継が完了するまでに時間がかかってしまうケースが少なくありません。
したがって、事業承継は短期間で行うのではなく、しっかりと準備ができるように時間に余裕を持つようにしてください。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
まとめ
安定した経営ができており将来性もあるなら、廃業よりもメリットが多い事業承継が適しています。
反面、多額の負債を抱えていたり事業の将来性がないなら、廃業を選んだほうがが良い可能性が高いです。
このように、会社の状況などによって最適な選択肢が変わるため、廃業や事業承継を選ぶ際はどちらが良いのかを比較検討し、慎重に判断する必要があります。
この記事では、廃業か事業承継かを選ぶために必要な情報を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。