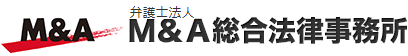後継者への自社株式集中のためオーナーが生前にできる4つの対策

事業承継においては、経営者としては、後継者に自社株を集中させたいところですが、他の相続人関係者などは遺留分減殺請求権を有しているなど、経営者の相続が発生した場合、相続紛争・事業承継紛争が非常に心配です。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
事業承継の「争続」対策に必須の遺言・事業承継信託・遺留分特例!
すなわち、事業承継においては、経営者が、後継者に自社株を集中させるためには、まずは、遺言や生前贈与で後継者に自社株を集中させることが一般的な対応策となります。
また、柔軟に事業承継したいということで事業承継信託にて後継者に会社の経営権や財産権を集中させることも多いです。
ただ、相続までに自社株の価値が高騰した場合、相続財産のほとんどが自社株式ということとなってしまい、後継者に自社株式を集中して相続させた場合、他の相続人から遺留分の主張を受ける可能性が高くなります。
その場合、否応なく、後継者が自社株を一部売却しなければならなくなることや他の相続人に自社株を一部相続させざるを得なくなることが多く、自社株式が分散してしまったり、後継者が相続することができる自社株式以外の財産が非常に少なくなってしまったりします。
そこで、遺留分の事前放棄制度があります。ただ、遺留分の事前放棄制度は要件が厳しく、また遺留分をすべて放棄することにもなりますので、あまり使われていません。
近時では、この点は、遺留分特例(除外合意・固定合意・付随合意)で解決することがで切るようになっていますが、遺留分特例(除外合意・固定合意・付随合意)の制度もメリット・デメリットがあります。
そこで、ここでは、後継者に自社株を集中するための制度であり、事業承継の「争族」対策としての制度である、「遺言」「事業承継信託」「遺留分特例」について解説します。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
後継者への自社株式集中のため、オーナーが生前にできる4つの対策
事業承継において、後継者への自社株式集中が必要な最も大きい理由は、後継者がもつ自社株式の割合が少ないと、会社の意思決定に必要な議決権が付与されないからです。たとえば、後継者の自社株式割合が50%未満だと、取締役の選任といった一般的な議案すら後継者だけでは決定できません。
そのような事態に陥らないように、オーナーが生前にできる対策としては次の方法が挙げられます。
- 遺言
- 生前贈与
- 事業承継信託
- 遺留分特例
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
対策1:遺言
1つ目の対策として、オーナーが生前に遺言書を作成しておく方法は、最も一般的といえます。
遺言がない場合は、相続人の間で遺産をどう分割するか話し合い、まとまらなければ法定相続分に従って遺産を分割します。オーナーの思い通りに遺産が分割されるとは限りません。しかし、生前に遺言書を作成しておけば、それに従って相続人が遺産を相続します。
遺言には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言の内容・日付・名前を自筆で記して押印すれば作成可
- 公正証書遺言:公証役場で、公証人に要件を確認してもらいながら作成
- 秘密証書遺言:内容は秘密のまま、遺言が存在することのみ公証人が証明
「争族」を避けたいのなら、公正証書遺言を作成しましょう。ほかの形式の場合、遺言内容を作るのが素人である被相続人のため、必要な要件を満たさずに遺言が無効になったり、複数の解釈が可能な書き方をしたりして、無用なトラブルにつながる可能性があるからです。
対策2:生前贈与
2つ目の対策である「生前贈与」とは、名前の通り生前に財産を渡すことです。生前贈与では、後継者が自社株式の取得対価を支払わないですむのはメリットですが、税率が高い贈与税を納める義務が生じるのはデメリットです。
しかし、中小企業の事業承継が円滑に進むように政府が施行した「事業承継税制」を活用すれば、一定割合の贈与税・相続税が猶予されます。
具体的には、親族間で非上場株式を贈与・相続する場合は、総株式数における最大2/3まで、贈与税は100%・相続税は80%分の納税猶予を受けられるというものです。
事業承継税制など、さまざまな制度を活用して相続税対策を取れば、後継者が支払う相続税額は大きく変わってきます。後述する遺留分に配慮して揉めない相続を行うには、まず法律のプロである弁護士に相談し、必要なら弁護士経由で税理士と連携することが大切です。
対策3:事業承継信託
3つ目の対策である「事業承継信託」について解説します。
まず「信託」とは、相手を信頼して委託(業務などを依頼)することであり、特に、財産の管理や運用を信頼できる相手に委託する制度のことです。
信託は次の三者から構成され、委託者と受託者の間で交わされるのが「信託契約」です。
委託者:もっている財産を預ける(信託する)人
受託者:財産の管理・運用を頼まれる(信託される)人
受益者:財産から生じた利益を、受託者から受け取る人(委託者と同一人物でも可)
信託契約は次の2種類に分けられます。
商事信託:受託者が報酬を受け取る信託契約。受託者は信託銀行・信託会社など
民事信託:受託者が報酬を受け取らない信託契約。家族などの個人でも受託者になれる
事業承継信託は商事信託であり、現オーナーが信託銀行などに自社株式を信託し、一定の条件に沿って後継者へ自社株式を引き渡す手続きとなります。
事業承継信託にはいくつかの方法がありますが、代表的なものとして「遺言代用信託」を紹介します。遺言代用信託において、関係する三者は次のようになります。
委託者:現オーナー
受託者:信託銀行など
受益者:現オーナー
第2受益者:後継者
現オーナー(委託者かつ受益者)は、信託銀行(受託者)と信託契約を交わし、自社株式を信託銀行に信託します。信託銀行は、議決権行使などの常任代理人としてオーナーを選任するため、オーナーは従来と同じく議決権の行使や配当などの受け取りができます。
オーナーが亡くなると信託契約は終了し、信託契約に基づいて、信託銀行は自社株式を後継者(第2受益者)に交付する仕組みです。
遺言代用信託におけるメリットのひとつは、自社株式が確実かつスムーズに後継者へと引き継がれる点です。相続の場合は、手続きが終わるまでは自社株式が相続されないので、経営に空白期間が生じてしまう可能性があります。しかし、遺言代用信託ではオーナーの死亡と同時に受益権が後継者に移動するので、空白期間は生じません。
「争族」を避けるには「遺留分」対策が不可欠
ここまで、後継者に自社株式を集中させるための対策として、遺言・生前贈与・事業承継信託を紹介してきました。しかし、この3つの対策においては「遺留分」の存在について注意する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に、遺産における最低限の取り分を保証する制度です。後継者にすべての自社株を相続させても、ほかの法定相続人から「遺留分を受け取りたい」という請求(遺留分減殺請求)を受けたら、相当する財産を分割しなければなりません。
さらに、遺留分を算定する基礎財産には、生前贈与や遺贈をされた財産(特別受益)も含まれる点に注意が必要です。
全相続財産の1/2(相続人が父母のみの場合は1/3)が、全遺留分の合計(総体的遺留分)として確保されます。そこから個別の遺留分(個別的遺留分)を計算するには、総体的遺留分に法定相続割合を掛け算します。
たとえば、後継者の長男が自社株式を、次男が同額の不動産を相続する遺言を作成したとしましょう。
法定相続人:長男(後継者)・次男
自社株式:4000万円(長男が相続)
不動産:4000万円(次男が相続)
しかし、相続までに自社株式が、長男の努力によって4000万円から1億6000万円へと上昇しました。すると、次男の個別的遺留分は、(1億6000万円+4000万円)×1/2×1/2=5000万円となります。次男から遺留分減殺請求を受けた場合、長男が努力して自社の価値を上げたにもかかわらず、自社株式が分散する皮肉な状況に陥ってしまうのです。
このように相続までに自社株式の価値が上昇すると、自社株式が分散したり、後継者が相続できる自社株式以外の財産が少なくなったりといった事態が生じるのが難点です。
遺留分の放棄
「遺留分の放棄」は、被相続人の生前に、相続人が遺留分減殺請求をする権利をあらかじめ放棄する手続きです。具体的には、オーナーなどが後継者以外の相続人に、遺留分を放棄するよう頼んでおく方法などが考えられます。
ですが、遺留分の放棄は要件が厳しく、相続人は自社株式以外の遺留分をすべて放棄することになります。加えて、相続人が家庭裁判所に申し立てをして許可を受ける必要があったり、家庭裁判所が下す許可・不許可の判断が統一されない可能性があったりなどの事情から、実際にはあまり利用されていません。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
対策4:遺留分特例
ここまでの解説をまとめると、事業承継においては、経営者としては、後継者に自社株を集中させたいですが、他の相続人関係者などとの相続紛争・事業承継紛争が心配ということになります。
そこで、遺言や生前贈与で後継者に自社株を集中させることが一般的な対応策となります。柔軟に事業承継したいということで事業承継信託にて後継者に会社の経営権や財産権を集中させることも多いです。
ただ、相続までに自社株の価値が上昇すると、相続財産のほとんどが自社株式ということとなってしまい、後継者に自社株式を集中して相続させることから、他の相続人から遺留分の主張を受ける可能性が高いです。その場合、否応なく、自社株式が分散してしまったり、後継者が相続することができる自社株式以外の財産が非常に少なくなってしまったりします。
そこで、遺留分の事前放棄制度がありますが要件が厳しく遺留分をすべて放棄することにもなりあまり使われていません。
しかし、この点は、遺留分特例(除外合意・固定合意・付随合意)で解決することができます。
遺留分特例とは、事業承継を円滑に進めるために、中小企業庁が2008年から施行している「経営承継円滑化法」の一つで、正式には「遺留分に関する民法の特例」(民法特例)といいます。
相続人全員の合意があれば、オーナーから後継者に贈与等をされた自社株式について、次の3つの合意を利用できる制度です。
- 除外合意:自社株式を遺留分算定基礎財産に含まない
- 固定合意:遺留分算定基礎財産に参入する自社株式の価額を、合意時の時価に固定
- 付随合意:除外合意・固定合意のどちらか、ないし両方の合意をしたうえで、次の2つを遺留分算定基礎財産
- 後継者:自社株式以外の財産
- 非後継者:贈与された財産
先ほどの例を使って説明します。
自社株式:4000万円→1億6000万円に上昇(長男が相続)
不動産:4000万円(次男が相続)
除外合意の場合は、自社株式が除外されるので、遺留分算定基礎財産は4000万円です。それぞれの個別的遺留分は、4000万円×1/2×1/2=1000万円となります。
固定合意の場合は、自社株式の価額が4000万円に固定されるので、遺留分算定基礎財産は8000万円です。それぞれの個別的遺留分は、8000万円×1/2×1/2=2000万円となります。どちらの場合も、自社株式の価値が上昇しても影響を受けません。
付随合意は、除外合意・固定合意のいずれか、ないし両方を選んだうえで選択できるオプションのようなものです。この民法特例では後継者が有利になってしまうため、非後継者には不公平感が生じ、同意を得るのが難しくなりがちです。そのため、非後継者においても、贈与などで得た財産を基礎財産から外せるようになっています。
まとめ
後継者に自社株式を集中的に相続させるために、オーナーが生前にできる対策には、「遺言」「生前贈与」「事業承継信託」「遺留分特例」が挙げられます。
遺言や生前贈与は一般的ですが、「争族」トラブルを生まないためには、公正証書遺言の作成や事業承継税制の活用など、専門家によりよい対策をアドバイスしてもらうのが効果的です。事業承継信託は、オーナーの死亡と同時に後継者に自己株式が引き継がれるため、経営に空白期間が生じないメリットがあります。
この3つの対策においては、後継者以外の相続人から遺留分減殺請求を受けないように手を打っておく必要があります。事前に相続人全員の合意を得て、遺留分特例を活用できる環境を作っておくことが大切です。
「争族」を避けて事業承継を円滑に進めるには、後継者以外の相続人に対する配慮が求められます。相続のプロである弁護士なら、豊富な実例をもとに適切な対策をアドバイスできますので、ぜひ相談してみてください。