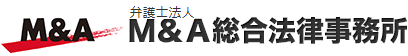無償で事業譲渡をした時に発生する税金とは?手続きや流れ、注意点をわかりやすく解説

事業承継の一手段として、自社の事業を親族や従業員などに無償で引き継ぐことは、時折考えられる選択肢です。しかし、無償での事業譲渡を実行する際は、譲渡側と譲受側の両方に税金が課されることを覚えておくことが重要です。
課税を受けた結果、無償で事業を譲渡することのメリットが小さくなったり、無くなってしまったりすることもあるため、注意深く選択することが必要です。
この記事では、無償での事業譲渡の取引で発生する税金について、譲渡側と譲受側に分けて説明します。無償での事業譲渡の手順や注意点なども紹介していますので、ぜひご参考ください。
事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社が自身の事業全体または一部を別の会社に渡すM&A手法をさします。ここでいう「事業」とは、事業に関するヒト・モノ・無形資産のことで、借金だけでなく特許・商標・顧客リスト・契約なども含みます。ただし、事業の一部としての個々の資産を単独で譲渡することは、事業譲渡とはみなされません。
企業の経営者が自身の子供・孫・甥・姪や従業員などに事業を承継する際、無償の事業譲渡が用いられるケースが多いです。このような親族や従業員に対する事業の引き継ぎは、中小企業にとってよく見られる選択肢です。実際、2017年版「小規模企業白書」によれば、後継者が決まっている小規模企業のなかでは、90%以上が家族内でのビジネス継承を選んでいることがわかっています。
さらに、事業継承ガイドラインのデータを見ると、経営者が長く事業を続けるほど、家族間での事業承継の割合が高くなる傾向があり、具体的にいうと経営者が事業を10年以上続けている企業では70%以上、30年以上続けている企業では約90%以上が家族内でビジネスを承継していることがわかります。
参考:中小企業庁「2017年版小規模企業白書」
中小企業庁「事業承継ガイドライン」
事業譲渡と株式譲渡の主な違い
M&Aの実施を計画する際は、自社の状況や目指す目標に沿って最適な手法を選ぶことが重要です。事業譲渡以外でM&Aに使える主な手法としては、株式譲渡が挙げられます。
株式譲渡とは、売り手の保有する株式を売却し、その結果として経営権を移す手法のことです。
事業譲渡では企業が運営する事業そのものが売買の対象になる一方で、株式譲渡では企業の所有する株式が売買の対象になります。また、事業譲渡では、従業員・取引先などとの権利義務関係の引き継ぎについて一つ一つ対応が求められる一方で、株式譲渡の場合には権利義務をまとめて引き継ぐことが可能です。
無償の事業譲渡を行うメリット・デメリット
無償の事業譲渡では、事業を承継する後継者側で譲渡資金を用意する必要がなくなります。そのため、後継者を確保しやすくなり、事業を継続できる可能性が高まります。
その一方で、無償の事業譲渡であっても、一定の税金が課されます。詳しくは次章以降で解説していますが、事業の譲渡側と譲受側それぞれに税金が課される点に注意が必要です。
【譲渡側】無償の事業譲渡での税金
無償での事業譲渡にあたって発生する可能性のある税金の一例を紹介すると、所得税・贈与税・法人税です。
無償で事業譲渡を行う場合、譲渡側と譲受側が個人なのか法人なのかによって、税務の扱いが異なる点に注意しましょう。まずは、無償の事業譲渡において譲渡側にかかる税金と、それに対応する会計処理の例を解説します。
所得税
所得税は、譲渡側が個人の場合に課せられる可能性がある税金です。個人が自身の事業を譲渡する際、譲受側が個人であるか法人であるかにより、税金の扱いが変わります。
個人から個人への事業譲渡であれば、譲渡側に所得税は課されません。一方で、個人から法人への事業譲渡では、譲渡側は「みなし譲渡所得税」と呼ばれる税金を支払う必要があります。
みなし譲渡所得税は、実際には対価を受け取っていないにも関わらず、税務の規定によって、まるで自身の資産を時価で売却し利益を得たかのように扱われ、その時価に対して所得税が課せられます。
法人税
法人税は、譲渡側が法人の場合に課せられる税金です。法人が自身の事業を無償で譲渡する場合、実際には現金を得ていないものの、法人税法上はその事業の時価を譲渡価額と評価し、そこに対して法人税(約34%)が課せられます。
なお、ここでいう時価とは、「その販売若しくは譲渡をした資産の引き渡しの時における価額又はその提供した役務につき通常得べき対価の額に相当する金額」(法人税法 第22条の2)であり、具体的には「原則として資産の販売等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額」であることが規定されています(法人税基本通達 2-1-1の10)。
そもそも法人税法においては、法人税の課税標準となる所得金額は益金の額から損金の額を控除した金額とされ、益金の額には有償もしくは無償による資産の譲渡による収益の額が含まれる旨が規定されています(法人税法 第21条、同22条)。つまり、無償による事業譲渡では、その取引から収益が生じたものとして益金の額(譲渡価額)を算出し、法人税の課税対象とするのです。
ここからは、無償の事業譲渡を行った際の会計処理について解説します。譲受側が個人で、その個人が譲渡側の法人の従業員である場合、会計処理上は賞与として扱われます。一方、その個人が譲渡する会社の従業員でない場合、会計処理上は寄付としてみなされます。
譲渡側が法人である場合、会計処理上は寄付とみなされ、その事業の時価に基づいて法人税が課せられます。無償での事業譲渡の各ケースにおいて、会計処理の一例を以下にまとめました。
【法人が法人に対して無償で土地を譲渡したケースの会計処理】
| 借方 | 貸方 |
| 土地譲渡原価 500万円
寄付金 3,000万円 |
土地 500万円
土地譲渡収益 3,000万円 |
【法人が雇用関係にある個人に対して無償で土地を譲渡した場合の会計処理】
| 借方 | 貸方 |
| 土地譲渡原価 500万円
賞与 3,000万円 |
土地 500万円
土地譲渡収益 3,000万円 |
【法人が雇用関係のない個人に対して無償で土地を譲渡した場合の会計処理】
| 借方 | 貸方 |
| 土地譲渡原価 500万円
寄付金 3,000万円 |
土地 500万円
土地譲渡収益 3,000万円 |
消費税は課されない
無償の事業譲渡は金銭的な対価が伴いません。そのため、税法上は寄付・贈与とみなされ、消費税は課されません。
【譲受側】無償の事業譲渡での税金
無償での事業譲渡の場合、その事業を受け取った側では、所得税・法人税・贈与税などの税金が課されることがあります。以下では、それぞれの税務について詳しく説明します。
所得税
譲受側が個人の場合、所得税が課せられます。無償で事業を譲渡する場面において、譲渡側が法人で譲受側が個人の場合、その二者の雇用関係によって譲受側の税務が異なります。
もしもこれら二者が雇用関係にあるならば、給与取得として会計処理を行います。一方、雇用関係が存在しない場合、一時的な所得として会計処理する決まりです。
法人税
個人から法人へ、あるいは法人から法人へ無償で事業譲渡した場合、譲受側の法人は資産を時価で取得したとみなされて「受贈益」が発生し、それに対する法人税が課されます。
以下に会計処理の一例を示します。
【法人が法人に対して無償で土地を譲渡したケースの会計処理】
| 借方 | 貸方 |
| 土地 3,000万円 | 受贈益 3,000万円 |
贈与税は個人から個人への事業譲渡で課せられる
個人が他の個人に事業を無償で譲渡する際、譲受側は譲渡された事業の時価に基づいて贈与税を支払わなければなりません。この贈与税は「累進課税」で、受け取った事業の価値が高ければ高いほど、税率も高くなります。
ただし、一般的な税率とは別に特定の条件下で適用される「特例税率」も存在し、これを利用すれば課される税率を下げることが可能です。
所得税・法人税・贈与税の税率表【参考】
所得税の税率表は以下のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付する。
なお、無償の事業譲渡では、一時所得に対して所得税が課されることになります。一時所得の金額は、以下の計算式で求められます。
- 総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を算出します。
続いて、法人税の税率表を下記にまとめました(普通法人のケースを抜粋)。実際には以下の法人税に加えて、法人住民税・事業税が課されます。
|
区分 |
開始事業年度(令和4年4月1日以降) | |||
| 普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
| 適用除外事業者 | 19% | |||
| 上記以外の普通法人 | 23.2% | |||
最後に、贈与税の税率表を紹介します。上が一般税率、下が特例税率です(基礎控除額は110万円)。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円以超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円以超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | - | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
国税庁「No.1490 一時所得」
国税庁「No.5759 法人税の税率」
国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
無償の事業譲渡と事業承継税制
事業譲渡にかかる贈与税について、特定の条件を満たすとその税金の課税が猶予される制度「事業承継税制」も存在します。事業承継税制を利用すれば、特定の条件をクリアした場合、贈与税の課税を引き継ぎ時点で行わず、延期することが可能です。条件を満たし続ける限り贈与税の課税は猶予され続けていき、最終的には免除も可能になります。
事業承継税制はこれまでに2度改正されており、現在では比較的簡単に利用できるようになっているため、贈与税の課税を避けたい場合には積極的に活用するとよいでしょう。
ここからは、事業承継税制の特例措置を受けるための要件を解説します。まず、経営者自身の要件は以下になります。
- 相続・贈与の時点で会社の代表者である
- 後継者を除いた一族の中で筆頭株主である
- 一族で議決権50%を超える株式を保有している
- 贈与により代表を退任する(もしくは退任済み)
次に、後継者の要件は以下のとおりです。
- 相続・贈与の直後に会社の代表者である
- 一族の中で筆頭株主である
- 一族で議決権50%を超える株式を保有している
- 贈与の場合は役員就任後に3年以上が経過し、かつ20歳以上となっている
最後に、会社の適用要件です。
- 中小企業者であること
- 従業員数が1人以上であること
- 資産管理会社・風俗営業会社でないこと
事業承継税制を活用する場合、適用を受けるまでには、複雑な要件や適用後に継続的に満たすべき要件・報告義務など、考慮すべき事項がたくさんあります。事業承継税制を活用する際は、税務の専門家のサポートを受けましょう。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
国税庁「個人版事業承継税制」
無償の事業譲渡の手続きや流れ
会社が無償で事業を譲渡する場合、基本的には以下の手順に沿って進めていく必要があります。
- 取締役会における決議
- 無償事業譲渡契約書の作成・締結
- 事業譲渡の通知・告知
- 株主総会における決議
- 株式買取請求の実施
- 事業譲渡の効力発生
これらの手続きを全て終えて、初めて無償の事業譲渡が正式に成立し、法的に有効になります。
とはいえ、無償の事業譲渡の場合、会社の株式のほとんどをオーナーである経営者が保有しているうえに、親族内で承継が行われるケースが多いため、取締役会における決議や無償事業譲渡契約書の作成・締結、事業譲渡の通知・告知、株主総会の特別決議による承認などを省略し、取引先など外部の利害関係人に事後通知を行うのみで手続きを完了するというケースも多く見られます。
そのため、実務上、無償の事業譲渡の手続きについて留意しておくべき必要性はそれほどありませんが、ここでは参考情報として解説します。
取締役会における決議
譲渡先の選定や交渉などを経て、事業譲渡の実施を正式に決定した後には、具体的な譲渡計画を立てるのが一般的です。そして、譲渡計画を立てた後は、その計画を会社の取締役会で承認してもらうことが求められます。
取締役会が設けられていない会社の場合は、全取締役のうち過半数の同意を得なければなりません。
無償事業譲渡契約書の作成・締結
無償事業譲渡の契約書には、譲渡日・譲渡の目的・譲渡する資産の詳細・保証責任・秘密保持義務・競争禁止義務・その他の協議事項など、話し合った内容全てを含めます。
事業譲渡の通知・告知
事業譲渡の実施にあたっては、決定された事業譲渡の内容と株主総会の日程を、効力が発生する日の20日前までに株主全員に知らせる必要があります。この手続きは、官報公告や電子公告などによって実施されます。
株主総会における決議
株主総会の特別決議が求められるケースは以下のとおりです。
- 会社が全ての事業を他社に譲渡する場合
- 会社の重要な一部の事業を他社に譲渡する場合
- 他の会社から全ての事業を譲り受ける場合
- 事業全体の賃貸・経営委託・損益全体に関する契約、またはそれらに準ずる契約の締結・変更・解除
株主総会の特別決議で承認を得るためには、議決権を持つ株主の過半数以上が会議に出席し、そのうち3分の2以上が賛成することが必要です。
ただし、会社法では一部の簡単な事業譲渡や手続きの省略が可能な事業譲渡の場合、株主総会での特別決議は必要ないとされています。
株式買取請求の実施
株主総会の特別決議は、議決権を持つ株主の過半数以上が集まった状況で、その集まった株主の議決権の3分の2以上が賛成した場合に有効となります。たとえこの特別決議が可決された場合でも、反対した株主には、その利益を守るために、会社に対して自身の株式を買い取るよう請求できる権利が与えられます。
事業譲渡を行う会社には、この株式買取請求の権利が存在することを、反対した株主に対して知らせる義務があります。そして反対した株主は、株主総会で反対票を投じた後から、事業譲渡の効力が発生する日の前日まで、その権利を行使できます。
事業譲渡の効力発生
事業譲渡が正式に成立し、その効力が発生する日を迎えると手続きは終了します。しかし、その後も事業の実際の引き継ぎ作業が必要で、時間がかかります。
特に事業譲渡に従業員の引き継ぎも含まれる場合、その日以降の事業運営のマネジメントが非常に重要です。この引き継ぎの期間は、「PMI(Post Merger Integration)」と呼ばれています。
PMIの期間中には、スムーズな業務移行を保証するために、譲渡側の経営者が譲受側と協力し、一定期間にわたって助言や支援を提供することがあります。
無償の事業譲渡の節税対策
法人が事業譲渡を有償で行う場合、「譲渡する資産と負債の差額」よりも「譲渡価額」が上回った場合、その利益に対して譲渡側に法人税が課されます。また、有償での事業譲渡では、譲渡側に消費税も課されます。
これに対して、無償での事業譲渡では、譲渡側に対して、譲渡する資産の時価を譲渡価額と評価し、そこに対して法人税が課されます。また、有償での取引とは異なり、無償の事業譲渡では消費税は課されません。
さらに、事業譲渡における課税は対象会社においてなされますが、有償での事業譲渡のケースで、配当などで売却対価をオーナーへ還流するような場合、さらにオーナーに対しても課税が生じる可能性があります。つまり、二重に課税される可能性があるのです。
事業譲渡における二重課税の仕組みを簡単に説明すると、有償譲渡の場合は譲渡対価(無償譲渡の場合はその事業の時価を譲渡価額と評価したもの)に対して、約34%の法人税が課されます(課税対象は事業譲渡を実施した会社)。その後、例えば経営者のもとに配当金等で譲渡所得を渡すときには経営者に所得が生じるため、所得額に対して20.315%の所得税(地方税・復興特別所得税を含む)が課されます(課税対象は配当等の所得があった経営者)。
なお、こうした二重課税を避けたり軽減したりするための方法としては、例えば経営者に譲渡所得を渡すのではなく、法人に譲渡所得をとどめておき、法人の経費として使用していく施策(例:経費で社用車を購入するなど)が挙げられます。
以上の点を踏まえると、有償ではなく無償で事業譲渡を行った方が譲渡側にとって節税効果が期待できるケースがあります。この点について、詳しくはM&Aの税務に関する専門家からアドバイスを受けましょう。
本章では、事業譲渡の実施にあたって、譲渡側企業で検討される主な節税対策を3つ解説します。
- 役員退職慰労金を利用する
- その他の経費を活用する
- 株式譲渡の手法を用いる
それぞれの内容を理解し、自社の節税対策にお役立てください。
役員退職慰労金を利用する
事業譲渡を通じて計上された利益は、その年度の法人税の対象となるため、利益を減らせばそれだけ法人税も少なくなります。ここで考えられる方法の一つとして、役員退職慰労金の活用があります。
例えば、事業譲渡を行った年度に社長が辞任し、社長に対して退職慰労金を支払うといった戦略が当てはまります。退職慰労金は経費として計上できるため、利益を抑えることが可能です。さらに、退職慰労金は税金の計算上、優遇措置があるため、法人税を抑えつつ社長個人へ資金を移すことができます。
ただし、退職慰労金を活用する際は以下のような注意点もあります。
- 退職慰労金の金額は無制限に高く設定することができない
- 個人の所得税は金額が増えるにつれて税率も上がる累進制なので、一定の金額を超えると法人税よりも高額になる可能性がある
これらの点を考慮して、利益とリスクを見極めながら退職慰労金を活用すると良いでしょう。
その他の経費を活用する
事業譲渡で計上された利益に対する税金を減らす方法として、他の経費を増やすという戦略もあります。例えば、事業を売却した年度に大規模な広告キャンペーンを行うなどして広告宣伝費を増やせば、法人税などの税金を大幅に減らせる可能性があります。
ただし、こうした経費増加による節税策には注意が必要です。なぜなら、広告費などを増やすことで現金が会社から出て行くため、最終的に会社に残るお金が減る可能性があるためです。したがって、ただ無駄に資金を使うのではなく、会社にとって必要で効果的な支出をすることが重要です。
株式譲渡の手法を用いる
法人の事業承継では、事業譲渡ではなく株式譲渡の手法を用いた方が、結果的に大きな節税効果が期待できることもあります。
M&A手法の種類や取引が有償で行われるか無償で行われるかによって、かかる税金は変わります。まずは原則として、有償での株式譲渡および事業譲渡で譲渡側に課される主な税金を下表にまとめました。
| M&A手法 | 譲渡側に主に課される税金 |
| 株式譲渡(有償) | 株式の譲渡益に対して20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用される。 |
| 事業譲渡(有償) | 事業の譲渡益に対して、法人住民税・事業税を含めて約34%の法人税が課される(譲渡側が法人の場合)。
事業譲渡により譲渡する資産のうち、消費税の課税対象となる資産に対して10%の消費税が課される。 |
次は、法人が株式譲渡および事業譲渡を無償で行う場合に、譲渡側にかかる主な税金をまとめて紹介します。
| M&A手法 | 譲渡側に主に課される税金 |
| 株式譲渡(無償) | 個人に対して譲渡する場合には、譲渡側に税金は課されない。一方で、法人に対して無償で株式譲渡を行う場合は、
時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得金額に対して20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が課される。 |
| 事業譲渡(無償) | 取引の対象となる事業の時価を譲渡価額と評価し、そこに対して法人住民税・事業税を含めて約34%の法人税が課される。 |
上記の表を単純に比較すると、株式譲渡の方が節税効果が大きいと判断できます。
とはいえ、事業譲渡の場合、オーナーが承継したい資産と保持したい資産を取捨選択できる点が特徴的です。子どもに事業を承継させる一方で、一部の資産については当面の間所有しておきたいといったケースもあります。また、不動産についてはアパート・マンションを経営したり土地を売却したりなど、相続税の節税方法としてさまざまな手法が活用できるため、不動産は事業承継時に後継者である子供に引き継がず、相続時に引き継ぎを図るケースも少なくありません。
以上の点を踏まえて、どちらのM&A手法が自社にとって最適なのかは一概には判断できません。実際にM&Aによる事業承継を行う際は、節税面以外の要素も踏まえてM&A手法を決定するケースが一般的です。
例えば、株式譲渡は、事業譲渡と異なり、企業の経営権そのものが移行する方法であるため、譲受側でどの資産を引き取るかを選べません。このため、譲受側には、企業の負債やまだ表に出ていない簿外債務を引き受けるリスクが伴います。
無償での株式譲渡を考える際も、事業譲渡の場合と同様に、経営者の親族や従業員などが譲受側になることが多いです。そのため、譲受側に企業の負債や簿外債務を負わせたくないと思う経営者は多いでしょう。
以上の点も踏まえて、節税対策を考える際は、M&Aの専門家に相談して自社に適したM&A手法を慎重に比較検討することが大切です。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
無償の事業譲渡における注意点
最後に、無償の事業譲渡を実施する際の注意点として、以下の3つを解説します。
- 債権者に対する個別の説明が求められることがある
- 無償譲渡と有償譲渡のどちらが有益なのか比較検討する
- 有償譲渡と同様に従業員に対する配慮が必要
それぞれの内容を把握し、後悔のない形で事業譲渡を成功させましょう。
債権者に対する個別の説明が求められることがある
事業譲渡では、債務を引き継がない場合、債権者保護の手続きは特別必要とされません。しかし、無償の事業譲渡では、譲渡側は対価を得ることなく事業を譲渡するため、収益力が低下する可能性があります。
そのため、無償事業譲渡が債権者に不利益をもたらすと判断される場合、契約が事後に取り消されることもあり得ます。債務を引き継がない事業譲渡の場合には債権者保護手続き法律上は不要であるとはいえ、今後も良好な関係性を維持していくためにも必要なコミュニケーションであると考えて、債権者に対して事前に説明を行うことが望ましいです。
無償譲渡と有償譲渡のどちらが有益なのか比較検討する
親族間の場合、無償の事業譲渡を選ぶケースが一般的ですが、実際の譲渡資産に応じて、有償の事業譲渡と無償の事業譲渡のどちらがメリットがあるのかを検討することが重要です。
例えば、不動産の譲渡では、買取り・賃貸契約・使用貸借のいずれを選択するかによって、税負担が異なります。例を挙げると、無償の事業譲渡の場合、使用貸借にすることで贈与税は課されないものの、相続税の影響を考慮する必要はあります。
こうした点を踏まえて、税務の専門家に確認を取りつつ無償譲渡と有償譲渡それぞれにかかる税金を慎重に比較検討する必要があります。
有償譲渡と同様に従業員に対する配慮が必要
無償で行う場合であれ有償で行う場合であれ、事業譲渡時には従業員へのサポートが非常に重要です。事業譲渡の前後において、従業員の雇用は通常継続されますが、下表に示した変化・不安などを理由に従業員にストレスがかかる場合も少なくありません。
法律上求められる手続きではありませんが、従業員との良好な関係を維持し、モチベーション低下や退職のリスクを避けるためにも、可能な限り従業員への適切なフォローを行いましょう。
| 従業員のストレス要因 | 対処法 |
| 職場環境や人員配置の変更 | 従業員には新しい環境や部署の変更による不安やストレスが生じる可能性があります。そのため、従業員の希望に合った配置や待遇を実現するため、最大限の配慮を行いましょう。
転籍する従業員に対しては、譲渡側の企業が待遇や配慮について話し合い、詳細な内容を丁寧に伝えます。 もし従業員が転籍に同意しない場合、譲渡側との雇用関係を維持しながら、譲受側に出向してもらう方法も検討できます。 |
| 有給休暇 | 従業員の有給休暇は勤続年数によって異なりますが、譲渡側企業との契約が終了すると、有給休暇の権利がなくなり、転籍後に引き継がれない可能性があります。
従業員が転籍する場合は、譲受側にこの点を事前に伝えておっき、従業員の有給休暇が引き継がれるよう、事業譲渡契約書にも明記することが重要です。 |
| 譲受企業の経営方針や就業規則になじめない | 一部の企業では、従業員が新しい環境になじむために、「保証期間」を設けています。つまり、一定期間は以前と同じ労働条件で働くことができるということです。
従業員が転籍する場合は、前述の有給休暇と同様に、事業譲渡契約書に従業員の働き方に配慮した項目を追加することがおすすめです。 |
| 退職金が減額される可能性 | 事業譲渡に伴い、勤続年数がリセットされることで、退職金が減額される可能性に不安を感じる従業員も多いです。
一般的な対策としては、「譲受側が勤続年数を引き継ぐ」「譲渡側が転籍する従業員に対して退職金を支払う」などが採用されます。 事業を譲渡する際には、税金だけでなく、転籍する従業員の「退職金」についても考慮することが重要です。 |
取引先に対する配慮も求められる
事業譲渡において、取引先との契約関係を買い手に移す場合、それぞれの取引先からの同意が必要となります。実務上、同意を得るために各取引先に通知し、それぞれから同意書をもらうのが一般的です。しかし、取引先が多ければそれだけコストもかかるわけで、その上、全ての取引先から同意をもらえるとは限りません。
特に、中小企業の場合、取引先との人間関係や取引内容が経営者の手に集中していることが多く、そういった企業が事業譲渡を行うと、取引のペースが落ちてしまう可能性もあります。
また、計画が早い段階で取引先に知られてしまうと、彼らからの反対や取引停止が起こるリスクも考えられます。そのため、情報の管理には十分な注意が必要です。具体的には、情報管理には細心の注意を払いつつ、取引先に相談する場合にも信頼できるキーパーソンに限定し、慎重に手順を進めていくことが求められます。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
まとめ
この記事では、無償での事業譲渡の取引で発生する税金について、譲渡側と譲受側に分けて説明しました。
無償の事業譲渡では、譲渡契約書の内容が簡素になる傾向があるほか、契約書自体を作成しないケースも見られます。しかし、後々のトラブルを避けるためにも、専門家のサポートを受けて無償事業譲渡契約書を確実に作成・締結しておくことが大切です。
また、節税面から見て自社に適したM&A手法を選ぶ際も、専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。