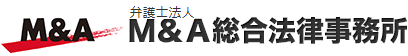後継者がいない場合の事業承継の方法とポイント

- 後継者不足を理由に廃業する日本の中小企業
- 廃業には多くのデメリットが伴う
- 後継者不足による廃業は「事業承継M&A」で回避できる
- 親族内承継
- 従業員承継
- 会社の売却(事業承継M&A)
- 事業承継M&Aには入念な準備が必要
- 準備のスタートは60歳が目安
- 自社の課題を明らかにする
- 事業承継M&Aを成功させるための経営改善
- 事業承継の実行プロセス①親族内承継・従業員承継の場合
- 事業承継計画の作成
- 関係者との調整
- 承継の実行
- 事業承継の実行プロセス②会社売却(事業承継M&A)の場合
- 事業承継M&A仲介機関の選定
- 事業承継M&A売却条件を具体的に提示する
- 自社の事業内容を評価してもらう
- 交渉~基本合意書の作成
- デューデリジェンス(事業調査)
- 最終契約の締結
後継者不足を理由に廃業する日本の中小企業
近年、会社の業績自体は決して悪化していないのに、廃業の道を選ぶ中小企業が増えています。中には、今後さらなる成長が見込めるにもかかわらず、廃業する以外に選択肢がなくなってしまうケースすら存在します。
その原因は、経営者の高齢化と後継者不足にあります。
つまり、現経営者が年齢を理由に事業から引退しなければならない一方で、会社の経営を引き継ぐ跡取りもいない中小企業の存在が、近年非常に目立つ事態となっているのです。
そうした会社は、事業を継続する体力が残っていたとしても、廃業という選択を余儀なくされてしまいます。
この点、日本社会は急激な少子高齢化に見舞われています。こうした社会状況を考えると、後継者不足による廃業を選ぶ中小企業が増加してしまうのは、やむを得ない側面があるでしょう。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
廃業には多くのデメリットが伴う
しかし、廃業には様々なデメリットが伴います。どんなデメリットがあるか把握しないまま廃業を迎えてしまうと、思わぬダメージを被る可能性があります。
事業用資産を売却しなければならない
たとえば、不動産や機械・什器類など、これまで事業に用いていた資産を売却しなければなりません。事業を廃止する以上、事業用資産には使い道がなくなってしまうからです。
十分な売却益を確保できるのならば良いのですが、思うような値段で売却できない場合も少なくありません。もっと深刻なケースとして、そもそも買い手が見つからないという場合も考えられます。売却できない場合は、やむなく自費で処分せざるを得ません。
事業用資産の売却がうまく進まなければ、廃業には想定外のコストがかかってしまうことになるのです。
従業員の再雇用先を確保しなければならない
これまで事業の発展に貢献してくれた従業員を、廃業によって無職の状態にしてしまうのは何としても避けたいところです。廃業のタイミングは、従業員の再雇用先が確保された段階にすべきです。
そのため廃業前の時期には、従業員が転職活動に打ち込めるように、勤務時間を調整する必要があります。特に年齢などの関係で、自ら転職先を見つけるのが難しい従業員に対しては、会社の側も可能な限り便宜を図らなければならない場面も出てくるでしょう。
取引先との関係の清算や債務整理をしなければならない
廃業を円滑に進めるには、取引先との関係をうまく清算する必要があります。取引先の事業にダメージを与えないように、計画的に取引を縮小していかなければなりません。
また、取引先に対して債務を抱えている場合は、廃業までにしっかり返済しておくことも必要です。銀行からの借入金がある場合は、その返済もしておかなければなりません。
つまり多くの場合において、廃業をするにはまとまった資金が必要となるのです。廃業に必要な資金を事業用資産の売却によって調達できれば良いのですが、資金調達がうまくいかなければ、廃業後の生活を圧迫してしまうことにもなりかねません。
後継者不足による廃業は「事業承継M&A」で回避できる
このように、廃業には多くのデメリットがあります。もっとも、早い段階から余裕をもって「事業承継」に取り組んでおけば、後継者不足による廃業という結末を回避することが可能です。
とはいえ、一口に「事業承継」といっても様々な手法があります。自社に適した事業承継のやり方を見極めなければ、廃業を上手に回避することはできません。
そこで、事業承継の手法にはどのような種類があるのか、まずは簡単に見ておくことにしましょう。大きく「親族内承継」「従業員承継」「会社の売却」の3つに分けることが可能です。
親族内承継
もっともオーソドックスな事業承継として、子ども等の親族から後継者を探す「親族内承継」という手法が挙げられます。
親族以外の後継者と異なり相続制度を利用できるので、会社財産や株式を包括的に承継できるというメリットがあります。心情的な面でも、関係者から後継者として受け入れられやすいので、従来は親族内承継が一般的でした。
ただ、価値観の多様化した現代では、経営者の親族が必ずしも家業を引き継いでくれるとは限らなくなっており、後継者不足の大きな一因となっています。
こうした状況の中で親族内承継を成功させるには、会社を引き継ぐことが親族にとっても魅力的な選択肢となるように、「企業価値の磨き上げ」や「経営体制の強化」に注力する必要があります。
また、後継者となる親族が安心して事業を承継できるように、時間的に十分な準備期間を設けるよう計画しておくことも大切です。
従業員承継
親族内承継以外にも、従業員の中から後継者を探す「従業員承継」という手法があります。
「親族内に後継者候補がいない」という消極的な理由で選ばれることのある手法ですが、もともと従業員として事業に携わってきた人材を後継者にするので、親族に比べて承継のための準備期間が短くて済むというメリットがあります。
一方で、相続による包括的な財産移転ができないことによるデメリットもあります。
というのも、現経営者が所有する株式を後継者に引き継ぐ際に、親族の場合は相続制度を利用できますが、従業員に対しては有償譲渡する必要があります。仮に会社の株式を無償譲渡しようものなら、会社の資本が空っぽになってしまうので望ましくないからです。
したがって、せっかく後継者候補と言うべき有能な従業員がいたとしても、その従業員に株式を買い取るだけの資金力がなければ、従業員承継を実施することは非常に難しくなってしまうのです。
それと同時に、後継者候補の従業員が「大金を払ってでも承継する価値がある」と思うような会社でなければなりません。そのためには、親族内承継の場合と同様に、「企業価値の磨き上げ」や「経営体制の強化」が必要となってきます。
会社の売却(事業承継M&A)
第三の選択肢として、「会社を売却する」という方法もあります。別の会社に対して「株式譲渡」や「事業譲渡」を行うことで、廃業という事態を回避します。いわゆるM&Aと呼ばれる手法を、会社の事業承継に応用するやり方です。
「売却」という言葉からは、後ろ向きな選択肢であるかのような印象を持ってしまうかもしれません。しかし、「事業の継続性」という意味では、非常に前向きな選択肢だと言えるのです。
というのも、株式譲渡や事業譲渡によって会社を売却した場合、会社の事業自体は変わらず継続されます。従来の雇用関係や取引関係も、買収企業によってそのまま引き継がれます。特に、株式譲渡による売却ならば、会社名を残すことすら可能です。
また、引退する経営者からすると、売却の対価としてまとまった資金が手に入るというメリットもあります。資産を失うおそれのある廃業に比べると、大変うまみのある方法だと言えるでしょう。
もっとも、会社の売却はあくまでも、買収企業との間で締結する契約です。相手との交渉次第では、不利な条件で妥協しなければならなくなったり、最悪の場合には売却自体が破談になったりする可能性もあります。
契約を円滑に進めるには、買収企業にとって魅力的な会社として映るように、やはり「企業価値の磨き上げ」「経営体制の強化」が必要となります。
事業承継M&Aには入念な準備が必要
以上のように、事業承継には大きく分けて3つの方法があります。そして、いずれの場合でも事業承継を成功に導くには、その準備として「企業価値の磨き上げ」「経営体制の強化」を十分に行うことが必要です。つまり、事業承継の準備期間に行うべきことは、どの方法を用いる場合でも大きく共通しているのです。
それではここから、事業承継を成功させるために必要な準備について、あらゆる場合にあてはまる重要ポイントを詳しく解説していきます。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
準備のスタートは60歳が目安
家族経営の企業にとって、後継者問題への準備に取り掛かる時期の目安は、オーナーが60歳になった頃と考えるのが良いとされています。
現在の日本人の平均寿命を考えれば、60歳であれば、老化による体力や判断力の衰えはまだ深刻化していません。また、後継者探しや後継者候補に対する教育など、承継に向けた準備に必要な時間も余裕をもって作ることができます。
したがって家族企業の経営者は、自分が60歳になったタイミングで、後継者問題を身近な支援機関に相談すると良いでしょう。
たとえば、日ごろから懇意にしている金融機関や商工会議所に相談すれば、「事業承継診断」を受けることができます。あるいは、国の支援機関である「事業引継ぎ支援センター」に相談することもできます。
なお、後継者問題を「家族の問題」と考えて、外部に一切相談しないケースが見受けられます。しかし、こうした姿勢は決して望ましいものではありません。なぜなら、問題が先延ばしにされてしまい、気が付くと手遅れになってしまうことが少なくないからです。
自社の課題を明らかにする
後継者問題について身近な支援機関に相談することで、自社の抱える課題が見えてきます。次のステップは、ここで見えてきた課題を詳細に分析し、具体的な行動につなげるための指針を作ることです。
経営状況を客観的に分析する
後継者問題を解決する方法には、会社の売却まで含めると様々なパターンがあります。そのような選択肢を可能な限り広げるためには、「自社の強みを明確にすること」が不可欠です。自社の事業が持つ魅力を客観的に明らかにすることで、多くの人に「この会社を承継したい」と思ってもらえるようになるからです。
そこでまずは、自社の経営状況を客観的に分析することから始めましょう。
なお、ここで分析すべき対象は、貸借対照表上の資産や負債だけではありません。自社が有するノウハウ・技術の価値といった「目に見えない資産」の有無や、激変する経営環境の中での自社の地位を把握することまで含まれます。
こうした経営状況の分析を正しく行うには、「分析のための評価基準」について理解を深めることが必要です。適正な評価基準を用いることで、自社の強みを第三者に対しても説得力を持って伝えることができるようになります。
そのために、何より最新の業界動向や会計基準について知っておきましょう。業界団体や中小企業支援機関が主催する勉強会に出席して情報収集をしたり、日本税理士連合会や日本商工会議所のウェブサイトで閲覧できる「中小企業の会計に関する指針」を読み込んだりしておくことで、最新の情報を得ることができます。
また、独立行政法人の「中小企業基盤整備機構」(略称「中小機構」)が作成する「事業価値を高める経営レポート」には、自社の強みを客観的に分析するためのマニュアルが掲載されています。中小機構のウェブサイト上で閲覧することができるので、ぜひ活用してください。
事業承継にあたっての課題を可視化する
自社の経営状況について分析すると同時に、事業承継に際しての課題も可視化していきましょう。
自分の子どもや有能な役員・従業員など、すでに後継者候補が見つかっている場合には、承継のスケジュールを具体的に決めていきます。
たとえば後継者候補に対して、事業を承継する意思があるかどうか確認するタイミングを検討します。その際、後継者候補の年齢や能力を考慮して、承継に向けた教育などに必要な準備期間についても計算に入れましょう。
また、経営者自身は後継者候補による事業承継が望ましいと思っていても、場合によっては社内外から異論が出ることも考えられます。そうした事態に備えて、役員・従業員や取引先の関係者に対して、あらかじめ後継者候補の存在を伝えておきましょう。後継者候補による承継を不安視する声が出てきたら、できるだけ早い段階で不安解消のための話し合いをしておくべきです。
親族内承継を検討する場合は、相続税対策も重要になってきます。経営者が所有する株式や事業用資産など、相続の対象となる財産の範囲をなるべく早く特定しておきましょう。相続税の金額や納税方法について早い段階から見当をつけておくことで、事業承継に関する不安を最小限に抑えることができます。
一方で、後継者候補がまだ見つかっていない場合には、候補者探しに力を入れる必要があります。
その際には、社内のみならず、社外の人材に対しても広く目を向けましょう。現在はネットを通して事業承継のマッチングを行う仲介機関が数多くあるので、社外から後継者を迎えることが容易になってきています。場合によっては、自社の事業を買い取りたいという会社が見つかる可能性もあります。
なお、前項で説明した「経営状況の客観的な分析」は、後継者探しの局面において特に役立ちます。というのも、自社の後継者となることに魅力を感じてもらうには、自社の強みを明確にしておく必要があるからです。たとえば、当初は事業承継に乗り気でなかった子どもが、事業の価値について改めて理解を深めることで、後継者となる覚悟を固めてくれるケースも珍しくありません。
事業承継M&Aを成功させるための経営改善
事業承継をめぐる自社の課題が明らかになったら、事業承継を成功に導くための具体的な行動に移りましょう。
「自社の強み」を磨き上げる
現時点における後継者候補の有無にかかわらず、経営状況の分析によって明確になった企業価値、すなわち「自社の強み」をさらに磨き上げることが必要です。
この点、親族内承継を予定している会社において、相続税を節約するために、意図的に事業の価値を低下させる手法(持ち株会社の設立による株価の低下など)がとられることがあります。
しかし、小手先の節税のために事業を弱体化させてしまっては、結果的に後継者が安心して事業を承継できない事態となるおそれが出てきます。これから後継者を探す必要がある場合だけでなく、すでに後継者が決まっている場合にも、自社の強みを可能な限り高めることが非常に重要なのです。
そのために利用できる公的な支援として、「中小企業等経営強化法」に基づく支援措置が挙げられます。これは、同法に定める様式で策定した「経営力向上計画」につき、国に対して申請し認定を受けることによって、税制面・金融面での様々な支援を受けられるというものです。
たとえば、認定された計画に基づき購入した資産について、法人税や不動産取得税などの軽減措置を受けることができます。あるいは、認定された計画の範囲内で、日本政策金融公庫から低金利での融資を受けることもできます。
こうした公的な支援も利用しながら、事業承継に向けて自社の事業をより魅力的なものにしていきましょう。
経営体制を強化する
事業承継は、企業風土を改善するための大きなチャンスでもあります。
というのも、会社運営の仕組みが合理的なものでなければ、事業承継は円滑に進みません。後継者がスムーズに事業を引き継ぐためには、後継者という「第三者」から見ても理解できるような、合理的なシステムで運営されている会社であることが必要だからです。
つまり、事業承継をうまく進めるには、会社運営の体制に不合理な点がないか広くチェックすることが不可欠です。その際に不合理な仕組みや体制が見つかった場合、企業風土を一気に改善するチャンスとなるのです。
たとえば、役員・従業員の職制や職務権限に不明確な点があれば、各種規定やマニュアルを整備する必要があります。内部統制の仕組みが整備されていないことが明らかになれば、改めて体制づくりを行う必要もあるでしょう。
こうして足元の経営体制を強化することで、後継者候補が安心して承継できる会社、あるいは後継者候補が見つかりやすい会社にしていきましょう。
業績が悪化した会社の場合
現時点で業績が悪化している会社は、事業承継に向けて財務状態の改善に取り組む必要があります。特に債務超過に陥っている会社の場合、早急に具体策を講じなければなりません。
たとえば、裁判所の関与のもとで事業再生に取り組む「民事再生手続き」を利用することが可能です。あるいは、裁判所が関与しないものとして、「中小企業再生支援協議会」の支援を得ながら金融機関から融資を受ける手続きも用意されています。
いずれにしても、まずは弁護士等の専門家に相談をして、自社にとって最適な再建策を選択しましょう。事業承継は、会社再建のためのチャンスでもあるのです。
事業承継の実行プロセス①親族内承継・従業員承継の場合
事業承継に向けて準備を進める過程で、親族または役員・従業員の中から、後継者候補が見つかったとしましょう。この場合には、親族内承継または従業員承継のプロセスへと移ることになります。
ここからは、親族内承継・従業員承継を実行するためのプロセスについて説明していきます。
事業承継計画の作成
親族内承継・従業員承継を行う方針が固まった場合には、まず「事業承継計画」の作成に取り掛かります。
事業承継計画の作り方
事業承継計画とは、「会社の資産や経営権をどのようにして後継者へ承継するか」を中心に、会社の10年後まで見通して詳細に決めておくための計画です。
最初に、あらかじめ行っておいた「経営状況の分析」をもとにして、会社の事業全体の中長期目標を設定します。そのうえで、中長期目標を達成するための事業の方向性を具体化し、そこへ事業承継の時期や方法についても盛り込んでいきます。
このように、「事業承継計画」とは会社の将来に関する全体的な計画であり、単に事業承継のことだけを決めるものではありません。会社の10年後を見通すことによって、後継者も安心して会社を引き継ぐことができるのです。
特例承継計画とは
なお、事業承継計画の中には、「特例承継計画」と呼ばれるものがあります。これは「事業承継税制」による優遇を受けたい場合に作成するものであり、その様式は「経営承継円滑化法」によって定められています。
作成した特例承継計画について都道府県知事の認定を得ると、事業承継税制の適用を受けることができます。具体的には、後継者が会社の資産や株式を承継する際に課税される相続税や贈与税について、税率の軽減や納税の猶予・免除をしてもらえるのです。また、事業承継に必要な資金を、一般よりも有利な条件で融資してもらうことも可能になります。
手続きの詳細については、地域の商工会議所などで教えてもらうことができます。適用期間が限定されている特例措置なので、自社にとって利用可能な手続きなのかも含めて、ぜひ一度相談をしてみてください。
関係者との調整
事業承継計画の内容が固まったら、できるだけ早い段階で、親族・従業員・取引先・金融機関といった関係者に対して周知することが必要です。
親族
親族に対して事業承継計画を知らせることは、何よりも「家族の問題」として重要です。特に会社財産や株式の相続に関しては、事業承継計画の内容を踏まえてきっちり説明をしておきましょう。事業承継を円滑に進めるためには、親族の協力を得ることが不可欠です。
従業員
従業員に対して事業承継計画の内容を知らせるのは、会社の将来への不安を払しょくするためです。また、早いうちから後継者候補を将来の経営者として見てもらうことで、事業承継後の信頼関係の構築もスムーズに進みます。
取引先・金融機関
取引先や金融機関に対しては、取引関係を維持する目的で事業承継計画の内容を知らせます。
現在の経営者が引退した後、会社の事業がどのような形で展開されるのか不明瞭だと、取引関係の継続をリスクととられかねません。現在の取引関係を事業承継後も維持するために、事業の方向性を取引先や金融機関に対して明示するのです。
承継の実行
関係者との調整を十分に行い、事業承継計画に定めた承継の時期が来たら、いよいよ事業承継を実行に移します。
代表取締役の交代
まずは、会社の経営権を後継者に対して引き継ぎます。具体的には、現経営者が代表取締役の地位を辞任し、新たに後継者が代表取締役の地位に就くための手続きを行います。
そのために必要な手続きは、会社の形態ごとに会社法で定められています。たとえば、取締役会設置会社なら、取締役会決議が必要です。取締役会のない会社であれば、定款に定めた手続きを踏むことになります。
株式の移転
さらに、株主総会での議決権についても、後継者へ引き継ぎます。具体的には、現経営者が所有している会社の株式を、贈与・相続あるいは有償譲渡によって、後継者に移転します。親族内承継の場合は贈与・相続が、従業員承継の場合は有償譲渡が、それぞれ用いられます。
贈与・相続によって株式を移転する親族内承継の場合は、贈与税・相続税に関する税務上の手続きが必要です。また、親族内承継・従業員承継のいずれの場合においても、株主名簿の書換えという会社法上の手続きが必要になります。
事業承継の実行プロセス②会社売却(事業承継M&A)の場合
以上は、親族や役員・従業員の中から後継者候補を見つけることができた場合の話です。
これに対して、結局のところ後継者候補が見つからなかった場合は、どうなるのでしょうか。この場合は、会社を売却するためのプロセスを進めることとなります。
事業承継M&A仲介機関の選定
会社を売却するには、買い手となる会社を見つける必要があります。そのための手段として現在一般的になっているのが、会社の売り手と買い手のマッチングを行う仲介機関の利用です。
たとえば、経済産業省が運営する「事業引継ぎ支援センター」に仲介してもらうことが可能です。あるいは、民間の仲介専門業者も数多く営業しているので、その利用を検討することもできます。
仲介機関を選定する際には、複数の業者を十分に比較検討するようにしましょう。各種セミナーや勉強会、さらには日ごろの付き合いを通じて、仲介機関に関する評判を耳に入れておくことも、非常に有益な判断材料となります。
事業承継M&A売却条件を具体的に提示する
利用する仲介機関が決まったら、いよいよ買い手候補探しが始まります。
望ましい買い手候補を見つけるためには、仲介機関の担当者に対して、具体的な売却条件を伝える必要があります。そのためには「自分が理想とする事業承継のあり方」について、あらかじめ明確にしておかなければなりません。
「会社名は残したいのか」「従業員や取引先との関係は現状維持したいのか」「事業の運営形態は変えてもよいのか」など、明確にしておくべき事項はたくさんあります。こうした条件を具体的に提示できるように、自社の経営状況や事業の方向性について、あらかじめ詳細に分析・検討しておくことが必要なのです。
なお、どのような事業承継を望むかによって、会社売却の手法は異なってきます。そこで、主な売却手法についても簡単に触れておきましょう。
株式譲渡
売り手側の経営者が所有する株式を、買い手に対して売却する手法です。株式を売却するだけで手続きが完結するので、他の手法よりも簡単に進めることができます。
会社の名前や組織をそのまま残したい場合は、株式譲渡が適しています。株主と経営者が変わるだけで、会社の事業自体は従前と変わらず存続するからです。会社の許認可や債権・債務も、そのままの状態で存続します。
売り手からすると、簡単な手続きで売却益を手にすることができるメリットがあります。一方で買い手側からすると、思わぬ債務まで承継してしまうリスクが存在します。
事業譲渡
会社の事業自体を、ひとつの財産として譲渡する手法です。
ここで売却されるのは、あくまでも事業に限られます。会社全体が引き継がれるわけではありません。そのため、事業の運営形態や従業員・取引先との関係について、買い手企業の裁量に任される部分が大きくなります。また、買い手が思わぬ債務を承継する心配もありません。
さらに、事業の一部だけを譲渡することも可能です。たとえば、事業を縮小して会社の存続を図るというような、柔軟な選択をすることができるのです。
自社の事業内容を評価してもらう
仲介機関に対して売却条件を伝えると同時に、自社の事業内容を客観的に評価してもらう必要もあります。これは買い手候補となる企業に対して、自社の情報を提供するための作業です。
この段階で、どれだけ自社を魅力的に見せることができるかは、それまでに行ってきた準備の内容にかかっています。買い手候補に対して自社の魅力をアピールできるように、「自社の強み」の磨き上げや経営体制の強化を十分に行っておく必要があるのです。
なお、買い手候補に対する自社情報の提供は、「ノンネーム情報」という会社名が特定されない形式で行われるのが一般的です。会社の重要機密を扱うM&Aにおいては、秘密保持には十分な配慮がなされているのです。
自社の事業を評価してもらう際には、何よりも「事実をありのまま伝える」ということが重要です。赤字や係争案件の存在といったネガティブな情報こそ、率直かつ正確に伝えることを心がけましょう。仮に情報開示が不十分なまま事業承継の話が進んでしまうと、最悪の場合、相手方から損害賠償を請求される恐れがあります。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
交渉~基本合意書の作成
仲介機関によって売り手・買い手のマッチングが済んだら、次は当事者同士の交渉に移ります。
仲介機関を通してやり取りされた情報に加え、トップ会談でさらに細かい条件を詰めながら、事業承継の契約内容を確定していきます。具体的には、譲渡価格・経営方針・今後の事業の方向性・従業員の待遇など、様々な項目について交渉を行います。
売り手・買い手の間で事業承継の合意に至ることができれば、基本合意書を取り交わします。これは、最終契約の前段階において、事業承継のアウトラインを明確にしておくためのものです。
デューデリジェンス(事業調査)
次は、基本合意書の内容を踏まえて、デューデリジェンス(事業調査)が実施されます。買い手側の会社が税理士・公認会計士・弁護士といった専門家に依頼して、売り手側の事業内容や財務状況について詳しく調査するのです。
最終契約の締結
デューデリジェンスを経て、基本合意書の内容に誤りのないことが明らかになれば、いよいよ最終契約の締結に入ります。契約書が取り交わされることで、合意の内容に法的拘束力が生じます。
なお、株式譲渡や事業譲渡といった手法ごとに、契約書に記載すべき事項は異なってきます。想定外のトラブルを防止するためにも、契約書の作成には弁護士等の専門家の協力を仰ぐようにしましょう。