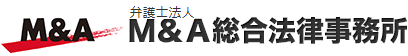事業承継における遺留分の特例の使用方法!

事業承継と遺留分の特例
事業承継において、経営者が後継者に譲渡する保有株式が巨額になっているため、保有株式が相続財産の多くの部分を占め、その結果、どうしても後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが明らかな場合があります。遺留分を侵害してしまうのであれば相続争いが生ずることは必至です。そこで、新設された制度が遺留分の特例です。ここでは遺留分の特例の制度の内容、適用要件、使用方法について、解説してゆきたいと思います。事業承継を検討されている経営者にとっては必見です。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
中小企業における事業承継
企業で行っている事業を後継者へと引き継ぐことを事業承継といいます。事業承継を行う際は、承継相手の選び方が大きな問題となります。とりわけ中小企業では経営者の手腕が企業全体の存続に関わるため、適切な事業承継を行うことが必須です。しかし、考えなければならない問題は承継相手のことだけではありません。承継相手はスムーズに決まったとしても、トラブルが発生するケースは多いのです。たとえば、相続によって事業を引き継ぐことになる際に、後継者とならない相続人が、本来なら得られるはずの遺留分を得ようとして請求を行うことがあります。
自社株式の集中
中小企業の経営者が事業承継を行う際は、後継者に自社株を集中させたいと考えるのが普通です。自社株が分散している状況では、事業を進めていくのが困難になってしまいます。しかし自社株は相続財産に該当するため、このような形での事業承継に対しては後継者とならない相続人が強く反発します。民法1042条によって相続人に保障されている遺留分が侵害されるからです。
遺留分侵害額請求(自社株式の集中により遺留分を侵害)
遺留分は、民法で保障されている特別な権利です。被相続人が遺言などで相続財産の分け方を指定することも多いですが、遺留分を侵害することは原則としてできません。遺留分が侵害された相続人が民法1046条に基づく遺留分侵害額請求を行うと、後継者に自社株を集中させる遺言があったとしても、遺留分に相当する部分を相続人に渡すことになるのが原則です。これでは自社株を集中させられず、円滑な事業承継も困難になってしまうため、中小企業経営承継円滑法という法律で、民法の遺留分に関する特例が認められています。
中小企業経営承継円滑化法(事業承継円滑化法)
高齢の中小企業経営者が増えているにもかかわらず、経営者の半数近くは事業承継について十分な準備ができていません。事業承継は短期間で容易に済ませられるものではないため、長い年月をかけて準備を進めることが不可欠です。誰がどのように自社株を相続するのかが決まらないまま経営者が亡くなってしまうと、遺留分侵害額請求などが起こりやすくなり、円滑な事業承継を行うのは困難です。事業承継に失敗して廃業する中小企業が増えると、日本経済全体にも影響を及ぼすことになります。そのため中小企業庁が主体となって、事業承継に関する支援を行う仕組みが作られているのです。
⇒会社相続・株式相続にお困りの場合はこちら!
民法の遺留分に関する特例の適用(自社株式の集中が遺留分を侵害しないようにする)
事業承継が妨げられる最大の要因は遺留分の問題です。遺留分侵害額請求によって自社株が分散しないようにするため、民法の遺留分に関する特例が設けられています。もちろん遺留分は相続人に保障されている重要な権利なので、むやみに侵害することはできません。円滑法においても、一定の要件を満たしている場合に限って特例が認められることになっています。特例の内容には、主なものとして除外合意と固定合意の2種類に加え、これらと併せて行うことができる不随合意があります。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
除外合意(円滑法4条1項1号)
概要
事業承継によって取得した自社株を、遺留分の対象から除外するための合意です。推定相続人全員の合意が必要とされますが、株式の全部ではなく一部について合意することも認められます。除外合意を行うと、自社株の部分について他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がなくなり、円滑な事業承継を行うことが可能になるのです。もちろん遺留分の対象外とされるのは自社株の部分に限られるので、その他の財産について不当な相続が行われるような場合には、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
要件
どのような企業でも自由に除外合意をすることができるわけではなく、いくつかの要件を満たしていることが求められます。まず、事業を3年以上継続している必要があるため、たとえば設立から間もない企業の場合は認められません。また、円滑法2条で定められた中小企業者に該当する企業であること、非上場企業であること、後継者が当該企業の旧代表者から自社株を取得することも要件となっています。
手続き
除外合意が成立したとしても、直ちにその効力が発生するわけではありません。経済産業大臣の確認を受ける必要があるため、合意から1ヶ月以内に後継者が申請を行います。この申請に関しては、後継者が単独で行うことが可能です。申請を行う際には、申請書・合意に関する書面・印鑑証明書などを提出します。経済産業大臣の確認を経た後、家庭裁判所に対して申し立てを行い、許可が得られた段階で除外合意の効力が発生します。
固定合意(円滑法4条1項2号)
概要
除外合意とは異なり、自社株を遺留分の対象に含めるのが特徴です。ただし、その価額は推定相続人全員が合意した時点の評価額で固定します。したがって、旧代表者の相続が開始されるまでに自社株の価値が大きく上昇してしまったような場合でも、後継者とならない相続人の遺留分の額は変動しません。遺留分侵害額請求を受ける可能性は残りますが、金額の変動を考慮する必要がないため、後継者は経営に専念しやすくなります。安心して企業価値の向上を図ることができるわけです。
要件
除外合意の場合は推定相続人全員の合意があればよいのですが、固定合意の場合はそれだけでは不十分です。推定相続人全員の合意に加え、弁護士等の専門家による証明が必要になります。固定合意をする時点での価額が不適切なものになってしまうのを防ぐため、相当な価額であることを証明しなければならないのです。また、推定相続人が自由な方法で評価してよいわけでもありません。中小企業庁が公表しているガイドラインに基づいて評価を行います。
手続き
固定合意についても、基本的に除外合意の場合と同様の手続きが必要になります。除外合意と異なっているのは、固定合意で定めた価額が相当なものであることに関する弁護士等の証明書を提出する点です。証明として認められるのは、弁護士・弁護士法人・税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人による証明です。
附随合意
概要
基本的な合意は除外合意・固定合意の2つですが、併せて別の合意をすることも認められています。除外合意・固定合意は推定相続人全員が合意する必要があるわけですが、それだけでは後継者・非後継者のバランスが取れないことがあります。その調整のために認められているのが不随合意です。
具体的な内容
円滑法5条・6条に、具体的な内容が定められています。それは、土地・建物などの自社株以外の財産を遺留分の算定財産から除外すること(円滑法5条)、推定相続人に金銭等を支払う旨の合意をすること(円滑法6条1項)、非後継者である推定相続人が旧経営者から贈与された財産を遺留分の算定財産から除外すること(円滑法6条2項)です。円滑法6条の規定は、推定相続人の間で不公平が生じないようにするための措置だと考えられます。
要件
除外合意・固定合意については単独で行うことができますが、不随合意はこれらと併せて行う合意なので、不随合意を単独で行うことは認められません。
手続き
除外合意をする場合と同様の手続きです。経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可が必要とされます。
合意の選択と併用
除外合意・不随合意のうち、どちらかが絶対的に優れているというわけではありません。企業の状況によって適切な合意は異なります。したがって、さまざまな要因を考慮しながら慎重に決めることが大切です。特に重要なのは、自社株の評価額がどのくらいなのかを知ることです。いずれ事業承継を行うときに備え、定期的に自社株の評価を行うようにしておくと安心できます。
また、除外合意・固定合意を併用することも可能です。一部の株式については除外合意を採用し、それ以外については固定合意を採用するといった方法も認められるので、状況に合わせて臨機応変な対応をする必要があります。
非後継者への配慮(自社株式を集中により遺留分を取得できないようになる日後継者へ配慮する必要がある)
推定相続人全員の合意があり、合意書の作成が行われたとしても、合意が必ず守られる保証はありません。そのため万が一の事態に備え、非後継者がとりうる措置に関する定めをしておくことが不可欠です。特別な定めがないと、たとえば合意対象となっている自社株を後継者が処分してしまったような場合でも、非後継者は何もできなくなってしまいます。このような事態を防ぐ方法としては、違約金に関する定めを置くことなどが考えられます。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
まとめ
事業承継を円滑に行うことができるように、中小企業経営承継円滑法で民法の遺留分に関する特例が設けられています。とりわけ重要なのは、除外合意・固定合意という2種類の合意です。これらの合意を上手に活用し、遺留分侵害額請求によって円滑な事業承継が妨げられないようにすることが欠かせません。ただし、遺留分は相続人の重要な権利の1つなので、合意を行う際の要件をきちんと満たす必要があります。後継者と非後継者とのバランスを図ることも不可欠です。