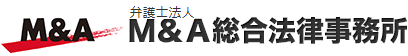贈与税の算出方法

この回では贈与税について取り上げ、算出方法を解説していきます。
相続税よりは難しくないものの、考え方に注意が必要な点もあります。
まずは基本的な留意事項から確認します。
⇒相続財産・遺産の使い込み・独り占め等でお困りの方はこちら!
贈与税計算の前段階における留意事項
贈与税は他人から財産をもらった側の人にかかる税金ですが、例えば親から子への贈与などの場合、それが民法上の扶養義務の範囲であれば贈与税の対象にそもそも入らないので、計算対象になりません。
扶養義務を超えた贈与が贈与税の対象になります。
課税対象から基礎控除110万円を控除する
贈与税の対象になる贈与を受けた場合でも、受贈者を単位として年間110万円までであれば、基礎控除の範囲内となるため贈与税の負担はありません。
またこの場合贈与税の申告手続き自体が不要です。
110万円をこえた受贈財産が課税対象になり、ここに税率をかけて贈与税額を算出することになりますが、誰から財産をもらったのか、贈与者によって税率が変わる点に留意します。
贈与税の税率は二種類ある
上の世代から下の世代への財産移転を活発にするため、直系尊属からその年の1月1日において20歳以上となる子や孫など、直系卑属への財産移転については「特例贈与」とし、この特例贈与財産については税率を優遇しています。
上記特例贈与にあたらない贈与が「一般贈与」となり一般贈与財産については特例贈与財産よりも税負担が若干上がる設定になっています。
二つの税率表は以下で確認できますが、一般贈与と特例贈与の別に、適用のある税率を間違わないようにしましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
例えば、一般贈与財産300万円の贈与を受けた場合、適用税率は15%、控除額は10万ですので、300万円×15%-10万円=35万円が贈与税率となります。
同じ年に一般贈与と特例贈与の両方の贈与を受けた場合
この場合は按分計算が必要になります。
例えば一般贈与財産として100万円、特例贈与財産として400万円の贈与を受けたとします。
この場合、まずは両者を足した500万円から基礎控除110万円を控除して、390万円を導きます。
次に、390万円を一般贈与財産として扱ったと仮定して計算します。
| 390万円×20%-25万円=53万円 |
これを全贈与財産に占める一般贈与財産分として按分計算します。
| 53万円×=10万6千円・・① |
今度は、おなじように390万円を特例贈与財産として扱い計算します。
こちらの対応税率を適用すると、
| 390万円×15%-10万円=48万5千円 |
これをまた、贈与財産に占める特例贈与財産分として按分計算します。
| 48万5千円×=38万8千円・・② |
上記の①と②を足すと、10万6千円+38万8千円=49万4千円となり、これが最終的な贈与税額となります。
相続時精算課税制度について
上記で見てきたのは、贈与税の基本制度である暦年課税制度によるものです。
こちらが原則になるのですが、もう一つ「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。
生前に行われた財産移転について、贈与者の死亡時、つまり相続時に精算するのが相続時精算課税制度です。
生前贈与について2500万円まで贈与税がかからないものとし、相続時には相続税と一体化して精算します。
相続税の基礎控除などの仕組みを利用できることから実施的に無税となったり負担を減らす効果も期待できますが、ケースによっては逆に負担が増えることもあるので、検討する場合は専門家の指導の下に考える必要があります。
また一度相続時精算課税制度を利用した場合、二度と暦年課税制度に戻ることはできません。
年間110万円までの基礎控除を使った相続税対策もできなくなるので、相続時精算課税制度を検討する場合はこの点を十分に考慮する必要があります。
まとめ
本章では贈与税の算出方法について見てきました。
相続税ほど難しくはありませんが、税率の種類が二種類あることに留意しておきましょう。
また暦年課税制度と相続時精算課税制度という二つの制度があり、併用できないことも知っておく必要があります。
相続対策のために相続時精算課税制度を検討する場合には、必ず専門家の指導を仰ぐようにしてください。