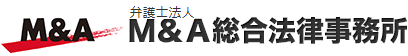他の相続人に全財産を相続させる遺言書が発見された!

長男やひいきにしていた子、あるいは養子などに全財産を相続させる遺言書が見つかっても、泣き寝入りする必要はありません。亡くなった人と一定の関係にある相続人には、生前の意思より優先される「遺留分」の請求権が認められるからです。
それでは、遺留分とはどう解釈し、どう主張すれば遺産分割での不公平の解消に繋がるのでしょうか。以降で詳しく解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の範囲にいる法定相続人につき、それぞれに保障される「最低限の取得分」を指します。ここで「最低限」と表現したように、亡くなった人の意志や遺産分割に関する合意事項に関わらず、必ず取得できる点に特徴があります。
想定されているのは、自己の権利を超えて遺産を取得した人物がいるケースです。そのような事態は、単に不公平であるばかりか、亡くなった人に生計を維持してもらっていた親族の経済的基盤すら脅かしかねません。遺留分制度は、この点を踏まえて設けられているものです。
「特定の相続人に全財産を相続させる遺言」の対処法
遺留分の権利が対処に繋がるのは、相続開始後になって「特定の親族に全財産を残す」という内容の遺言書が見つかるトラブルです。
最も多いのは、長男や長女が「家督を継ぐ」との考え方から遺産の承継先に指定されるケースです。なかには、生前ひいきにされていた子や、晩年になって同居するようになった内縁の妻(夫)が遺言で相続するケースもあります。
まず理解したいのは、法律で定められる相続権の割合(=法定相続分)に内容が反しているとしても、遺言の効力がなくなるわけではない点です。まず、遺言を含む法律行為や私有財産の処分は、「所有権絶対の原則」や「私的自治の原則」による自由が保障されています。その上で、相続法においても、亡くなった人はその遺言で共同相続人の相続分を定められると規定されているのです(第902条1項)。
一方で、遺産分割での不公平に納得できない親族にも、相続法に基づく保護があります。すなわち、全財産を相続した人に対して「遺留分侵害額請求権」を主張すれば、最低限に過ぎないもののある程度の額は取り戻せるのです。
生前贈与も遺留分請求の対象になる
特定の親族が遺産を独り占めするケースの中には、遺言ではなく、生前贈与ですでに名義変更を済ませてしまっている場合があります。この場合も「遺留分を侵害した」として取り戻せます。
問題となるのは、贈与の時期です。この後解説するように、贈与の相手方が相続人であれば10年・相続人ではない人なら1年とのように、取り戻せる範囲が決まっているからです。そこで、預貯金なら銀行の取引明細を取り寄せる……とのように、立証手段の確保を兼ねて「いつ贈与されたのか」はっきりとさせなければなりません。
遺言の効力自体が疑わしい場合は?
一般的に、遺言書は年齢を重ねてから作成されるものです。なかには、認知症その他の精神上の障害と診断されてから書かれたものや、後から他人の手が加わっているものがあることが否めません。そうした被相続人本人の健常な判断が反映されていない遺言は、当然無効になります。
もしも遺言の有効性に疑義があるのなら、法定相続人等の利害関係者による「遺言無効確認訴訟」の申立てでジャッジしてもらえます。遺言が無効との判決が下された場合、続く遺産分割調停で各法定相続人の取得分を決定できるため、遺留分を請求するまでもありません。
【遺言が無効になる可能性があるケース】
- 公正証書遺言※ではなく、作成の経緯に不審な点がある
- 自筆証書遺言の形式(民法第968各項)が守られていない
- 遺言書の封印に破られた形跡がある
【※参考】公正証書遺言(民法第969条各号)とは
本人確認書類等の持ち物と証人を揃え、各地にある「公証役場」で作成された形式の遺言です。不備の生じる可能性が限りなく低く、原本は公文書として保管される等、内容の真正さ・効力・改ざん対策の各面において信頼性の高い形式です。
なお、遺言無効確認訴訟の提起の際には、主張の裏付けとなる資料を用意する必要があります。具体例として、遺言された日付の当時に認知症だった、つまり法律行為や私有財産の処分ができない状態であったことを示す医療記録等が挙げられます。
相手が相続欠格or相続廃除されていた場合は?
民法では、相続権を強制的に剥奪する規定として「相続欠格」と「相続廃除」が設けられています。
では、遺言で全財産をもらい受けることになった相手が欠格・廃除となった場合、それを理由に遺産の独り占めを阻止することは出来るのでしょうか。結論としては、遺言書の文言により解釈が分かれると言わざるを得ません。
| 相続権を剥奪する制度 | 概要 | 遺産の取得可否 |
| 相続欠格(民法第891条各号) | 該当する場合、自動的に相続権が失われる※取消しは不可 | 「相続させる」→×「遺贈する」→× |
| 相続廃除(民法第892条・第893条) | 生前の請求もしくは遺言により、相続権が失われる※生前の間なら取消し可 | 「相続させる」→×「遺贈する」→〇 |
考えられる中で最も悪質なのは、遺言書を精査した結果、高齢の親に無理やり書かせたと判明するパターンです。この場合、まず遺言が無効になり、遺産分割協議が必要になります。残る問題は全財産を相続させる旨の遺言をさせた人物の扱いですが、「相続人の欠格事由」により、協議への参加は認められません。
一方で「相続廃除」の場合は、被相続人による必要な手続きがなされているかが問題です。また、遺贈の効果は失われません。
いずれにしても、遺産を独り占めすることになった相手が欠格・廃除になるかを含め、弁護士に状況を診断してもらう必要があります。
「家督相続」は廃止されている
遺留分侵害額請求を始めると、相手方が「家督相続」の考え方を持ち出すことがあります。結論として、上記のような主張に法的根拠はありません。
確かに、家名とともに戸主が全財産を相続する仕組みが法制化されていた時期はありました。しかし、それは明治時代のことであり、戦後の昭和22年の民法大改正で廃止されています。
現在の相続法では、一定の身分関係であれば遺産分割を請求する権利があります。また、きょうだいや両親等といった同一の関係にある相続人の間では、性別・年齢・生まれた順番・家業への従事状況・被相続人との仲等による差別は一切ありません。
遺留分請求にかかる交渉では、上記の制度を説明しつつ、法律の理解と支払いの履行を求める必要があります。
遺留分を請求できる条件
以降では、遺留分を請求する際のルールを整理します。
まず確認しておきたいのは、請求するにあたって必ず満たすべき3つの条件です。
相続法で定められた請求権者であること
第1に、遺留分は「兄弟姉妹以外の法定相続人」に限って認められます。
必ず遺留分権利者になれるのは、配偶者と子です。相続開始時点で子(=相続順位1位)がいなければ、代わりに父母・祖父母等の直系尊属のうち最も血縁の近い人(=相続順位2位)に遺留分が認められます。配偶者・子・直系尊属がまったくいない場合には、兄弟姉妹(=相続順位3位)が法定相続人になるものの、遺言で財産を取得する人に対して遺留分を求めることは出来ません。
遺留分の侵害を知ってから1年以内であること
第2に、遺留分侵害額請求を実際に開始できるのは、「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」から1年間と定められています(民法第1048条)。
ただし、いつでも事実を知れば1年以内に対処できる、という訳ではありません。遺留分請求の最終期限は相続開始から10年で到来し、その後はいかなる理由があっても請求できないとも定められているのです(=除斥期間)。
相続欠格or相続廃除がないこと
第3に、遺留分が認められるのは法定相続人である間に限られます。先で紹介した「相続欠格」あるいは「相続廃除」となった場合、遺留分を請求する権利もなくなります。
ほとんどの場合は心配無用ですが、相手方から欠格に関する主張が行われる可能性も踏まえて、弁護士に確認をとると良いでしょう。
遺留分の計算方法
遺産分割の不公平に苦しむ親族としては、「遺留分として請求できる金額」が一体いくらになるのか気になるのではないでしょうか。金額を算定する時は、大まかに以下4ステップを踏みます。
【遺留分計算の4ステップ】
- 「遺留分算定の基礎となる価額」を計算する
- 「遺留分の総体」を計算する
- 「個別の遺留分」を計算する
- 「遺留分侵害額」を計算する
「遺留分算定の基礎」の計算方法
まず見定める必要があるのは、遺留分算定の基礎となる価額、つまり請求対象となる財産の総体です(民法第1043条1項)。これに関しては、以下の式から割り出せます
遺留分算定の基礎となる額=
①相続開始時点で遺されていた財産の価額+②遺贈&特別受益としての生前贈与の価額※-③相続財産に含まれる債務額
【※参考】特別受益とは
特別受益(民法第903条)とは、遺贈や特定の生前贈与を「すでに受け取っている相続財産」とみなし、これを遺産に持ち戻そうとする時の呼称です。生前贈与については、具体的に以下のようなものが挙げられます。
なお、遺留分算定の基礎となる価額を計算する際は、持ち戻せる特別受益には範囲の制限があります(詳しくは法改正による変更点で解説します)。
- 教育資金の贈与
- 結婚資金の贈与
- 養子縁組のための資金の贈与
- 被相続人名義の土地建物の無償使用
- その他、生計の資本としての贈与(不動産や事業資金など)
総体的遺留分の計算方法
次に判定する必要があるのは、総体的遺留分、つまり「各相続人に認められる遺留分の合計額」です。民法では、遺留分算定の基礎となる価額に対し、法定相続人の状況に応じて下記割合で総体的遺留分が認められるとしています(第1042条1項各号)。
- 直系尊属以外の相続人がいない場合:3分の1
- 上記以外:2分の1
個別的遺留分の計算方法
個別的遺留分、つまり「1人ひとりの請求権者に認められた遺留分」は、総体的遺留分のうち法定相続の割合に相当する額です(民法第1042条2項)。判定に必要な割合については、表のように法定相続人の組み合わせにより変化します。
| 法定相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
| 配偶者のみ | 1分の1(2分の1) | ― | ― | ― |
| 配偶者+子 | 2分の1(4分の1) | 2分の1(4分の1) | ― | ― |
| 配偶者+直系尊属 | 3分の2(6分の2) | ― | 3分の1(6分の1) | ― |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3(2分の1) | ― | ― | 4分の1(遺留分はゼロ) |
| 子のみ | ― | 1分の1(2分の1) | ― | ― |
| 直系尊属のみ | ― | ― | 1分の1(3分の1) | ― |
| 兄弟姉妹のみ | ― | ― | ― | 1分の1(遺留分はゼロ) |
※カッコ外は「法定相続の割合」、カッコ内は「遺留分算定の基礎となる価額に占める権利割合」を示しています。
遺留分侵害額の計算方法
以上の計算で求められた個別的遺留分は、その全額を請求分として提示できるわけではありません。公平を期すため、遺贈や特別受益にあたる生前贈与の他、わずかでも相続で得た財産があれば、請求額から控除されます(民法第1046条2項各号)。
まとめると、遺留分侵害額として実際に請求できるのは、以下の計算式によって算出された金額です。
遺留分侵害額=
個別的遺留分-{(遺留分権利者が相続で得た財産額-相続財産に含まれる債務額×法定相続の割合)+遺贈の価額+特別受益としての生前贈与の価額}
平成30年の相続法改正による変更点
ところで、本記事で紹介する遺留分侵害額請求権は、平成30年の相続法改正まで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました。現行法での遺留分の考え方は、令和元年7月1日以降に発生した相続について適用されるものです。
新法・旧法ともに趣旨自体は共通していますが、以下の点で決定的に異なります。
【変更点①】遺留分請求の対象
令和元年6月以前の「遺留分減殺請求権」は、亡くなった人から受け継がれた財産そのものが対象でした。対する同年7月以降の「遺留分侵害額請求権」は、財産をそのまま取り戻す権利ではなく、あくまでも遺留分相当の金銭の支払いを求める権利だとされています。
【変更点②】持ち戻せる特別受益(贈与財産)の範囲
遺留分算定の基礎に含められる特別受益には、一定の範囲に限定されています。
かつての遺留分減殺請求権は、その範囲を「相続開始前の1年間における贈与分」に統一していました。一方、遺留分侵害額請求権においては、贈与された人(=受贈者・受遺者)が相続人である場合のみ特に区別して、遺留分算定の基礎に含めてよい範囲を「相続開始前の10年間」と拡大しています。
ただし、遺留分を侵害すると知ってされた贈与につき「定められた範囲より以前の遺留分算定の基礎に含められる」とする点は、旧法から特に変更されていません。
遺留分請求の流れ
遺留分侵害額請求の実務では、家族だからこそ先手を打たれる可能性を考えて、慎重に進めなくてはなりません。ここでは、遺留分を取り戻すにあたって障害になるポイントを押さえつつ、各ステップについて解説します。
相続財産の調査
遺留分の計算に欠かせない相続財産の状況を知りたいと考えても、ほとんどの場合、遺言で財産を取得することになった相手方が資料を握っている状態です。そこで、遺留分権利者として独自に調査しなくてはなりません。
調査にあたっては、資産別に関係各所に問い合わせる必要があります(下記参考)。
- 預貯金・株式
…金融機関から残高証明書を取得し、資産状況を確認。
- 不動産
…法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)、市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得。その他、地積測量図、建物図面、売買仲介業者の査定書等を取り寄せる。
- 生前贈与
…取引明細書や登記情報から、資産の移転状況を調べる。
請求開始の意思表示
遺留分侵害額請求について相手方に知らせる時は、差出人情報や内容等が記録される「内容証明郵便」を使います。何らかの記録が残る形でないと、後々の交渉において、遺留分請求の手続きが「民法で定められる期間(1年以内)に行われているかどうか」でもめる恐れがあるからです。
また、内容証明郵便の送付は基本的に予告なしで行うもので、メールや電話による連絡は差し控えます。請求を開始するまでに第三者に財産を売却され、その代金も使い込まれてしまったとあっては、支払いが実現しない点で元も子もないからです。この点に関しては、平行して「民事保全手続」を行い、財産の処分を制限する手法が考えられます。
交渉後の「合意書」の作成
遺留分権利者と相手方と話し合いが始まり、その決着を見た時は、「合意書」に内容をまとめます。この時、双方認識している相続にかかる内容、支払の時期や手段等、後だしで主張されないよう細かく合意事項を洗い出す必要があります。
問題は、そもそも交渉できるかどうかです。実際、相手方が交渉に応じなかったり、遺留分請求に関する主張が真っ向から対立したりする可能性は、事の性質上どうしても捨てきれません。もしそのようなことがあれば、法的手続きに移行することになります。
裁判手続(調停・訴訟)
解決のための最終手段は、もちろん裁判手続の活用です。遺留分侵害額請求にかかる争い事について言えば、訴訟を起こさず、まずは家庭裁判所に仲裁してもらいながら話し合う「調停」で解決を試みます。
と言っても、上記の「調停前置主義」は、係争事の性質を考慮してそれほど厳格に運用されません。訴訟で迅速に決着できる(調停をやっても成立しない可能性が高い)と見込まれる状況なら、はじめから訴訟を起こしても構わないのです。この点、ケース別にどんなやり方をとるべきか判断する必要があり、経験・知識共に豊富な弁護士による診断が欠かせません。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求にあたっては、いくつか気を付けたいポイントがあります。以下では、不明点として挙げられる場合が特に多い事項を2つに絞って紹介します。
金銭支払いの原則がある
先でも触れたように、令和元年7月以降に発生した相続では、それより前と違って「金銭による支払い」が原則です。
確かに、現金不足のためやむを得ず不動産等の資産移転させる事例はない、とは言えません。そうは言っても、遺留分を取り戻そうとする時点においては、法改正以前には出来た「現金でない資産そのものの請求」は出来ないのです。
補足すると、現金以外の資産で遺留分を受け取った場合、通常ない譲渡所得税の賦課があります(所得税基本通達/法第33条関連)。
遺留分権利者にとってかえって不利になる点や、自社株など相手方にとって手放すわけにはいかない資産が遺留分侵害の原因になる可能性を考えれば、金銭での支払いはむしろ望ましいと言えます。
死亡保険金は遺留分算定の基礎に含まれない
トラブルのパターンとして、共同相続人の一部が死亡保険金を受け取り、その結果として遺産分割で不公平が生じるケースが考えられます。
結論として、死亡保険金に対する遺留分侵害額請求は原則できません。受取人固有の権利である以上は相続財産にはあたらないとの解釈に基づき(最高裁昭和40年2月2日判決)、遺留分算定の基礎にも当然含められないと考えられるのです。
一方で、例外がないとも言えません。
最高裁平成16年10月29日判決では、受取人である相続人とその他の共同相続人との間に「到底是認することが出来ないほど」著しい不公平が生じれば、その死亡保険金は相続財産に持ち戻すべきだと判断されています。
分かりやすく表現するなら、保険金が通常考えられないほど高額化している場合、公平を期すため遺産として扱えます。そうであるなら、遺留分侵害額請求ももちろん出来るようになると考えられるのです。
まとめ
長男など特定の親族に全財産を取得させる遺言があっても、簡単に諦めるべきではありません。権利を確認した上で毅然と主張すれば、少なくとも法律上保障される最低限の取得分は取り戻せます。
難しいのは、事前の財産調査が必要になる他、相手の出方を観察しながら対応方針を柔軟に決める必要がある点です。もちろん、請求できる遺留分の価額についても、個別の資産状況に応じて正確に計算しなくてはなりません。
弁護士に依頼した場合、トラブル解決に必要な上記の手配は、全て迅速かつ確実に行われます。心理面でも、代理人の存在によって家族と争う気まずさから解放され、自身の権利を主張するゆとりが生まれます。
理解できない、到底受け入れられないような遺言書が見つかった時は、まず弁護士に相談してみましょう。