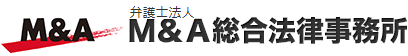遺言無効確認訴訟で相続財産を取り戻す方法とは?

遺言がおかしいと感じたら、「遺言無効確認訴訟」で遺産を取り戻せる可能性があります。提訴する時は、医師の診断書や介護記録が立証手段として役立ちます。事前調査の内容を元に「遺言能力がない」等の主張をしっかり整理して臨みましょう。
「遺言書の内容が生前言っていたことと違う」「自分で意思を書き残せたとは思えない」と感じた時は、躊躇せずすぐに調査してみましょう。その結果で確信が得られたなら、遺言無効確認訴訟で遺産を取り戻せる可能性があります。
本記事で主に紹介するのは、今後主張することになる遺言無効の原因です。全体に目を通せば、実務的な訴訟の流れや有力な証拠等、対応に必要な知識を一通り押さえられます。
⇒相続財産・遺産の使い込み・独り占め等の問題を解決する方法を見る!
遺言無効確認訴訟とは
遺言無効確認訴訟(遺言無効確認請求訴訟)とは、遺言執行により名義変更された遺産を取り戻すべく、「遺言に効力がない」と確定させるための手続きです。
言うまでもなく、財産処分に関する遺志を本人に尋ねることは不可能です。もしかすると、遺言書が書かれた時期には、すでに加齢によって正しい判断が出来ない状態に陥っていたのかもしれません。あるいは、介護者等が上手くそそのかし、自分に都合のいい遺言書を作らせたのかもしれません。
以上のように、遺言書について「故人の意思が反映されていない」との疑いが生じても、法的に確認されるまでは死亡時点から効力を生じます(民法第985条)。当然、何の根拠もなしに遺産の返還を求めても、相手は応じないでしょう。
そこで「遺言無効確認訴訟」を申立て、判決で事実を明らかにする必要が出てくるのです。
遺言無効確認訴訟を提起できる人
遺言無効確認訴訟を提起できるのは、法律上の利益を有する人です(最高裁判決昭和47年2月15日)。当てはまるのは、遺言の効力如何で利益を得ることになる「法定相続人」や「受遺者」です。
一方、訴えの相手方(=被告)となるのは、もちろん「遺言が有効ならば利益が得られる相続人や受遺者」となります。他には、遺言書で遺産の名義変更等の手続きを担うべきとされた「遺言執行者」を相手取って提訴することも認められています(最高裁判決昭和31年9月18日)。
遺言が無効になった場合はどうなる?
遺言無効確認訴訟で勝訴もしくは和解した場合は、遺言書がなかったものとして相続手続きします。つまり、法定相続人の全員参加のもと「遺産分割協議」を開き、その合意によって相続財産を取得するのです。
ただ、訴訟で対立した相手が相続権を有していると、上記協議も上手く進まないかもしれません。その場合は、遺産分割調停・訴訟といった裁判手続を再度行い、公平に取得分を決めることになります。
遺言無効確認訴訟から相続手続き完了までの期間
遺言の効力を巡るトラブルは、一般に時間がかかります。
まず訴訟提起前の準備に最短3か月程度、訴訟後スムーズに勝訴が確定したとしてもこの時点で2年余経過しているのが一般的です。その後の遺産分割協議でもトラブルが発生するとなると、さらに最短1年程度は相続手続き完了を待たなくてはなりません。
そこで重要なのが、判決で遺言無効を確認するメリットをしっかり見極めることです。もしメリットが不十分であるなら、和解等の負担の少ない解決策を模索しなければなりません。
遺言がおかしいと感じた時のチェックポイント
遺言の内容に違和感を覚えた時は、その様式をじっくりチェックしてみましょう。
書面に以下のような特徴があれば、効力に疑義が生じる可能性が高いと言えます。
- 筆跡や押印の跡が乱れている
- 遺言書の日付が新しすぎる
- 変更・削除・訂正・撤回の日付が新しすぎる
- 開封された状態で遺言書発見の報告を受けた
- 使用された印鑑が他の重要文書で使っているものと違う
遺言無効確認訴訟でよくある9つの主張
遺言の無効を訴訟手続で確認するには、効力発生の要件のうち何を満たしていないのか具体的に指摘する必要があります。訴訟でよくあるのは、以下のような主張です。
遺言能力がない
遺言ができるのは、15歳以上かつ意思能力が備わっている人のみです。(民法第961条・第963条)。ここで言う意思能力は「遺言能力」と呼ばれ、多くの場合、認知症やせん妄(※高齢者によく見られる注意力を中心とする障害)といった精神上の障害を患っていない状態と解釈します。
つまり、遺言をした日付において上記のような障害を患っていた場合、その遺言の効力は認められません。
【参考】成年後見人による遺言の方式
精神上の障害によって被後見人となっていても、一時回復した時は医師の立会いがあれば遺言できます。注意したいのは、一応は判断能力が戻ったとしても、1人で遺言書を作成してはならないとされている点です(詳細は「証人および立会人の不在」で解説します)。
遺言書の方式違背
遺言する時は、法律で定められる様式を守らなくてはなりません(民法第960条)。様式を逸脱する遺言書は、方式違背により無効とされます。
最も多いのは、公証役場を通さないで作成される「自筆証書遺言」(民法第968条各項)の方式違背です。
【一例】自筆証書遺言の方式違背
- ワープロソフトで作成されている
- 日付・氏名・押印のどれかが漏れている
- 加除その他変更の方法が守られていない
- 字が乱れており判読できない
検認前の開封
原本が公証役場で保管される「公正証書遺言」(民法第969条~第969条の2)でないものは、見つかった時ただちに家庭裁判所に提出して「検認」を経なくてはなりません。検認によってその時点での遺言の内容が証明され、以降の偽造・変造を防げるのです。
翻って、家裁提出前に開封されている遺言は、発見者により手が加えられている可能性が高いと言わざるを得ない場合がよくあります。
遺言書の代筆
遺言は代理に親しまない重要な行為です。「普通方式」と「特別方式」のどちらで作成されるにせよ、特別方式の一部を除いて遺言者本人の手で作成されなければなりません。
それにも関わらず成年後見人や同居家族に口授・代筆されていると、やはり無効と判断されます。
共同遺言
夫婦や親子での共同遺言は、法律で禁止されています(民法第975条)。遺言者の表示が2人以上あれば、それだけで遺言が無効になる原因となるのです。
遺言の内容は家族で話し合っても構いませんが、書面を作る時は夫・妻・子ども……とのように各々の名義で作成されなければなりません。
「遺言の撤回」の撤回
遺言は本人の意思によりいつでも撤回できます(民法第1022条)。
しかし、撤回を後から取り消すことはできません。撤回した第1の遺言を有効とする旨の第2の遺言、つまり「元の遺言を復活させる」内容の遺言は、法律上無効とされるのです(非復活主義/民法第1025条)。
問題は、相手方から「第2の遺言が詐欺または強迫で作成されたものだ」と主張される場合です。その主張が訴訟で認められると、例外的に元の遺言は復活します。
錯誤による無効
遺言するにあたり、資産状況や法的義務等の重要な事実を誤って認識していると分かる場合は、法律行為全般の一般則として無効になります(民法第95条)。
例として挙げられるのは、親族ではない受遺者(=遺贈を受けた人物)に「遺贈した財産で家族の面倒を見るように」と頼むケースです。一定の義務と引き換えに遺贈する「負担付遺贈」の様式で行われたならともかく、法的効力のない付言事項として依頼した場合には、遺言無効と判断される可能性が高いと言えます。状況から見て、扶養義務について誤解していたと考えられるためです。
証人および立会人の不在
遺言の方式の中には、証人および立会人を指定の数だけ要するものがあります。
立ち会った人の署名がない、あるいは立会いの実績が確認できないような遺言書には、効力がありません。
| 遺言書の種類 | 必要な証人および立会人 | 根拠条文 | |
| 普通方式 | 自筆証書遺言 | ― | ― |
| 秘密証書遺言 | 公証人1名および証人2名 | 民法第970条3項 | |
| 公正証書遺言 | 証人2名 | 民法第969条2項 | |
| 成年被後見人の遺言 | 医師2名 | 民法第973条1項 | |
| 特別方式 | 一般危急時遺言 | 証人3名 | 民法第976条1項 |
| 難船危急時遺言 | 証人2名 | 民法第979条1項 | |
| 伝染病隔離者の遺言 | 警察官1人および証人1人以上 | 民法第977条 | |
| 船舶乗船中の遺言 | 船長または事務員1人および証人2名以上 | 民法第978条 | |
証人および立会人の欠格事由
付け加えると、遺言書の作成時に証人および立会人となれるのは、民法第974条1号~3号の事由がない人のみです(下記参照)。これら欠格事由が証明できる場合には、遺言は無効とされます。
【証人および立会人の欠格事由】
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者
- 上記にあたる人の配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記および使用人
その他の重大な遺言無効確認の原因
遺言が無効になる原因は、ここまで挙げた単純なミスとも思われるものだけではありません。以下のように、第三者もしくは本人の悪意があるケースもあります。
偽造・改ざん・変造等
本人以外の者が手を加えた遺言は、当然効力を持ちません。
遺言書自体をまるごと第三者が作成する「偽造」にせよ、内容や枚数を勝手に変える「変造」や「改ざん」にせよ、証拠があれば遺言は無効です。
なお、こういった行為を行った人物には、相続法によりペナルティがあります(詳細は後述)。
詐欺や強迫による遺言
遺言能力がないとみなされるケースには、本人以外の人物による嘘や強要によって遺言書の作成・変更・撤回・取消等が行われる場合も含まれます。
遺言の方式等に一見して問題がない場合でも、生前の言動や家族関係とつじつまの合わない時は、それだけで効力に疑義が生じます。そして、詐欺・強迫について遺言無効確認訴訟で認められた場合には、やはりその行為をした人物にペナルティがあります(詳細は後述)。
公序良俗違反
社会のモラルに反する「公序良俗違反」にあたる遺言は、それだけで無効です。
具体的には、以下のような内容のものが挙げられます。
【一例】公序良俗違反で無効となる遺言書
- 不倫相手・愛人に遺産を譲る内容の遺言※
- 特定の人物との結婚を条件とする遺言
- 配偶者との離婚を条件とする遺言
- 法令違反を指示する内容の遺言
※「別居開始から一定期間経っている」等の婚姻関係の事実があった場合、公序良俗違反を主張できない可能性があります。
⇒相続財産・遺産の使い込み・独り占め等の問題を解決する方法を見る!
遺言無効確認訴訟の流れ
遺言無効確認訴訟にあたっては、事前準備や敗訴した時の対策が必要です。
ざっくりとした全体の流れを示すと、以下のようになります。
遺留分に関する予備的請求
実際の手続きでは、遺言無効確認訴訟の前に「遺留分侵害額請求権」を主張する旨を内容証明郵便で相手方に伝えるのが一般的です。訴訟で主張が退けられてしまったとしても、相続人に最低限保障される「遺留分」だけは確保できるようにするためです。
なお、内容証明郵便で遺留分の額を明らかにしておく必要はありません。ひとまず「遺留分を請求する意思がある」とだけ日本郵政が証明してくれる形で伝えておけば、上記請求権にかかる消滅時効の完成が妨げられ、後々改めて訴訟を提起して解決できます。
事前調査・証拠収集
遺言が無効であると主張するからには、効力発生を妨げる事実を原告側で立証しなければなりません。そのために欠かせないのが、診療記録等の証拠収集です。
一般に、「これさえあれば決定的な証拠になる」と言える資料はありません。担当医・入居先の老人ホーム・介護保険担当者・そして調査会社……とのように関係各所にあたって、なるべく多くの資料を集める必要があります。
家事調停の申立て
相続等の家庭に関するトラブルを法的手続で解決しようとする場合、まず家事調停から申立てなければならないとする決まりがあります(家事事件手続法第244条・第257条1項)。遺言無効確認訴訟もこれに従い、先だって調停を申立て、相手と裁判所で話し合う機会を設けなくてはなりません。
もっとも、訴訟から始めたからといって、必ずしも家事調停に回されるとは言えません。裁判所が「調停に付することが相当でない」と判断する場合には、そのまま審理を進めてもらえる場合があります。典型的なのは、意見対立が激しく話し合いが折り合わない場合です。
訴訟の申立て
条件が整えば、いよいよ遺言無効確認訴訟の申立てです。訴訟物・請求の趣旨・請求の原因等を明らかにした訴状を作成し、集めた証拠資料を添付して裁判所に提出します。
この時、勝訴に備えて既に名義変更された遺産をスピーディに取り戻すべく、「所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟」等を併合提起する場合があります。
【参考】共同相続人の協力が必要になる場合あり
遺言無効確認訴訟の申立ては、共同でなくても構いません。原則上、相続人のうちの誰かが原告になれば問題ないのです。しかし、遺言無効を確認すれば他の相続人にも訴えの利益があるとなると、協力関係が必須になります。ここで「協力しようにも連絡が取れない人がいる」「認知症を患って訴訟に参加できない人がいる」等といった状況が障壁になる可能性が考えられます。
審理・判決
裁判所による訴状審査が終わると、第1回口頭弁論期日が指定されます。以降は約1か月ごとに期日が指定され、原告・被告双方の主張のやりとりを進めます。
以上のプロセスで争点整理され、当事者の希望があれば本人や証人の尋問が行われつつ、最後に判決言渡期日が指定されます。なお、この間に裁判所から和解を勧められることもあります。
控訴審または上告審
判決で遺言無効が確認されると、これに納得できない被告側から控訴・上告が行われる場合があります。改めて審理されると、逆転敗訴となる可能性も否定できません。
そこで、原告側の立証方法等をより慎重に検討する必要があります。
遺産分割協議
控訴期間が過ぎて勝訴が確定したら、ここでようやく遺産分割のやり直しに着手できます。
共同相続人に連絡して集まってもらい、合意形成できれば「遺産分割協議書」を作成しましょう。
なお、遺言無効の原因が特定の相続人にある場合は、この相続人を遺産分割協議から排除するための訴訟を起こせる可能性があります(詳細は後述)。
遺言が無効となる原因の立証手段
遺言無効の証拠となるものは、大きく5種類に分けられます。
いずれも客観性が高ければ高いほど有力となり、より有力なものほど確保の難易度も上がります。また、弁護士のサポートは得られるものの、基本的には遺言無効を主張する人自身で集めなくてはなりません。
診療記録
遺言能力がなかったことを証明する手段として、遺言書が作成された時期の診療記録が挙げられます。具体的には、担当医の診断書、カルテ、看護記録、検査記録等が挙げられます。
なお、個別の遺言無効確認事件では、上記記録にある症状やその程度が慎重に判断されます。
介護サービス事業者が保有する記録
訪問介護やデイサービスを利用していた場合、その事業者が保有する記録を医療記録と組み合わせることで、主張したい内容が補強されます。具体的には、業務日誌、介護記録、介護保険を利用する際に作成されるケアプラン(介護サービス計画書)等が挙げられます。
難しいのは、上記記録の開示に応じてもらえるかどうかです。開示請求者の立場を見て断られる、一部秘匿される、あるいは開示前に改ざんされる等といったことがあり得るのです。
また、介護サービスにかかる記録は「あくまでも補助的な立証手段」と考えなくてはなりません。医師免許がない以上、「認知症」等と言った医学的な見解が書かれていても、正式な診断に基づくものか否かは判然としないとして主張が退けられる場合もあるのです(東京地裁判決平成27年8月31日等)。
遺言者の筆跡や印影が分かる書類
遺言書に手が加えられている可能性がある場合は、遺言者の筆跡や印影が分かる他の書類が立証手段となります。遺言書の本文や署名欄と照合し、明らかな相違点があれば「第三者による偽造・変造」だと断定できるのです。
実際の手続きでは、調査会社(鑑定事務所)に依頼して報告書をもらい、それを裁判所に提出するのが一般的です。ただ、原告(=遺言の無効を主張する人)の主観がある程度入っていると考えられ、審理中の証拠調べで改めて鑑定される可能性があります。
遺言者とのやりとりに関する記録
「方式違背等はないが内容がおかしい」といった場合は、遺言者との生前のやりとりに関する記録に基づいて遺言無効を主張できます。具体的には、贈与契約書、生前贈与の状況が分かる入出金明細、メールやメッセージアプリ上の会話記録、面会記録等が挙げられます。
上記資料では「生前の言動とつじつまが合わない」と主張を裏付けられる他、本人の意思を歪めた(もしくは詐欺や強迫をした)と思われる人物の行動も証明できます。
⇒相続財産・遺産の使い込み・独り占め等の問題を解決する方法を見る!
証人および立会人に関する書類
証人および立会人に問題があったと主張する場合には、その身分や当時の状況を示す資料が立証手段になります。普通なら、結婚・離婚の履歴が分かる戸籍謄本で足りるでしょう。
気がかりなのは、他人の戸籍謄本を取り寄せられるかどうかです。結論として、第三者請求であっても「自己の権利を行使する等の正当な理由」があれば、問題なく請求できます。
遺言の内容を歪めた人物のペナルティ
遺言の内容を故意に歪めた者、あるいは遺言無効確認訴訟に先手を打とうと遺産を横領した者には、相応のペナルティがあります。今後その人物を遺産分割に関わらせないためにも、粛々と必要な対処を進めましょう(下記参照)。
相続欠格
たとえ被告に相続権があったとしても、その権利が剥奪される場合があります。それは、無効の理由が「相続人の欠格事由」(民法第891条各号)にあたる場合です。
遺言の効力を巡るトラブルでよくあるのは、遺言の偽造・改ざん・変造(5号)、あるいは詐欺または強迫(4号)です。
もしも遺言無効にかかる主張が欠格事由に該当するなら、遺言無効を確認するのと併せて「相続権不存在確認請求訴訟」を提起しなければなりません。左記請求で権利が失われれば、その人物を遺産分割協議から排除できます。
不当利得返還義務
遺言が無効になる前に処分されていた財産は、「不当利得」として被告に返還義務が生じます。
典型的なのは「内容証明郵便が届いたことに慌てて、預金口座から急いでお金を下している」といったケースです。この場合、任意交渉しても返金に応じないだろうとの見込みが立っていれば、遺言の無効主張にかかるものと「不当利得返還請求訴訟」を併合提起する方法が検討できます。
まとめ
「遺言がおかしい」と主張する際は、無効となる原因について具体的に主張・立証しなければなりません。本記事で紹介した原因で最も多いのが「遺言能力がない」と指摘するケースですが、該当する場合でも、遺言無効確認訴訟のやり方はケースバイケースです。
また、実務上は以下のポイントも十分注意しなければなりません。
- 遺留分侵害額請求の意思を事前に伝えたか
- 同じ立場にある共同相続人と連携できそうか
- 証拠資料の開示に保有先が応じるか
細かい点では、訴状の書き方や口頭弁論期日の対応についても、自力対応だと頭を抱えることになります。もしもの時は弁護士に相談し、手続きに関する助言・訴訟活動・共同相続人との連携等といった強力なバックアップを得ましょう。