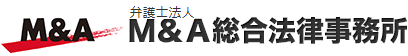相続時精算課税制度のメリット・デメリット!

贈与税の軽減制度である「相続時精算課税」を適用することで、相続財産評価額のうち上限2,500万円まで一時的に非課税とすることが出来ます。生前対策のひとつとして一見有用に見えますが、活用の判断は慎重さが求められるでしょう。
相続時精算課税の効果から適用要件・重要なメリット&デメリットまで、相続を控えた家族が押さえておきたいことを紹介します。
⇒相続財産・遺産の使い込み・独り占め等でお困りの方はこちら!
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、被相続人から相続人へとあらかじめ生前贈与しておくことで、贈与税の税制優遇が受けられる制度です。
本制度を適用してから贈与を行うことで、贈与における通常の課税方式(暦年課税)の各項目において、以下のように変更されます。
| 相続時精算課税の効果 | |||
| 比較項目 | 適用前(暦年課税) | → | 適用後 |
| 控除額 | 110万円 | 2,500万円 | |
| 税率 | 10%~55% | 20% | |
適用要件
相続時精算課税では、贈与当事者の年齢・身分関係の要件があります(以下紹介)。
なお、資産種類の要件はありません。
贈与者年齢:60歳以上 受贈者との関係:父母または祖父母 |
受贈者年齢:20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点) 贈与者との関係:直系卑属のうち推定相続人※または孫 |
「直系卑属のうち推定相続人」とは
→直系卑属とは子・孫以降の世代を指し、このうち推定相続人とは最も先順位の相続権を持つ人(=直系卑属のなかでも最も上の世代)を指します。
【注意】適用対象の贈与分は後日課税される
相続時精算課税を適用して税額の軽減対象となった贈与分は、贈与者の死亡時(相続開始時)に相続税の課税対象となります。支払い済みの贈与税は相続税から控除されるものの、実質的には「課税の先送り」に過ぎないともとれるでしょう。
しかし、活用方法・適用する資産に注意すれば、節税効果は十分得られます。どういった点に注意すればよいのか、いったん具体的な適用イメージを紹介した上で解説します。
相続時精算課税の適用イメージ ※相続人=子1人の場合
| 父から子へ評価額3,000万円の資産を生前贈与贈与税の税額
= (3,000万円 - 特別控除額2,500万円) × 20% = 100万円 |
| 父が死亡し、子が評価額2,000万円の資産を相続正味の遺産額…5,000万円(生前贈与額3,000万円を算入した結果)
相続税の額 = (5,000万円 - 基礎控除3,600万円) × 20% - 支払済贈与税100万円 = 80万円 |
相続時精算課税のメリット
相続時精算課税には、注目すべきメリットとして次の2点が挙げられます。
相続時は「贈与時点の評価額」で税計算される
本制度を適用した生前贈与に対して相続税が発生するときは、あくまでも「贈与したときの評価額」で税計算が行われます。
この仕組みで恩恵を受けられるのは、株式等の評価額が大幅に上がる可能性のある資産でしょう。生前贈与しないままだと価額上昇分まで課税対象となってしまうところ、本制度適用の上で贈与しておけば、課税対象額を将来に渡って現時点のまま据え置けるのです。
⇒相続財産・遺産の使い込み・独り占め等でお困りの方はこちら!
事業承継税制と併用できる
自社株式を贈与または相続したときの納税猶予制度(=事業承継税制)は、平成30年度より相続時精算課税制度と併用できるようになりました。ファミリー企業の経営者が生前に親族内後継者を決めるケースにおいては、ますます税制面で有利となります。
先述の贈与時点の時価が相続税の課税対象となるメリットとあいまって、後継者に余念なく企業の拡大を図ってもらえます。
相続時精算課税のデメリット
評価額が大幅に上がる可能性のある資産(特に自社株式)が本制度適用に向いている一方で、少額資産または不動産への適用は十分検討すべきです。
理由として、以下2点のデメリットが挙げられます。
適用後は暦年贈与に戻せない
資産額が小さいほど、相続時精算課税よりも暦年課税のほうが税額上有利となる可能性があります。しかし、本制度適用後にふたたび暦年課税に戻すことは出来ません。
「予定していたよりも生前贈与額が少なかった」といった事態を念頭において、遺産承継プランをきちんと立てておく必要があります。
小規模宅地等特例が使えない
小規模宅地等特例(宅地等の相続税評価額を最大80%減額できる制度)は、相続時精算課税制度と併用できません。十分な検討なしに不動産の生前贈与を行ってしまうと、かえって税額が高くなるでしょう。
こうした側面を踏まえ、不動産の生前贈与の際は税理士による提案が必須です。
まとめ
あらかじめ生前贈与しておくことで贈与税の優遇が受けられる「相続時精算課税制度」は、あとから相続税の課税対象となる点に要注意です。
その仕組み上「将来にかけて評価額が上がる資産」には適していますが、不動産・少額で価値の上がりにくい資産を適用対象とする場合は、十分な検討すべきでしょう。
本制度適用可否を含め、生前贈与と遺言書を組み合わせた税対策は、弁護士・税理士などの専門家を交えて行うことをおすすめします。