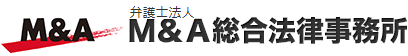遺言書に自分の名前がない!相続できない!納得できない!弁護士が徹底解説!

相続が起きると故人が残した財産は相続人に承継されることになりますが、誰にどの財産をどれだけ承継させるかは基本的に被相続人が自由に決めることができます。
遺言書が用意されていない場合は民法で定めた法定相続分が原則適用となりますが、遺言書がある場合は法定相続分に優先されます。
法律よりも遺言書が優先されるのは亡くなる方の遺志を尊重するためですが、もし相続人であるあなたに対して遺産の分配が指示されていなかった場合、原則として何の財産ももらえないということになってしまいます。
この場合でも諦める必要はなく、弁護士に相談すれば法律的な観点から相続人としての権利を主張していくことが可能です。
本章では「遺留分」という権利に着目して、相続財産を受け取る権利を主張していく方法をお伝えします。
⇒遺留分トラブルを解決する方法を見る!
遺留分とは?
遺留分というのは、一定の相続人の方に保証された最低限の遺産の取り分のことをいいます。
遺留分は遺族の生活保障の意味合いもあり、残された遺族が生活に困ることが無いように、法律で認められている権利です。
例えばですが、「愛人に全財産を譲る」と残して一家の主が他界したらどうでしょう。
それが故人の遺志である以上やはり尊重しなければなりませんが、それにしても遺族には酷な話です。
そうした場合でも、残された一定の相続人は遺留分を主張することで最低限の遺産の取り分を確保することができます。
遺言書で遺産の取り分が指定されなかった場合も遺留分の主張は可能ですので、今回のテーマのような事例でも遺留分の知識が役に立ちます。
ただし、遺留分が認められるのは法定相続人のうち以下の者だけです。
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(両親や祖父母など)
被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
また遺留分はあくまで権利であり、自動的に確保できるわけではありません。
遺言書に遺産の取り分の指示がないなど、自身の遺留分が侵害されている場合に、自ら遺留分を主張しなければならない点に注意が必要です。
昨今はトラブルが起きない遺言書の準備の仕方について各所から情報発信がなされていますから、遺言書を残す方が遺留分権利者に配慮し、あらかじめ各人の遺留分を侵害しない内容とすることも多いですが、そうでないケースもかなりあります。
本章のテーマのように一切遺産を受け取れない遺言内容となっていた場合は、自ら遺留分を主張しなければなりません。
遺留分はどのくらい認められる?
遺留分は最低限の取り分ですので、法定相続分を保証されるわけではありません。
遺留分は「総体的遺留分」と「個別的遺留分」という二つの概念があります。
総体的遺留分というのは、遺留分権利者が複数人いる場合における、遺留分権利者全体が保有する遺留分割合をいいます。
総体的遺留分は相続財産全体に対し、直系尊属のみが相続人となる場合は三分の一まで、それ以外の場合は二分の一まで認められます。
そしてその総体的遺留分を各相続人の法定相続分で配分したものが「個別的遺留分」です。
以下で、ケースごとに各人が実際に受け取れる個別的遺留分をまとめて見ます。
| 相続人の組み合わせ | 相続人 | 各人の遺留分 |
| 配偶者のみ | 配偶者 | 二分の一 |
| 配偶者と子二人 | 配偶者 | 四分の一 |
| 各子 | それぞれ八分の一 | |
| 配偶者と父母 | 配偶者 | 三分の一 |
| 父母 | それぞれ十二分の一 | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 二分の一 |
| 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹は遺留分無し | |
| 父母のみ | 父母 | それぞれ六分の一 |
次に、自身に遺留分が認められる場合、どのようにその権利を主張していくのか見ていきます。
遺留分侵害額請求で権利を主張する
遺留分の権利は各人が能動的に主張する必要があり、そうしないと遺留分を取り戻すことができません。
自身が受け取れなかった遺留分の財産は、他の相続人等に多く分配されている状況ですから、これを取り戻すというイメージです。
遺留分を主張する場合、他の相続人等に対し「遺留分侵害額請求」という形で請求することになります。
請求の相手方は個別のケースによりますが、他の相続人や受遺者、生前に故人から生前贈与として財産を受け取ったことのある一定の受贈者などです。
事案によって請求する相手が異なるので弁護士に相談することをお勧めします。
なお遺留分侵害額請求は口頭や通常の手紙などで行うこともできますが、通常は内容証明郵便を用い、請求の証拠が残る形で行います。
相手が請求を拒否すれば将来的に訴訟となり、その際に請求したことの証拠となることや、後述する時効の問題に対応するためです。
遺留分に関する実際の手続きの流れ
それでは、実際に自身の遺留分を取り戻すための手順と流れを確認していきます。
前提として、前述したように自身が遺留分の権利を認められる立場であり、遺言書に遺産の取り分について記載がないケースを想定します。
相続人調査、確定
個人の遺留分は、その事案で誰が相続人となるのか、また相続人の人数を確定させないと正確な判断ができません。
そのためまずは故人の戸籍を遡って相続人調査を行う必要があります。
故人が生前に頻繁に引っ越しをしていたケースでは、遠方にある複数の役所に掛け合って何度も郵送でのやり取りを繰り返さなくてはならないこともあります。
相続財産調査
遺留分は故人が残した遺産に対する取り分ですから、その遺産がどれくらいあるのかを正確に知る必要があります。
中には他の相続人が遺産の一部を隠しているようなケースもありますし、そうでなくとも金融機関に照会をかける必要があるなど、相続財産調査は素人の方には難しいことが多いです。
また過去の生前贈与についても誰にどれだけの財産が渡ったのか調べなければならないケースもあります。
遺留分を請求する相手方に財産の開示を求めなければならないこともあり、その場合利害が対立することから、当事者同士ではスムーズな財産調査ができないこともあります。
我々弁護士はこうした手配にも慣れているのでお任せいただくのが安心です。
相続財産の評価
遺産がすべて現預金であれば別ですが、多くのケースでは不動産や有価証券などが遺産に含まれます。
こうした遺産が金額にしていくらになるのか、正確に評価しなければ遺留分の算定ができません。
遺留分の対象となる財産は基本的に現時点での評価を算定することになりますが、過去になされた生前贈与の財産などは現在の価値に引き直して計算しなければならないなど、実務面で素人の方には難しくなっています。
遺産の評価を正しく行えないと自分に不利になってしまうこともあるので、弁護士などの専門家が正しく評価する必要があります。
遺留分侵害額請求
先述した遺留分侵害額請求を、ケースに応じた相手方に対して行います。
注意しなければならないのは、この請求権には時効があり、遺留分の権利があると知ってから(通常は相続開始から)1年で請求することができなくなることです。
相続人や遺産の調査にも時間がかかるので、できるだけ迅速に動く必要があることに留意しましょう。
通常の郵便や口頭での請求は1年以内に請求を行ったことの証明が難しいですが、内容証明郵便であれば証拠が残るので通常はこの方法で行われます。
民事保全手続き
遺留分侵害額請求をされた側は、自身の取り分が減少することを嫌って財産隠しをすることがあります。
これを防ぐため、ケースによっては民事保全の手続きによって財産の保全を考えます。
保全手続きは必須のものではありませんが、最終的に訴訟で争うことになった場合、確定した遺留分について保全財産から確実に回収できるので可能であれば検討します。
ただ裁判所に一定の補償金の納付を求められるので、この負担も考えつつ、保全の有効性が上回るかどうか考えます。
手続的にも素人の方には難しいと思いますので、弁護士に手配をお願いすることが多いでしょう。
交渉
自身の遺留分を侵害している相手方と交渉して財産の返還を求めます。
任意で応じてくれればよいのですが、そうでない場合は裁判所を通じた手続きが必要になります。
現実の問題点として、遺留分は仕組みが分かりづらいため相手に懇切丁寧に説明してもなかなか理解してもらえないことも多く、「遺留分など知らん」「適当なことを言って、俺から財産を巻き上げるつもりではないか」と反発されることもよくあります。
そのため相手方も弁護士を付けることがあり、こちらが素人の場合は相手の弁護士に言いくるめられて不利な条件を飲まされる恐れも出てきます。
調停
任意の交渉が上手くいかない場合は、裁判所に対し遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。
裁判所が間に入り話し合いを取りまとめるように尽力してくれますが、強制力はないため相手方が調停による話し合いに応じなかったり、話し合いが決裂した場合は調停不成立となります。
訴訟
調停でも話がまとまらなかった場合は、最終的に裁判によって決着をつけることになります。
⇒遺留分トラブルを解決する方法を見る!
遺留分を巡る注意点
遺留分に関しては少し前に法改正が入っておりルールが変わっています。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれており、こちらは遺留分を返してもらうにあたり、原則として不動産など金銭以外の物に対しても遺留分の権利が及びます。
そのため遺留分を取り戻した結果、相続財産たる不動産などが共有状態となることもあります。
法改正後の「遺留分侵害額請求」は金銭の請求権となり、遺留分の侵害について金銭で返還を求めることになる点で違いがあります。
2019年6月30日以前に発生した相続事案は法改正前のルールが適用となるので、その場合はまた違った対処法を検討する必要が出てきます。
遺留分に関する時効は二種類あり、一つは上述したように遺留分があることを知ってから1年ですが、特別事情があって相続があったことを知らなかったような場合は、「相続開始から10年」という別の時効ルールが適用されます。
法改正前のルールで遺留分を考える場合は現状のルールと違うことに注意が必要です。
もう一つの注意点としては税務処理に関してです。
遺留分に関する事案では、遺留分を侵害する者から遺留分権利者に対して財産の移動が起きます。
これに応じて相続税の申告納税が必要になったり、納税額が変わることで修正申告が必要になることもあります。
相続税の計算は複雑で、遺留分を手にしたことで意図せず相続税額が増大し、結局手元に残る資産が減ってしまうということも考えられます。
そのため遺留分に関しては税務的な観点も含めて総合的に考えていく必要があります。
当事務所では必要に応じて税理士とも連携しながらワンストップで事案の処理にあたりますので、依頼人の方に負担はありません。
相続事案に明るい弁護士なら遺留分を増額できることも
遺留分は仕組み自体が素人の方に分かりにくいものであり、また請求の仕方を間違うと本来得られるはずだった利益を得られないこともあります。
そのため遺留分の請求は弁護士に依頼される方が元々多い分野ではあるのですが、その際には適当に弁護士を選ぶのではなく、ぜひ遺留分に詳しい弁護士に相談して頂きたいと思います。
というのも、遺留分に関する細かい論点では判例などを駆使して主張していく必要があり、遺留分に明るくない弁護士では依頼者の利益を最大現に引き出せない可能性があるからです。
普段から相続事案を扱っていて遺留分に関して深い知識と豊富な経験を持つ弁護士であれば、知見を駆使して依頼人の利益を最大化できます。
また弁護士は他の相続人に使い込まれた相続財産がないかどうか調べたり、相続人が生前に被相続人から援助を受けたことがないかを調べ、その事実がある場合には相続のルールに則って遺留分権利者の取り分が増えるように手配することもできます。
また遺留分の対象になる不動産が値上がりしているような場合も、正しい財産評価を行うことで請求額を増やすことが可能です。
相続や遺留分に詳しい弁護士であれば、考えうる限りの方策をもって依頼者の利益を最大化することができるので、弁護士選びはぜひ慎重に行ってください。
まとめ
本章では遺言書に自分の相続財産に関する取り分の記載がなかったケースを想定し、「遺留分」という権利をもとに最低限の取り分を主張していく方法について見てきました。
遺留分は一定の相続人に認められたもので、遺言によっても侵害することができない権利です。
遺留分の仕組みを使って自身の取り分を確保することができますが、自分から主張しなければならないことや、時効の問題があることに注意が必要です。
実際に遺留分の権利を主張していくには、故人の財産調査や相続財産の評価、請求手続きや交渉など実務面で素人の方には難しくなっています。
当事務所では遺留分に関する問題を多く扱っており、これまで多くの方の遺留分確保に尽力して参りました。
依頼人の利益を最大化するのはもちろん、税務面で調整や考慮が求められる場合には必要に応じて税理士とも連携する体制を取っております。
当事務所では、ワンストップで相談を受け付ける体制を整えておりますので、安心してご相談頂ければと思います。
⇒遺留分トラブルを解決する方法を見る!