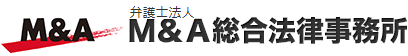相続における寄与分の決め方・計算方法について解説
お困りではありませんか?

相続が発生した場合に、遺言がなければ法定相続分によって遺産分割を行なうことになります。
しかし、被相続人が体が不自由になり、長男が長年介護をしていたような場合に、他の子と相続分が全く一緒であるのは不公平という感覚を持つ方も多いと思います。
このような、被相続人に一定の貢献があった場合について、相続においてもそれを評価するために仕組みとして「寄与分」というものがあり、どのように計算すればいいのか我々弁護士に多く相談が寄せられます。
このページでは、寄与分とはどのようなものか、相続におけるどの段階で問題になるのか、争いになった場合にはどうやって解決するのか、についてお伝えします。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与をした相続人に認められるもので、財産の維持・増加に貢献した分だけ他の相続人よりも多く相続ができる仕組みです。
例えば、相続財産が1,000万円あり、配偶者と子2人が相続人であるとします。
この場合、法定相続分に従うと、配偶者が1/2・子がそれぞれ1/4づつ相続分があることになり、金額に直すと配偶者が500万円・子がそれぞれ250万円づつとなります。
しかし、子のうち一人が、被相続人の介護をしていたような場合で、その金額が介護費用に換算すると100万円になると評価できる場合に、子が介護をしたことから被相続人は100万円の財産を失わずに済んだといえます。
このような場合に、介護をした子を相続においても優遇しようというのが寄与分です。
寄与分が認められるときには、相続財産1,000万円から寄与分の100万円を引いた900万円を法定相続分で分割し、寄与分が認められる相続人に引いた100万円を加算します。
そのため、配偶者は450万円(900万円✕1/2)・寄与分が認められる子が325万円((900万円✕1/4=225+100万円)・もうひとりの子が225万円分と計算することになります。
このように、寄与分は法定相続分による相続では、個別具体的に見て不平等となるときにそれを是正することができるシステムです。
遺産分割におけるどの過程で問題になるか
遺産分割において寄与分はどの過程で問題になるのでしょうか。
相続分の計算は
- 法定相続分の計算
- みなし相続財産を計算
- 具体的相続分を計算
という過程で行われます。
法定相続分の計算は、相続人が誰かを確定した上で、それぞれの法定相続分(上記の例だと配偶者が1/2・子がそれぞれ1/4づつ)算出します。
みなし相続財産の計算は、相続財産から寄与分を差し引いて特別受益分を加算して求めます。
上述の例でいうと、相続財産が1,000万円と計算され、寄与分を差し引いた900万円が「みなし相続財産」とされます。
寄与分はこのみなし相続財産の計算の過程で問題となります
みなし相続財産を計算した上で、その相続財産を法定相続分で按分し、寄与分・特別受益分を加算・減産して求められるのが具体的相続分です。
上述の例で言うと、配偶者が450万円・寄与分が認められた子が325万円・寄与分が認められなかった子は225万円が「具体的相続分」です。
このように具体的相続分の計算にも寄与分は影響します。
弁護士への相談によくあるのが、この計算が複雑でよくわからないというものです。
代襲相続人の寄与分の主張
例えば、Aは長男Bによって介護されていた場合で、Bが先に亡くなってからAが亡くなるという場合があります。
この場合にBに子がいる場合(仮にCとします)には、Aの相続についてCはBの分を代襲相続することになります。
この場合、CはAを直接介護したわけではなくても、Bが生きていれば認められたであろう寄与分を相続において主張することが可能です。
これは、CはBの相続人としての地位を引き継いでいるためです。
包括受遺者による寄与分の主張
遺言で、相続人以外の人に相続させる方法の一つとして、割合を指定して相続をさせる「包括遺贈」というものがあります。
この包括遺贈によって遺贈を受ける人のことを包括受遺者といいます。
たとえば、被相続人の長男夫妻が同居をしていて、長男の妻が介護をしていたようなケースがあります。
長男の妻は同居をしていてもそのままでは相続人ではありません(後述する特別寄与料の請求をする余地はあります)。
そのため、長男の妻の献身に応えたいと考えた場合には、長男の妻に遺言で遺贈をすることがあります。
その方法として相続財産に対する割合を示して遺贈をすることがあります(例:相続財産の1/5を長男の妻○○に相続させる)。
この場合に長男の妻が寄与分を主張できるかについて、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされており(民法990条)、相続人に認められる寄与分も主張することが可能であるとされています。
親族間の遺産分割協議に参加してもらうというものになり、紛争の火種になりかねないので、あまり弁護士がご提案する遺言の方法ではありません。
遺贈と寄与分の関係
遺贈と寄与分の関係について、民法904条の2第3項は「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」としています。
例えば、相続財産が1000万円で寄与分と認定される額が200万円あるときに、相続財産のうち900万円分を遺贈するという遺言があったとしましょう。
遺贈がなかったとすると、寄与分の200万円を差し引いて、みなし相続財産は800万円であるという計算になります。
しかし、相続財産から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできないとされているので、相続財産から900万円の遺贈がされているこのケースでは、寄与分として主張できるのは100万円ということになります。
なお、この規定によって相続できなくなる相続人も発生しますが、別に遺留分侵害額請求権を行使することができます。
遺言で相続分が指定されているときの寄与分の関係
遺言で相続分が指定されていることがあります。
例えば、配偶者に500万円・寄与分が認められる相続人が300万円・寄与分が認められない相続人に200万円としたとしましょう。
先程の遺贈があった場合には寄与分の規定に優先するという条文(民法904条の2第3項)の趣旨からは、遺言で記載する内容は法律の規定に優先するの筋であると考えられています。
遺言をする際に寄与分があることも含めて検討しているのですから、その部分について尊重するという趣旨から、相続分が指定されている場合には、遺言で定められた相続分で具体的相続分を決定し、寄与分は考慮しないことになります。
遺留分と寄与分の関係
遺留分は相続分の1/2ないし1/3として計算されます(民法1042条1項1号・2号)。
このときに寄与分や後述する特別受益などは考慮しないこととされています。
そのため、寄与分は遺留分に影響しません。
また、寄与分が遺産の額のほどんどを占める結果になった場合や寄与分の額のほうが多い場合、他の相続人の相続分を侵害するのでは?という主張をされることになります。
例えば、遺産が1,000万円で配偶者・子2人が相続人である場合に、子の一人の寄与分が1,000万円ある場合に配偶者・もう一人の子は相続できなくなります。
この場合には寄与分の内容が優先され、他の相続人は遺留分侵害額請求をすることはできないと解釈されています。
寄与分の類型
ここまで「寄与分」という内容でのみお伝えしていましたが、「被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与」として認められる行為として次の5つの類型があります。
弁護士が依頼をうけて寄与分を算定する際にも参考にするものです。
家事従事型
被相続人となる人が個人事業をしていて、その事業を手伝っていたような場合には、従業員を雇わなくてよかったため支出をしなくてよかった・手伝ってくれたため利益がたくさん出た、といえます。
そのため、寄与分として認められる可能性があり、このような類型での寄与を家事従事型と呼んでいます。
ただ、給与を出していた場合には、その給与が極端に少ないような額でも無い限り、特別の寄与とはいうことができず、寄与分は認められません。
家事従事型寄与分を計算する場合には、一般的に次のような計算式が用いられます。
寄与者が通常得られたであろう年間の給付額×(1-生活費控除割)×寄与年数-現実に得た給付✕裁量的割合=家事従事型寄与分
寄与者が通常得られたであろう年間の給付額は、国の統計資料や賃金センサスなどを参考にしたり、同業他社の給与額を参考に計算します。
生活費控除割合とは、被相続人から生活費として受け取っていた割合のことをいいます。
金銭等出資型
被相続人が体が不自由になり介護施設などに入居する際の費用を負担していたり、借金の返済を行った場合には、被相続人は費用を支払わなくてよかったといえることから、特別の寄与といえます。
なお、被相続人が会社を経営していて、会社に出資していた場合には、被相続人とは別に会社への出資分として考えられるため。寄与分にはあたりません。
金銭等出資型の場合には、
贈与額✕貨幣価値変動率✕裁量的割合=金銭等出資型寄与分
として計算します。
不動産を贈与した場合には、相続開始時の不動産の時価で、不動産に住まわせていたなどして使用貸借をしていた場合には、
賃料相当額✕使用期間
で計算します。
裁量的割合とは、裁判所で争われた場合に、裁判所が事情を考慮して増額・減額をする場合の割合です
療養看護型
仕事を退職して、被相続人の療養看護につきっきりであったような場合には、被相続人はヘルパーを雇うなどの負担がなかったといえ、財産を維持できたといえますので、寄与分が認められます。
ただし、相続人が行っていた療養介護が、単に話し相手をしていただけのような場合で、被相続人の費用支出を免れたていたとはいえない場合には、寄与分とは認められません。
また、同居している長男の妻が療養看護をしていた場合で、長男自体は通常通り仕事を続けていていたような場合に、長男自身は特別な寄与をしていないので寄与分は認められません。
この場合、長男の妻は特別寄与料の請求をすることができる場合があります。
療養看護が必要であったかどうかについては、一般的には要介護認定の程度によって判断します。
療養看護型の寄与分が認められるためには、要介護度2以上であることが目安となります。
療養看護型の寄与分の計算は、
介護福祉士・ヘルパーへの日当相当額✕療養看護日数✕裁量的割合=療養看護型の寄与分として計算します。
扶養型
被相続人の生活費を負担していたような場合には寄与分が認められる可能性があります。
ただし、夫婦・親子・兄弟姉妹は相互に扶養をする義務があり、この扶養義務の範囲内で金銭支出をしていただけの場合には、寄与分としては認めらません。
扶養義務の範囲を超える生活費の負担をしているような場合に限って寄与分が認められることになります。
扶養型の寄与分の計算は、
負担した扶養額×負担した期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)=扶養型寄与分額
で行なわれます。
財産管理型
被相続人の財産管理をしていたような場合には寄与分が認められることがあります。
例えば被相続人が不動産を賃貸しており、各種手続きを子のうちの一人がしていたような場合に、被相続人としては専門家などに依頼する費用の負担がなかったといえますので、寄与分として認められるといえます。
財産管理型の寄与分の計算は、
管理や売却を第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合=財産管理型の寄与分額
で行なわれます。
寄与分と併せて問題になるもの
寄与分について問題になる際に合わせて問題になるものとして、特別受益・特別寄与料の2つを確認しておきましょう。
特別受益
特別受益とは、被相続人から遺贈を受けたり、結婚のための費用をもらったり、生活費などを贈与されていた場合に、相続分から差し引く分のことをいいます(民法903条)。
寄与分は被相続人の財産にプラスになることをした人を優遇する制度であるのに対して、特別受益は被相続人の財産にマイナスになることをした人の相続分を差し引くもので、反対の事情を考慮するものです。
この場合には、特別受益といえる額を相続財産に加算してみなし相続財産を計算して、具体的相続分を計算する際に加算した特別受益の分を相続人の相続分から差し引きます。
たとえば、被相続人の遺産が1,000万円で、相続人は妻・子2人である場合に、子のうちの一人が結婚をする際に200万円の現金の贈与を受けていた場合を想定しましょう。
このときには特別受益といえる200万円を加算した1,200万円がみなし相続財産となり、1,200万円をもとにまず法定相続分で按分します(妻600万円・子2人それぞれ300万円)。
そして、特別受益として加算した200万円分を、特別受益を得た子から差し引くので、特別受益を得た相続人である子の具体的相続分は100万円として計算されることになります。
寄与分と特別受益両方がある場合には、一緒に計算をしてみなし相続財産を計算することになります。
特別寄与料
寄与分は特別の寄与があった相続人のみに認められる制度です。
しかし、上述したような同居している長男の妻が被相続人の介護をしていたり、一家の事業を手伝っているようなケースもあります。
このような場合、相続人ではないため寄与分の適用はなく、遺贈をしたり・養子にして相続人にするなどの対策がなければ一切相続財産に何らの主張もすることができないとされていました。
しかし、このような寄与を一切考慮しないというのは、常識的には受け入れがたいという人も多いのではないでしょうか。
そのため、相続法が改正され2019年7月1日から、相続人以外の親族が特別の寄与をしたといえる場合には、特別寄与料という金銭の請求をすることができるものとしました。
ここでいう「親族」とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族がこれにあたります。
長男の妻である場合には1親等の姻族なので親族にあたり、特別寄与料の請求が可能です。
寄与分の計算方法
寄与分の計算については、上記で示したような計算方式で一般的には計算されますが、最終的な金額の決定は、1に当事者の協議によって行ない、当事者の協議によって定まらない場合には、調停・審判を利用します。
遺産分割協議
まずは遺産分割協議の中で遺留分の額を確定します。
上記で示した計算式は、以下の調停・審判に進んだときに、裁判所が認定するのに利用する計算式ですが、当事者間での交渉に利用することも可能です。
当事者間の交渉で決めるものになるので、実際に法的手続きを使ったときに認定されるであろう額よりも多い・少ない額で認定することもできます。
協議で寄与分の合意が得られ、他の特別受益などの額を確定し、みなし相続財産を確定した上で、誰がどの遺産をどうやって分割するかを決めます。
なお、寄与分として評価される額があったとしても、実際の遺産の分割にあたって、他の相続人よりも低い額の相続をすることも可能です。
例えば、遺産として2,000万円の不動産と1,000万円の預金があり、500万円の寄与分が認められる相続人が1,000万円の預金を相続して2,000万円の不動産を具体的相続分が低い他の相続人が相続することも差し支えありません。
協議で行なう内はある程度は自由に交渉することができるといえるでしょう。
遺産分割調停
協議で寄与分の額に合意できず、最終的な遺産分割協議ができない場合には、法的な手続きによって遺産分割を行ないます。
法的な手続きというと裁判を思い浮かべる人が多いと思いますが、遺産分割にあたってはまず調停を行ってから、審判という方式の法的手続きを利用します。
遺産分割調停とは、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が、相互の主張を聞いた上で合議で調停案を当事者に示し、これに当事者が合意すれば調停案の内容で紛争解決とする制度です。
遺産分割のように当事者が家族・親族であるような場合には、紛争が終わった後でも関係が続くので、なるべく話し合いで柔軟な解決案を模索して、丸く収めるべきと考えられてます。
そのため、話し合いの延長である調停を利用して、柔軟な解決をはかることにしています(調停前置主義)。
調停では家庭裁判所に出頭をして、当事者が個別に呼ばれて、裁判官・調停委員に主張を聞いてもらいながら、妥協案を探します。
寄与分の額について争いになった場合には、寄与分を主張する人が金額とその計算根拠を主張し、必要に応じて証拠を提出して、裁判官・調停委員と交渉を行ないます。
裁判官・調停委員は、その主張に対して問題点を指摘したり、どのくらいの金額であれば妥協できるかを聞いてくることが想定されます。
その主張に対して、寄与分によって相続分が減ってしまう方からも事情を聴取し、妥協点を話し合います。
このときに、寄与分を主張されている人が、遺留分など一切認めないというような主張をしても、法的に認められる権利である以上裁判官・調停委員には取り合ってもらえません。
寄与分や他の争いについて、相互に裁判官と調停委員が意見を聞きながら妥協点を模索し、最終的には、裁判官と調停委員の合議で調停案を作成します。
当事者がこれに納得すれば、調停が成立し、寄与分についての紛争も解決します。
遺産分割審判
調停案に当事者のどちらかが納得できない場合には、遺産分割審判を行ないます。
審判は裁判所が判断をするもので、裁判所の判断に当事者は拘束されることになる手続きで、裁判と聞いてイメージするものと同様に考えて良いでしょう。
調停は話し合いの延長ですが、審判は話し合いではなく、当事者の主張や立証をもとに裁判所が判断する手続きです。
寄与分の額やその他の争いについて、調停で合意ができなかった場合には審判手続を利用して最終的な判断を仰ぐことになります。
寄与分のみが問題となっている場合には寄与分を定める処分調停・審判を利用する
以上は寄与分だけではなく、遺産分割全般的に解決することを前提にお伝えしましたが、争っている部分が寄与分の額である場合には、「寄与分を定める処分調停」という手続きが用意されています。
また、この調停が調わない場合には、寄与分を定める審判という手続があります。
争いが寄与分の額にとどまっているだけならば、この手続を利用しても良いでしょう。
審判に不服の場合には即時抗告という方法で高等裁判所が判断する
審判に不服がある場合には、裁判における控訴のような手続きとして、即時抗告という制度があります。
この不服申立手段を用いると、家庭裁判所の上級審である高等裁判所で改めて判断してもらえるので、家庭裁判所での判断とは異なる判断が出る可能性はあります。
寄与分で争いがある場合には弁護士に依頼することをおすすめ
寄与分で争いがある場合には、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。
寄与分の計算は難しいので弁護士に計算してもらうのが良い
理由の一つめとしては、寄与分の計算は、上記のように裁判所で利用される計算式があるのですが、ではその一つ一つでいくら・どのくらいの割合と計算するのが正しいか、判断に迷うことは多いです。
ましてや、相続に関する当事者が複数いる場合には、当事者の見立てによって大きく金額が代わり、争いになることもあります。
弁護士に依頼して交渉をしてもらうと、過去の判例や類似の事例など、客観的な根拠に基づいて交渉をしてくれることになるので、相手も納得して交渉に応じることが期待できます。
感情的な対立が激しくなっているときには緩衝材になってくれる
寄与分を認めるということは、相続において家族の一人が相続において優遇されるかどうかが問題になります。
そのため、単に金銭的な問題だけではなく、感情的な対立が発生することがあります。
「寄与分というものがあって、金額も妥当であるのはわかっていても、あの人が多く相続することに納得行かない。」などの理由で、紛争が長引いてしまうこともあります。
このような場合には、弁護士は法的な主張を整理するだけではなく、当事者間の緩衝材となって、紛争を穏当に解決することに貢献することがあります。
相続当事者の仲が悪いような場合や、相続がきっかけで仲が悪くなってしまいそうな場合には、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
まとめ
このページでは、このページでは、寄与分についてお伝えしました。
特定の相続人が、被相続人に貢献していた場合の優遇措置なのですが、具体的な金額を決めることが難しく、紛争が長期化することも珍しくありません。
早めに弁護士に相談をして、スムーズな解決をはかることをおすすめします。
お困りではありませんか?