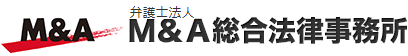遺言書がある場合の相続と遺留分との関係や、遺留分侵害額請求の対策について解説

遺産相続では、被相続人が遺言書を作成していない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
被相続人が遺言書を作成していた場合には、被相続人の遺産を希望した人に相続させられますが、法定相続人の遺留分については遺留分侵害額請求により金銭の支払いを請求することができます。。
遺留分とは、遺言書があった場合でも、兄弟姉妹を除く法定相続人が遺産を最低限取得できる権利のことです。
遺言書を作成した場合には、遺言書の内容によっては相続トラブルになり、遺留分侵害額請求を起こされる可能性もあります。
今回は、被相続人が遺言書を作成していた場合の遺留分との関係についてや、遺言を作成する場合の遺留分対策について解説していきます。
また、遺留分侵害額請求を起こされた場合に、どのような対策をすればよいのかについても解説していきます。
遺留分とは
遺留分制度とは、被相続人の相続財産について、は配偶者、子供、親(祖父母)が法定相続人になる場合に一定割合の相続財産の承継について保障される民法に定められた制度です。
被相続人は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められますが、配偶者、子供、親(祖父母)などの被相続人と近い法定相続人は相続に対して期待しているものです。
そのため、遺留分を侵害するような遺言の作成や贈与をすることは法的には有効ですが、遺留分侵害額請求をされた場合は、金銭にて遺留分を支払う必要があります。
遺留分とは、法定相続人の生活の保障や、法定相続人の保護を目的とした制度なのです。
遺留分の割合
遺留分とは、法定相続人が配偶者、子供、親(祖父母)の場合に一定割合の相続財産の承継について保障される制度ですが、どのくらいの割合が保障されるのでしょうか?
遺留分が保障される割合は、配偶者か子供が法定相続人に含まれる場合は相続財産の1/2、法定相続人に配偶者、子供が含まれずに直系尊属のみの場合は相続財産の1/3です。
例えば、法定相続人が配偶者、子供1人の場合、法定相続分はそれぞれ相続財産の1/2ですが、遺留分はその1/2になりますので配偶者、子供それぞれ相続財産の1/4になります。
また、法定相続人が直系尊属のみの場合の法定相続分は相続財産の100%ですが、遺留分はその1/3になります。
遺言と遺留分の関係
民法では、被相続人が相続財産を遺言によって誰に相続させるかを決めることが認められています。
そのため、被相続人が特定の人に相続財産を残したい場合は、遺言書を作成するという方法があるのです。
ただし、相続には遺留分という大きな壁があり、すべての相続財産を特定の人に残すことは難しいと考えられます。
しかし、遺留分を請求するかしないかは法定相続人の意思によりますので、事前の対策をしておくことで希望通りの相続が行われる可能性が高まります。
亡くなった後に遺言書により被相続人の意思がわかった場合は、遺留分権利者との間で相続トラブルに発展することが多いため、生前にトラブルにならないように遺留分対策をしておく必要があるのです。
遺言で遺留分を廃除できるか
相続廃除とは、被相続人が特定の法定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することで、法定相続人の保有している遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。
ただし、相続廃除が認められる条件は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に限られます。
遺言で相続廃除をする場合は、遺言書の中で相続廃除の意思を示しておけば、被相続人が亡くなった後に遺言執行者が相続廃除の申し立てを家庭裁判所に対して請求します。
一方、遺言書で相続廃除の意思表示をせずに相続財産を特定の人に相続させる意思を示しても、法定相続人の権利である遺留分をすべて奪うことは難しいでしょう。
遺留分を侵害する遺言とは?
遺留分とは法定相続人の相続を受ける権利を守るための制度ですが、遺言書が遺留分を侵害するようなものであった場合には遺言書自体が無効になるのでしょうか?
遺言書の内容が遺留分を侵害するような遺言書であったとしても、無効ではありません。
ただし、遺留分の権利がある法定相続人が遺留分侵害額請求をした場合には、法定相続人は遺留分の範囲内に限って金銭の支払いを請求できます。
この場合に、遺留分の権利がある法定相続人が遺留分侵害額請求をしなければ、遺言書の通りに相続が行われます。
遺留分を侵害する遺言とは、以下のケースが考えられます。
特定の相続人にすべての相続財産を残す場合
法定相続人が複数いるケースで、遺言書にて特定の相続人にだけにすべての相続財産を残すようにする場合は遺留分を侵害する遺言になります。
例えば、遺言で子のうちの一人だけにすべての相続財産を残すとした場合は、他の子の遺留分を侵害することになるのです。
相続人以外の第三者にすべての相続財産を残す場合
法定相続人がいるケースで、法定相続人でない第三者にすべての相続財産を残すようにする場合は遺留分を侵害する遺言になります。
例えば、配偶者や子供がいる被相続人が、家族でない第三者にすべての相続財産を残すとした場合は、配偶者や子供の遺留分を侵害することになるのです。
特定の相続人に多くの相続財産を残すなど著しく不公平な場合
法定相続人が複数いるケースで、遺言書にて特定の相続人にだけに他の相続人よりも多くの相続財産を残すようにする場合は遺留分を侵害する遺言になります。
例えば、法定相続人である子供が複数いるケースで、遺言で子供のうちの一人だけに多くの相続財産を残すとした場合は他の子供の遺留分を侵害することになるのです。
遺言書の効力
被相続人が遺言書を残していなかった場合、被相続人の相続財産は法定相続人が相続をします。
相続財産によっては話し合いによる遺産分割が必要なものと、遺産分割が必要なく法定相続分により分割されるものに分かれます。
一方、被相続人が遺言書を残した場合は、遺言書により相続の方法を指定できます。
すなわち、遺言書の効力は、特定の相続人に法定相続分よりも多くの相続財産を残すこともできますし、法定相続人以外の第三者に相続財産を残すこともできるのです。
このような、遺留分を侵害するような遺言書の内容であっても、その遺言書は有効なのです。
遺言書の種類
遺言書の種類には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれについて見ていきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人が自分で遺言書を自書する形式の遺言書です。
費用がかからなく手軽に作成できることが自筆証書遺言のメリットですが、遺言書の保管者や相続人は遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。
ただし、法務局で遺言書の原本を保管してもらう遺言書保管制度を利用している場合は、検認は不要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい公証役場で原本を保管してもらう形式の遺言書です。
公証人が作成するために無効になりにくいことや、検認が不要なのが公正証書遺言のメリットですが、費用や手間がかかることがデメリットです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたままで公証役場で認証してもらえる形式の遺言書です。
遺言の内容を誰にも知られたくないけれども、遺言書があるという事実だけを認証したい場合に利用しますが、実際はほとんど利用されていません。
遺言を書く時のポイント
自筆証書遺言の場合は、遺言書を全文自筆で書き、作成日を記載して、署名・捺印が必要です。
自筆証書遺言が有効かどうかは、厳格に判断されます。
そのため、遺言書には、相続させる相手、遺贈する相手、相続財産などをきちんと特定できるように記載しなければなりません。
特定が不十分な場合は、遺言の効力が生じずに無効になってしまう可能性があります。
また、遺言書を書く時には、後で相続トラブルにならないように、遺留分への十分な配慮が必要です。
遺留分侵害額請求について
被相続人が遺言書により相続財産を遺留分権利者以外に残すなどの遺留分を侵害するようなものであった場合、遺留分の権利者は相続財産を受けた人に対して侵害額に相当する金銭を請求できます。
この侵害額に相当する金銭の請求を遺留分侵害額請求といい、遺留分侵害額請求権を行使することで遺留分の権利者は遺留分を回復できます。
ただし、遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分の権利者の任意であり、遺留分を侵害された場合でも遺留分侵害額請求をしないケースも多々あるのです。
法改正により遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ
遺留分侵害額請求は、2019年法改正により遺留分減殺請求から変更されたものです。
遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への変更点は、相続財産そのものを取り戻すことから、侵害額に相当する金銭を請求することに変わったことです。
例えば、遺留分減殺請求した相続財産が不動産などの場合、相続財産そのものを取り戻すために相続財産を受けた人と遺留分の権利者が一旦不動産を共有する状態になります。
そして、共有状態を解消するために、共有物分割請求をしなければならず、二度手間でした。
一方、遺留分侵害額請求は侵害額に相当する金銭を請求するため、不動産を一旦共有状態にしなくても金銭の請求だけでことが足りるのです。
遺留分侵害額請求の対象になる行為
遺留分侵害額請求の対象になる行為には、遺言書による遺留分の侵害や、生前贈与による遺留分の侵害になります。
遺言書による遺留分の侵害には、特定の相続人にすべての相続財産を残す場合や、相続人以外の第三者にすべての相続財産を残す場合などがあります。
法定相続人以外の第三者に対してなされた生前贈与による遺留分の侵害は、相続開始前の1年間に限って遺留分侵害額請求の対象になります。
一方、法定相続人に対する生前贈与による遺留分の侵害は、相続開始前の10年間、かつ、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与のみ対象となります。
遺留分侵害額請求の効果
遺留分侵害額請求とは侵害された遺留分を回復させる請求のため、遺留分侵害額請求権が行使された場合は、侵害された遺留分に相当する賃金を支払う必要があります。
遺留分侵害額請求では、相続財産そのものを請求することは認められず、金銭的請求に限定されています。
遺留分侵害額請求の請求期限
遺留分侵害額請求権には、時効と除斥期間がありますので注意が必要です。
遺留分侵害額請求の時効は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年間です。
また、相続開始の時から10年間が経過した場合は、除斥期間により遺留分侵害額請求権が消滅します。
遺留分侵害額請求の手順
遺留分侵害額請求の手順は、以下のように行われるのが一般的です。
遺留分侵害額請求の通知を行う
まずは、遺留分請求するという意思表示を遺留分権利者が侵害している側に通知をします。
この場合、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
相続人間で話し合いを行う
通知をしたら、円満な解決を目指し話し合いをします。
遺留分侵害額請求の調停の申立
話し合いでまとまらない場合は訴訟を提起することが考えられますが、遺留分に関する事件は家庭に関する事件のため、訴訟の前に家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる必要があります。
この場で調停案に合意できた場合は、調停成立となります。
遺留分侵害額請求訴訟
調停でまとまらない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
遺言書を作成する場合の遺留分対策
遺言書を作成して特定の人に相続財産を残したい場合などには、遺留分対策をしておかなければ後々相続トラブルになる可能性が高くなります。
遺言書を作成する場合の遺留分対策には、以下のような対策が考えられます。
付言事項の作成
遺言書には、法的な効力が発生しない付言事項を作成することが可能です。
付言事項とは、法的な効力が発生する遺言書の本文ではなく、なお書きにメッセージが記載された部分のことをいいます。
被相続人の気持ちを、遺留分の権利者の良心に訴えるような文章を書くと効果的です。
生前贈与をしておく
法定相続人以外に対する生前贈与は、相続開始前の1年間分が遺留分侵害額請求の対象になります。
また、法定相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年間、かつ、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与のみ対象です。
そのため、対象にならないように事前に生前贈与をしておくと、遺留分侵害額請求対策になります。
遺留分の放棄をさせておく
遺留分侵害額請求をしそうな法定相続人がいる場合には、生前に遺留分の権利者に家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可を申し立ててもらう方法もあります。
遺留分の放棄が認められるためには、遺留分を放棄する合理的な理由があり、遺留分の権利者に対価が与えられているという要件が必要です。
遺留分を放棄してもらうためには、事前に遺留分に変わる対価的な財産を与えておく必要があります。
相続人を増やす
遺留分を減らすためには、養子縁組などにより法定相続人を増やすという方法もあります。
法定相続人が増えれば、相続人ごとの遺留分も減らせます。
相続人全員での協議を生前にしておく
遺言書の作成をする前に、法定相続人全員と遺言書の内容について協議をしておくという方法もあります。
後々の相続トラブルを防ぐためには、事前の協議は有効かもしれませんが、全員が納得してくれるとは限らず反発が起こる可能性もあります。
まとめ
遺留分とは、一定の法定相続人が遺産を最低限取得できる権利のことです。
この遺留分を侵害するような遺言書を残したとしても、遺言書は無効になりません。
遺留分の権利者は、遺言書により遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求をするかどうかは遺留分の権利者が決めることができ、遺留分侵害額請求をしなければ遺言書の内容が有効になります。
遺留分を侵害するような遺言書を残すと、後々相続トラブルに発生することが多いため、被相続人は生前から遺留分対策をしておくとよいでしょう。