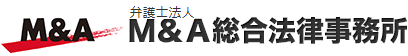公正証書遺言の効力が有効でも遺留分は請求できる?手続を分かりやすく解説
お困りではありませんか?

公正証書遺言は公証人の立会いのもと作成する遺言であるため、確実性の高い遺言といえます。もし、公正証書遺言が有効でも遺留分は請求できるのでしょうか。ここでは、その可否に加えて、遺留分制度や手続、公正証書遺言作成のポイントまで解説いたします。
公正証書遺言の効力が有効でも遺留分は請求できる
まず結論から申し上げますと、公正証書遺言の効力が有効でも遺留分を請求することは可能です。これは、相続人の権利を守るという遺留分制度の趣旨に基づいています。そこで、まずは遺留分制度について理解を深めましょう。
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人に法律上留保された相続財産の割合のことをいいます。被相続人は、自己の自由な意思により生前贈与や遺言ができますが、その内容によっては、法定相続分(民法上定められている相続分)に従えば財産を受け取ることができた相続人が一切財産を受け取れないということが起きてしまう可能性があります。これを、遺留分の侵害といいます。遺留分制度は、相続人の生活の安定や家族財産の公平な分配のために、被相続人の財産処分の自由を一定限度で制約する制度となっています。
遺留分権利者
遺留分の侵害を受けた一定の相続人のことを遺留分権利者といいます。具体的には、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)が遺留分権利者となります。なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者とはならない点に注意です。また、欠格・廃除・放棄によって相続権を失った者も遺留分権を失います。
遺留分の算定
はじめに、ここに説明する遺留分とは、後に説明する遺留分侵害額とは別の意味となります。遺留分は、下記の算定式により算出します。
| 遺留分 = ①遺留分を算定するための財産の価額 × ②遺留分の割合①遺留分を算定するための財産の価額: 被相続人が相続開始時に有していた財産【A】+贈与財産の価額【B】-相続債務の全額【C】
②遺留分の割合【D】:総体的遺留分×法定相続分の割合 |
A~Dの流れに沿って、具体的に解説していきます。
A.被相続人が相続開始時に有していた財産
相続開始時に被相続人が有していた財産には、預貯金等に加えて不動産も含まれます。不動産は価格の算定のため、評価を行なう必要があります。
B.贈与財産の価額
原則として、相続開始前の1年間にされた贈与が対象となります。ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは1年以上前のものについても算入されます。また、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年以内のもので、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額」、すなわち特別受益に該当する額に限り、遺留分算定の基礎として算入されます。
C.相続債務の全額相続人に負債がある場合
その全額を差し引きます。なお、被相続人の借金や医療費等の未払金は差し引けますが、葬儀費用はその対象となりません。
D.遺留分の割合
総体的遺留分に法定相続分の割合をかけたものが遺留分の割合となります。ここにいう総体的遺留分とは、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、直系尊属以外の者も相続人である場合は1/2です。これを法定相続分の割合に乗じて遺留分の割合は算定されます。
遺留分侵害額請求
遺留分の概要について理解を深めたところで、次は遺留分侵害額請求について解説いたします。
遺留分侵害額請求とは
上記の遺留分を有する相続人が被相続人から受けた相続財産の総額が、遺贈(*)及び贈与がなされた結果として遺留分の額に達しないときに、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分が侵害されたこととなります。そこで、遺留分権利者は、自身の遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求をすることができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
*遺贈…遺言によって自らの財産の一部または全部を無償で与えることをいいます。遺贈する相手方は、相続人でも相続人以外でも可能です。
遺留分を請求できる対象者
遺留分侵害額請求ができる対象者は、遺留分権利者及びその承継人です。
請求先の優先順位
遺留分侵害額請求の相手方は、受遺者または受贈者です。(*)
*受遺者…遺贈によって財産を受け取る者のことをいいます。受遺者は遺言の効力発生時に生存している必要があります。
*受贈者…贈与によって財産を受け取る者のことをいいます。贈与は双務契約であり、贈与者と受贈者の合意によって成立します。
遺留分侵害額請求がなされた場合、受遺者と受贈者は遺贈・贈与の目的の価額を限度として、以下の①~③の優先順位に従い遺留分侵害額を負担します。
- 受遺者と受贈者が両方存在する場合は、まず受遺者が先に遺留分侵害額を負担します。
- 受遺者が複数ある場合、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者・受贈者はその目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときはその意思に従います。
- 受贈者が複数あるとき(2の場合を除く)は、後の贈与にかかる受贈者から順次、遺留分侵害額を負担します。
上記の順序は、時期が新しい処分であればあるほど遺留分を侵害する程度が大きくなるという解釈を念頭において設定されています。
遺留分侵害額の算定
遺留分侵害額は、下記の算定式により算出します。
遺留分侵害額 = 遺留分額 - 遺贈・特別受益額 - 遺留分権利者の法定相続分による遺産額 + 遺留分権利者承継債務額
公正証書遺言がある場合の遺留分の請求について
遺留分についての知識を深めたところで、次は公正証書遺言がある場合の遺留分請求の方法について解説していきます。
公正証書遺言とは
普通方式の遺言の方法は3種類ありますが、そのうち主に使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。遺言は一定の方式に従っていない場合は無効となってしまう可能性がありますが、「公正証書遺言」は公証人の立会いのもと行われるため、有効性の認められやすい遺言の方式といえます。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもと行われます。遺言者は、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせます。遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名押印し、公証人は、方式に従って作成された旨を付記して署名押印します。この手続を経て公正証書遺言は成立します。なお、公正証書遺言の場合は、検認(遺言書を家庭裁判所に提出して承認を受ける手続)が不要です。
公正証書遺言の効力が有効でも侵害分の遺留分請求は可能
有効である公正証書遺言に遺留分を侵害する内容が記載されていた場合でも、遺留分侵害額請求は可能です。遺言の方式にかかわらず、遺留分請求は可能です。遺留分制度は、冒頭にも記載したとおり、相続人の生活の安定や、家族財産の公平な分配のために、相続人を救済する制度だからです。
公正証書遺言がある場合の遺留分請求手続の進め方
遺留分侵害額請求権は、形成権(権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生・消滅させる権利)と解されています。そのため、受贈者または受遺者に対する具体的な金銭支払請求権は、遺留分侵害額請求権を行使して初めて発生します。
請求の方法は法定されていませんが、配達証明付き内容証明郵便で請求するのがおすすめです。なぜならば、「請求日」が分かり、「相手に到達したことの証明」ができるからです。請求書には、請求する人の氏名、請求相手の氏名、請求の対象となる遺贈・贈与・遺言の内容、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨、請求する日時を記載しましょう。相手方との協議が定まったら合意書を取り交わし、遺留分侵害額を返還してもらいます。
請求に応じない場合
内容証明郵便を送付しても合意に至らず、遺留分侵害額の返還がなされない場合は、調停や訴訟での解決を試みます。これによって請求訴訟では、和解でも判決でも強制執行が可能となるため、相手の財産を差押さえることも可能となります。
注意点
注意すべき点は、遺留分侵害額請求には時効があるということです。遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に請求権を行使しないと、請求ができなくなってしまいます。また、除斥期間は相続開始時から10年で、どちらか早い方の時期に請求権は消滅します。加えて、遺留分侵害額請求により発生した金銭債権の消滅時効は5年と定められています。そのため、公正証書遺言の内容に異議を唱えたいときは、なるべく早めに請求権を行使するようにし、請求に応じてくれない場合には時効が完成する前に金銭の支払いを求める訴訟を提起する必要がある点、留意しましょう。
公正証書遺言を作成する際のポイント
上記では遺留分請求をする相続人の立場から解説をしてきました。しかし、相続人に遺留分請求という法的手続を実行させる手間や、受遺者・受贈者との無用なトラブルを避けるためにも、自分自身が被相続人の立場に立った場合にどのように公正証書遺言を作成するかについて、解説いたします。
生前に相続人全員の同意を得る
まず一つ目は、公正証書遺言の内容についてあらかじめ相続人の同意を得ておくことです。遺留分は形成権であるため、行使しない限りは公正証書遺言の内容のとおりに財産が承継されます。相続人の理解をあらかじめ得ておくことで、相続人自身も納得し、さらに自身の意思が反映された形で承継させることが可能となります。
遺留分を侵害しない内容で作成する
二つ目は、遺留分を侵害しない内容で公正証書遺言を作成することです。重ねての説明となりますが、公正証書遺言が有効だからといって、遺留分請求があった場合には全て遺言の内容のとおりに財産が承継されるわけではありません。自身の本意に背く内容となってしまうかもしれませんが、相続人等のトラブルを防ぐための選択肢の一つといえます。
遺留分侵害請求に備えて生命保険で資金を準備しておく
遺留分を侵害しない内容で公正証書遺言を作成することが形式上も内容的にも良いですが、どうしても財産を承継させたくない相続人がいるという場合もあるかもしれません。そのときは、被相続人を被保険者とし、相続させたい相続人を受取人として生命保険を契約するなどの方法も考えられます。遺留分権利者からの遺留分侵害額請求があった場合には、生命保険金から遺留分を支払うことが可能です。生命保険金は、遺産総額から見てよほど過大でない限り、原則として遺留分計算の対象から外れるからです。
遺留分の放棄をしてもらう
四つ目は、遺留分の放棄をしてもらうことです。家庭裁判所の許可を要件として、相続開始前(被相続人の生存中)に相続人は遺留分放棄が可能です。しかし、無理やり放棄させられるといった事態を避ける必要があります。そのため、相続人の意思に基づくということ以外にも、遺留分放棄に合理的な理由・必要性、遺留分放棄の見返りがあることが家庭裁判所の許可の要件となる点に注意してください。
相続人から廃除する
財産を承継させたくないという理由にはさまざまあると思いますが、例えばその理由が、その者から虐待を受けた、重大な侮辱を加えられた、著しい非行があった等であれば、その者を相続人から廃除することが可能です。廃除とは、そのような事由がある場合に被相続人の意思・感情を尊重するため、家庭裁判所が審判または調停によってその者の相続権を剥奪する制度です。廃除された相続人は相続権を失うため、遺留分を請求することはできなくなります。この効果は非常に大きいため、廃除原因は厳格に解される点には注意する必要があります。
付言する
最後に、これは法的な効果を生じさせるものではありませんが、遺言書の最後に付言を書き添えることも考えられます。なぜそのような内容の公正証書遺言を作成したのか、相続人へのメッセージを書き添えることで、遺留分請求を抑止できることもあると思います。
まとめ
公正証書遺言が有効であったとしても、遺留分侵害額請求は可能です。自身が遺留分侵害額請求をする場合、その侵害額の算定は決して簡単なものではありません。また、請求できる期間にも注意する必要があるため、弁護士への相談を検討することをおすすめいたします。また、自身が遺言を遺す立場としては、遺留分請求やそれにまつわるトラブルを生じさせないためにも、この制度を理解したうえで対策をし、公正証書遺言を作成しましょう。
お困りではありませんか?