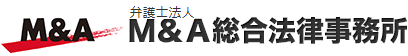相続した不動産の評価額とは?評価方法や流れ、税金を減額する方法、税法上の不動産価格と民法上の不動産価格との違いをわかりやすく解説

相続した不動産の評価額(税法上の不動産価格)を把握することは、相続税の計算や遺産分割を行う上で非常に重要です。しかし、相続した不動産の評価方法にはいくつかの種類があり、それぞれの方法によって評価額(税法上の不動産価格)が異なることがあります。
この記事では、相続した不動産の評価額(税法上の不動産価格)について詳しく解説し、民法上の不動産価格との違い、評価方法やその流れ、そして税金を減額するための方法についても紹介します。不動産の相続に関する基本的な知識を身につけて相続手続きをスムーズに進め、相続税の負担を軽減するための対策を講じましょう。
相続した不動産の評価額とは
土地や建物などの不動産を相続した際には、相続税が課されることがあります。この相続税を算出するためには、相続した不動産の評価額(相続税評価額(税法上の不動産価格))を知る必要があります。
相続税評価額(税法上の不動産価格)とは、法律で定められた評価方法に基づいて計算された財産の価値で、相続税や贈与税を計算する際の基準となるものです。
ただし、相続した財産の合計が基礎控除額を下回った場合、相続税は発生せず、申告する必要もありません。
基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人数)」で計算します。不動産は物理的な分割は不可能なので、相続人間で不動産を分割する際には、相続税評価額(税法上の不動産価格)を算出してから分割するのが一般的です。
相続した不動産の評価方法
相続した不動産の評価方法は、土地と建物で異なる計算方法を取ります。たとえ被相続人が所有する土地に同じく被相続人が所有する家が建っていたとしても、それぞれ別々に評価しなければなりません。
この章では、それぞれの評価方法について詳しく説明します。
土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)の算出方法
土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)を算出する方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。それぞれの算出方法を順番に解説します。
路線価方式
路線価方式とは、相続した宅地が面している道路に設定された路線価を基に評価する方法です。路線価方式での相続税評価額(税法上の不動産価格)の計算式は以下のとおりです。
- 路線価×補正率×土地の面積
路線価とは、その道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額を千円単位で表示したもので、毎年国税庁から公表されます。国税庁の路線価図や倍率表で確認できます。
路線価は、地価公示価格の約8割程度で設定されています。なお、路線価が定められている地域は、主に市街地の道路ごとに地価の差が見られる場所です。
補正率とは、路線価に対して個別の土地の状況を反映させるための調整係数です。具体的には、土地の形状や利用状況、周辺環境などを考慮して路線価に調整を加えます。補正率を適用することで、より現実に即した評価額(税法上の不動産価格)を得ることができます。
例えば、路線価が5万円、補正率が0.95、土地の面積が100㎡の場合、土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)は以下のように計算されます。
- 5万円×0.95×100㎡=475万円
倍率方式
倍率方式は、路線価が設定されていない地域の土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)を計算する方法です。都市部では路線価方式で評価されることが多いですが、地方の郡部地域や市街化調整区域(無秩序な市街化を防ぐための区域)では路線価が設定されていないため、倍率方式が用いられます。
倍率方式では、相続した宅地の基準年度(3年ごとに評価替えされる)の固定資産税評価額に倍率を掛けて土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)を計算します。固定資産税評価額は、納税通知書に同封されるか、同時期に送付される固定資産税課税明細書に記載されています。自治体によって送付時期は異なりますが、一般的には4月から6月頃です。固定資産税課税明細書は再発行できないため、届いたら大切に保管しましょう。
倍率方式では以下の計算式を用います。
- 固定資産税評価額×評価倍率
倍率は土地ごとに異なるため、国税庁のウェブサイトで確認しましょう。たとえば、固定資産税評価額が800万円で評価倍率が1.3の場合、土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)は以下のように計算されます。
- 800万円×1.3=1,040万円
建物の相続税評価額(税法上の不動産価格)の算出方法
建物の相続税評価額(税法上の不動産価格)は、家屋の使用形態によって変わりますが、居住用や事業用の建物は「基準年度の固定資産税評価額×1.0」で計算します。
建物の固定資産税評価額は新築時に一度役所で評価され、その後3年ごとに評価替えが行われ、経年減価などが反映されて減額されます。新築時の評価額(税法上の不動産価格)は、実際の建築費の約60%程度であることが多いとされています。
相続した土地の評価の流れ
ここまでの説明を踏まえて、本章では相続した土地の評価を行う流れを以下の2つのステップに沿って紹介します。
- 路線価地域なのか倍率地域なのかチェックする
- 評価額(税法上の不動産価格)の減額要件を満たしているかチェックする
それぞれのステップで行うべきことを中心に順番に解説します。
路線価地域なのか倍率地域なのかチェックする
まずは、相続した土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかチェックしてください。路線価図があれば路線価地域、路線価図がなければ倍率地域です。
路線価図の有無は、国税庁のHPを用いて、以下の手順で調べられます。
- 国税庁HPにアクセスする
- 相続開始日の属する年度のタブをクリックする
- 対象の土地がある都道府県をクリックする
- 路線価図をクリックする
- 対象の市区町村をクリックする
- 地名(町又は大字)を探す
- 路線価図から対象地を見つける
その後、路線価地域にある土地の場合は路線価方式を用いて、倍率地域にある土地の場合は倍率方式を用いて相続税評価額(税法上の不動産価格)を算出します。
評価額(税法上の不動産価格)の減額要件を満たしているかチェックする
所定の要件を満たすことで、相続した土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)を減額できる場合があります。
例えば、借地権が設定されている土地の場合、相続税評価額(税法上の不動産価格)が低くなります。借地権とは、第三者が土地を借りてその土地に建物を建てる権利のことです。
借地権が設定されている土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)は、次の計算式で算出されます。
- 自用地の価額×(1−借地権割合)
なお、借地権割合は地域によって異なり、30~90%の範囲で設定されています。自用地とは、自分が所有する土地のことを指します。
また、貸家建付地の場合も、相続税評価額(税法上の不動産価格)が低くなります。貸家建付地とは、第三者に貸すための自用地のことで、賃貸物件(一戸建て、アパート、テナントビルなど)が建っている土地のことです。貸家建付地は自由に売却や更地にできないため、自用地としての相続税評価額(税法上の不動産価格)が低く抑えられます。
貸家建付地の相続税評価額(税法上の不動産価格)は、次の計算式で求められます。
- 自用地の価額-(自用地の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
借地権割合および借家権割合は地域によって異なり、路線価図や評価倍率表で確認できます。賃貸割合は、「賃貸されている部屋の専有面積の合計÷賃貸物件の専有面積の合計」で算出されます。
その他、以下のような条件に該当する土地の場合、相続税評価額(税法上の不動産価格)が低くなる可能性があります。
- 奥行が長い土地
- 不整形地
- 前面道路の幅員が4mに満たない土地
- 道路に面していない土地
- 地積規模が大きい土地
- 接道義務を満たしていない土地
- 線路や踏切に隣接している土地
- 墓地隣接地
- がけ地等を有する土地
上記のような土地の場合、その土地に応じた補正率を掛けて調整できるため、相続税評価額(税法上の不動産価格)が低くなることがあります。
ただし、相続した土地の相続税評価額(税法上の不動産価格)を減額できるかどうかの判定は非常に複雑です。正しく判断して相続税評価額(税法上の不動産価格)を算出するためには、専門的な知識が必要になりますので、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
相続した建物の評価の流れ
相続した建物の評価を行う流れを以下の2つのステップに沿って紹介します。
- 固定資産税評価額をチェックする
- 評価額(税法上の不動産価格)の減額要件を満たしているかチェックする
それぞれのステップで行うべきことを中心に順番に解説します。
固定資産税評価額をチェックする
まずは、相続した建物の固定資産税評価額を確認しましょう。
建物の相続税評価額(税法上の不動産価格)は、以下の計算式で求められます。この計算式から分かるように、相続税における建物の評価額(税法上の不動産価格)は基本的に固定資産税評価額と同じです。
- 固定資産税評価額×評価倍率(1.0)
建物の固定資産税評価額は、毎年4月頃に送付される固定資産税課税明細書(納税通知書)に記載されています。なお、令和6年1月1日以後に相続または贈与により取得した分譲マンションについては、評価方法が改正されているためご注意ください。
評価額(税法上の不動産価格)の減額要件を満たしているかチェックする
次に、相続した建物が評価額(税法上の不動産価格)の減額要件を満たしているかチェックしましょう。具体的に言うと、相続した建物が賃貸されているかどうか確認してください。
賃貸があった場合、以下の計算式で相続税評価額(税法上の不動産価格)を減額できます。
| ケース | 計算式 |
| 1軒(1棟)全部貸家のケース | 固定資産税評価額×(1-借家権割合) |
| 住宅の一部が貸家のケース | 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) |
※借家権割合は、一律30%
※賃貸割合は、建物の各独立部分の床面積の合計に対する賃貸部分の床面積の合計
相続した不動産にかかる税金を軽減できる制度
相続した不動産にかかる税金を軽減できる制度として、以下の3つを取り上げます。
- 小規模宅地等の特例
- 空き家特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
これら3つの制度の概要を順番に解説します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の条件に当てはまる小規模宅地における相続税評価額(税法上の不動産価格)を最大で80%減額できる特例です。
自宅や事業などで使用している土地を相続する相続人が満額の相続税を払うと、負担が大きくなってしまい、土地を手放すことを選択するケースが多いです。そこで本制度は、相続人が土地を手放すことを防ぐ目的で設けられました。
小規模宅地等の特例を利用することで、大きな節税効果が得られ、相続人が土地を維持しやすくなります。本制度を利用できる土地の条件は以下のとおりです。
- 被相続人等の居住の用に供されていた宅地
- 事業用の宅地
- 貸付事業用の宅地
小規模宅地等の特例では、限度面積や減額割合が下表の通り決まっています。
| 相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額割合 | ||
| 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ①特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
| 貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等 | ②特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
| ③貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |||
| 一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | ④貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
| 被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ⑤貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
| 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330㎡ | 80% | ||
例えば、居住用宅地の相続税評価額(税法上の不動産価格)が3億円、土地面積が250㎡という場合、小規模宅地等の特例で減額できる相続税評価額(税法上の不動産価格)は、以下のように計算できます。
- 2億円×80%=1億6,000万円
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
空き家特例
空き家特例とは、正式名称を「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」とする制度で、空き家の発生を抑制するために設けられた特例措置です。
相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却し、定められた要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
譲渡所得の金額は、下記の計算式の通りです。土地や建物を売った譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算し、所得を基準に税額が決まるため、特別控除が使える場合は節税になります。
- 譲渡取得=譲渡価格(収入金額)−必要経費(取得費+譲渡費用)−特別控除額
取得費は、不動産の購入代金や、購入手数料などに、その後支払った改良費などを加えた合計額のことです。建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を引いて計算します。
また、譲渡費用とは、不動産を売却するために支出した費用のことです。仲介手数料や測量費などが該当します。
参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは、相続税を支払って取得した土地・建物などの財産を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算(取得費加算)できるという制度です。
そもそも土地や建物などの不動産を売却して譲渡所得を得たときは、確定申告を行い、必要に応じて所得税や住民税を納めなければなりません。譲渡所得を計算する際は、財産の売却で得た対価の額(収入金額)から、財産を取得するためにかかった費用を差し引きます。
取得費加算の特例を適用すると、相続税額をもとに計算した一定金額を取得費に加えられます。その結果、譲渡所得金額が減り、税負担を抑えられるという仕組みです。
参考:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
不動産の評価額(税法上の不動産価格)が遺産分割協議にもたらす影響
相続した不動産の評価額(税法上の不動産価格)は、相続税の計算に重要な役割を果たすだけでなく、遺産分割協議にも影響を与えます。遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、遺産の分配方法について話し合うプロセスです。
不動産の相続税評価額(税法上の不動産価格)は、実際の取引価格(実勢価格(民法上の不動産価格))の約8割程度の額として決定されます。不動産を相続したいと考えている相続人にとっては、不動産の評価額(税法上の不動産価格)が低いほど有利になるため、遺産分割協議では「相続税評価額(税法上の不動産価格)をそのまま使いたい」と主張することが予想されます。
一方で、不動産を相続しない相続人にとっては、不動産の評価額(税法上の不動産価格)が高いほど有利になるため、遺産分割協議では「実勢価格(民法上の不動産価格)で評価するべきだ」と主張する傾向があります。
相続税評価額(税法上の不動産価格)を用いた場合の事例
ここからは、親が死亡して長男と次男の2人が相続人となるケースを例に、不動産の評価額(税法上の不動産価格)が遺産分割協議にもたらす影響について考えていきます。
遺産は実家の土地建物(長男夫婦が同居していたもので、相続税評価額(税法上の不動産価格)は2,000万円)と、預貯金4,000万円だったとします。この場合、相続税申告での遺産総額は合計で6,000万円になります。
上記のケースにおける遺産分割協議で長男が遺産の不動産を取得したいと考えており、相続税評価額(税法上の不動産価格)を用いたいという場合、次男に対して以下のような提案をすることが想定されます。
- 税理士作成の遺産目録で遺産総額は6,000万円
- 相続分は各2分の1なので3,000万円ずつ
- 実家の土地建物は自分が相続してそのまま住み続けるので、預貯金は1,000万円だけ相続する
- 次男は預貯金3,000万円を相続すれば良い
もし上記の提案に次男が同意すれば、遺産分割協議は成立します。
実勢価格を用いた場合の事例
長男の提案に対して、次男が遺産に含まれる不動産を取得せず、実勢価格(民法上の不動産価格)を用いたいという場合には、以下のような主張をすることが想定されます。
- 実家の土地建物の実勢価格は、2,500万円(=2,000万円÷0.8)程度となるはず
- そうなると遺産の総額は6,500万円になり、2分の1だと3,250万円ずつ
- 長男が実家の土地建物を相続するなら、預貯金における長男の相続分は750万円(=3,250万円-2,500万円)となる
- なので、預貯金の自分の相続分は3,250万円(=4,000万円-750万円)となる
裁判所は実勢価格(民法上の不動産価格)で判断
不動産の評価額(民法上の不動産価格)について相続人の間で合意できれば問題ありませんが、合意できない場合には家庭裁判所での調停を経て、最終的には審判で決定されます。この際、裁判所は遺産に含まれる不動産を遺産分割時の実勢価格(民法上の不動産価格)で判断します。
実勢価格(民法上の不動産価格)については、遺産分割の話し合いや調停、審判の場面で、根拠資料に基づいて議論することになります。
最も確実な根拠資料は不動産鑑定士の鑑定書ですが、鑑定書の作成には多くの費用がかかります。そのため、不動産業者に無料で作成してもらった簡易査定書を代用することもあります。
相続した不動産の評価額(税法上の不動産価格)まとめ
相続した不動産の評価額(税法上の不動産価格)は、相続税の計算や遺産分割協議において重要な役割を果たします。評価額(税法上の不動産価格)の算出にはいくつかの方法があり、路線価方式や倍率方式などがあります。それぞれの方法には特徴があり、状況に応じて適切な方法を選びましょう。
相続税を減額するためには、評価額(税法上の不動産価格)を適正に見積もることが第一歩です。そのためには、専門家の助言を受けながら、慎重に評価方法を選定し、正確な評価額(税法上の不動産価格)を算出することが重要です。さらに、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの税制優遇措置を活用することで、相続税の負担をさらに軽減することも可能です。