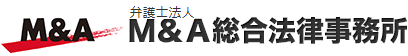不動産を遺産分割する方法とは?相続が発生した時の流れや手続きをわかりやすく解説

不動産を遺産分割する方法とは
配偶者や血縁のある親族が亡くなると、相続が発生することがあります。しかし、このようなことは、頻繁に発生するようなことではないので、その際にやるべきことは、あまり知られていません。
国税庁の発表によると、相続税が発生した相続財産の約40%が土地や家屋の不動産です。相続財産が現金などの場合には、相続人の間で分配するのも分割しやすく容易ですが、土地や家屋の不動産の場合、物理的に相続人の持分に分割するのが困難な場合がほとんどです。
このような場合にどのように遺産分割をする方法があるのか?どのような準備をしておけばいいのか?手続きはどのようなことをしなければならないのか?ということなどを知っておけば、いざという場合に慌てなくてすみます。
今回は、これらのことが理解できるように、不動産を遺産分割する方法などについて、わかりやすく解説していこうと思います。
不動産の遺産相続の方法とそれぞれのメリット、デメリット
相続人が複数人いる場合に、遺産の不動産をどのように遺産分割して相続するのかは、とても難しい問題です。土地や建物などの不動産は、物理的に一体として存在することがほとんどなので、現金のように容易に分割できないという特徴があります。
相続される土地や建物が都合よく、複数人いる相続人の相続割合に適切に分割できる場合はほとんどありません。
よって、実際には、相続が発生した場合、土地や建物などの不動産を分割する方法として「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有」の4つの方法が行われています。それぞれ、メリットやデメリットがありますので、1つずつ解説していきます。
現物分割
現物分割は、共有しているものを物理的に分割する方法です。メリットとしては、単純で分かりやすく明快だということです。相続人が複数人いる相続で現物分割する場合は、その相続割合に応じて、相続される土地や建物を分割します。
現物分割が可能な場合には、分割するための複雑な手続きも要さず、相続割合に応じて分割されるので、相続人間で争いが起こる可能性も低いです。
しかし、実際上は、土地や建物などの不動産が相続財産の場合、それを相続割合に応じて分割することは、困難な場合がほとんどです。
例えば1つの土地家屋を妻と2人の子供で法定相続分に応じて分ける場合、妻に半分、2人の子供は4分の1ずつ相続することになります。しかし、実際には1つの土地家屋を物理的に妻に半分、2人の子供に4分の1ずつ分けるというのは困難であることは容易に想像がつきます。
金銭のように、法定相続分などに応じて容易に分割できる場合には、現物分割は単純明快で公平ですが、土地建物などの不動産の場合、相続人が複数人いる場合には、物理的に分割すること自体が困難です。これが、土地や建物の不動産を現物分割することの最も大きなデメリットです。
さらに、相続財産の不動産が土地だけで、物理的に分割が可能な場合であっても、相続人が多数いる場合などには、細かく分割されることによって、著しくその価値が下がったり、用途が限られてしまったりすることが多いというのもデメリットと言えます。
代償分割
代償分割は、複数の相続人のうち1人が土地や建物の不動産など相続の対象物を受け取り、相続対象物を受け取った相続人が、他の相続人にそれぞれの相続割合に応じた対価となる代償金を支払う方法です。
代償分割は、相続人の中に現金が欲しい人がいる場合に有効です。また、不動産の評価額が合意できれば、相続割合に応じた分配ができるということもメリットということができます。
さらに、相続対象物となる不動産にすでに住んでいる相続人がいる場合などには、その相続人がそのまま居住を継続できるというメリットもあります。
一方で、不動産の価格の算定には、後述のとおり、いろいろな方法があることから、相続対象物である不動産の価格の評価で意見が分かれ、代償金の額を巡って争いになりやすいというデメリットがあります。
また、相続対象物を受け取る相続人が、他の相続人に対して代償金となる現金を用意できない場合、この方法を取ることは困難であるというのもデメリットです。
換価分割
換価分割は、相続の対象物を売却し、その売却代金を相続人に分配する方法です。土地や建物などの不動産の場合には、その不動産を売却して得た現金を相続人に分配することになります。
相続対象物である不動産を実際に売却し、現金に換えて、それを分配することから、売却額の分配割合についての争いが起こる可能性が極めて低いことがメリットと言えます。
一方で、各相続人が相続できる金額は不動産の売却額に左右されるため、売却当時の経済状況や不動産売買状況によって、想定した相続額が受け取れない可能性があるというのはデメリットと考えられます。
また、相続した相続人全員に譲渡取得税という所得税や住民税などの税金が課せられる可能性があるというのもデメリットです。
共有
共有はこれまで見てきた3つの方法と違って、分割しないという方法です。「現物分割」「代償分割」「換価分割」はいずれも何らかの方法によって相続の対象物である不動産を、相続人に分割していましたが、共有という手段を取る場合は、分割自体をしないということになります。
共有という方法を取る場合、複数人いる相続人の相続割合に応じて持分を定めて、それに応じて相続の対象である不動産を所有することになります。
共有のメリットは、相続の対象物である不動産を相続した段階では、持分割合が決まるだけなので、分割することによる争いが起こる余地がないということです。上記のとおり、不動産に対し持分だけが決まって、実際に不動産が分割されることはないので、問題が起こりにくいです。
しかし、一方で持分の違いがあったとしても、対象の土地建物の不動産に対して全相続人が所有者ということになるので、相続した不動産を賃貸するとか、売却する場合など、相続した不動産について何かを決める際に、共有者全員の同意が必要となります。
このような場合に、その都度協議が必要で、意見が合わない、連絡が取れない、合意に時間がかかるなどのトラブルが発生する可能性があるというのがデメリットです。
また、共有を繰り返して相続をすると、どんどん相続の対象となる不動産の所有者が細分化していって、ますますその後の分割や不動産の扱いについての合意がとりにくくなるということも考えられます。
不動産価値の評価方法
これまで見てきたとおり、相続の対象物となる不動産が複数人の相続人に相続される場合、4つの方法がありました。その中でも、代償分割や換価分割の場合には、相続される不動産の価値の評価方法が非常に重要になってきます。
なぜなら、その評価によって、現金を受け取る相続人の受け取り額が決まるからです。換価分割の場合は、実際に相続の対象となる不動産を売却して分割するので、評価額については問題にならないかもしれません。
しかし、特に代償分割の場合には、実際には相続の対象となる不動産を売却しないので、その評価方法や評価額で争いになることがよくあります。
不動産を受け取る相続人はその不動産の評価額を低くして、他の相続人に支払う現金を少なくしたい、逆に現金を受け取る相続人は、できるだけ不動産の評価額を高くして現金を少しでも多くもらいたいというのが一般です。
ここでは、不動産の評価方法と実際に遺産分割で採用される評価方法について説明します。
相続税評価額
相続税評価額は、相続税や贈与税を申告する時に基準となる評価額のことです。固定資産税のように、役所が通知してくるものではなく、納税者自らが計算しなければなりません。
一方で、納税者自らが計算しなければならないからといって、その計算方法がバラバラだと納税者間の公平性に欠けます。よって、実際には、「路線価方式」「倍率方式」のいずれかの方法によって計算されます。
主に市街地の宅地の算定では「路線価方式」、それ以外の不動産の算定では「倍率方式」が用いられます。
「路線価方式」は、評価の対象になる土地に隣接する路線(道路)に付けられている路線価に、土地の面積を乗じて評価する方法です。
路線(道路)ごとの路線価は、国税庁ホームページで見ることができる路線価図に掲載されていて、国税庁から毎年7月にその年のものが公表されます。「路線価方式」での算定をする場合、相続税の申告では被相続人が亡くなった年のものを使います
次に「倍率方式」は固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法です。固定資産税に乗じる倍率は、毎年国税庁が決定して公表します。
「路線価方式」でも「倍率方式」でも、相続税評価額は、一般的に、実勢価格よりも安い金額になります。
実勢価格
実勢価格は、実際に不動産を売買する際にどれぐらいの価格になるかを想定して算出される価格です。つまり、売り手と買い手の需要と供給の釣り合う価格ということができます。
実際には、直近の周辺の不動産の実際の取引価格を参考にして算出されることになります。また、それぞれの土地の周囲の環境や特性によっても価格が変わります。
公示価格
公示価格は、一般の人が土地の取引や資産評価をする際の価格の客観的な目安とするために、国土交通省が毎年発表している価格です。全国の特定の26,000地点について、1月1日時点での平米単価が公表されています。
公示価格はあくまで一般の土地取引や資産評価のための目安の価格であるため、同じ標準地の周辺の土地であっても、実際の個別の取引価格は、需要の多さや周囲の環境などによって違ってきます。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、不動産を所有していると課税される固定資産税を決める際の基準になる不動産の評価額のことです。「固定資産評価基準」という、土地や建物などをそれぞれどう評価するかを定めた基準に基づいて、各市町村(東京23区は都)が評価額を個別に決めます。
不動産の遺産分割で採用される評価方法
これまで見てきたとおり、不動産の評価方法は、それぞれ評価の目的に応じていくつかあります。そこで、不動産の遺産分割に際してどの評価方法を取るかということが問題になります。
不動産を受け取る相続人はその不動産の評価額を低くして、他の相続人に支払う現金を少なくしたいため、最も評価額が低くなる方法を選択したいと考え、逆に現金を受け取る相続人は、できるだけ不動産の評価額が高くなる方法を選択して現金を少しでも多くもらいたいということになります。
一般的には、遺産の不動産を受け取る相続人は相続税評価額での評価を望み、現金を受け取る相続人は実勢価格を望むという傾向があります。
相続される不動産の評価について、相続人間で合意ができれば問題はありません。しかし、合意ができない場合、家庭裁判所の調停、それでもまとまらない場合には審判が下されます。
裁判所の審判では、実勢価格での評価がされる傾向にあります。このことから、相続人間で合意できない場合でも、最終的には実勢価格で評価されることを前提として協議が進められることになります。
遺産分割する不動産の種類と注意点
遺産分割する不動産には、土地だけの場合もあれば、一戸建てやマンションなど、いくつかのパターンがあります。不動産の種類によって、遺産分割して相続する際の特徴や注意点がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
また、不動産の評価の違いを考慮した相続対策も注意点として知っているのといないのとでは大きな差ができることもありますので、この点もご紹介しようと思います。
土地のみの場合
土地のみの場合で、代償分割や換価分割をする場合、遺産相続が発生した時と、実際に分割する時とで価格が大きく変わる可能性があります。このようなことも踏まえ、遺産分割協議では、将来の価格変動も見据えながら分割協議をする必要があります。
また、田舎の土地などが遺産分割する対象の場合、必ず売却できるとは限らないという点も注意が必要です。
一戸建ての場合
相続される遺産の不動産が一戸建ての場合、相続人の誰も遺産の一戸建てに住まないままで、放置をされていると、「特定空家」に指定される可能性があります。「特定空家」に指定されると、誰かが住んでいる一戸建てと比較して約6倍の固定資産税が課税されることになります。
このような事態を避けるためには、早急に売却するなどして、換価分割をするか、相続人の誰かが遺産の不動産に住んで代償分割をする、しばらく共有状態を継続するのであれば、賃貸をするなどの措置を取る必要があります。
マンションなどの共同住宅の場合
マンションなどの共同住宅の場合、相続人の誰かが住まないのであれば、遺産分割協議をして相続分が確定するまでは、賃貸して家賃収入を得るということでそのままの状態を維持しながら収益を出すことも可能です。
しかし、物件が古いなどの場合、借り手が見つからなかったり、維持費や管理費がかさばったりすることがあるという点で注意が必要です。
不動産価格の評価方法を考慮した相続対策
前述のとおり、不動産価格には、「相続税評価額」、「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」があります。このうち相続の際に関係してくることが多いのが「相続税評価額」と「実勢価格」です。この「相続税評価額」と「実勢価格」の差を考慮すると、効果的な相続対策をすることも考えられます。
例えば、都会の不動産の場合、一般的に「実勢価格」が「相続税評価額」に比べて非常に高い傾向にあります。相続財産となる資産に都会の不動産がある場合、そのまま不動産として相続されると、相続税としては、「実勢価格」よりもかなり低い「相続税評価額」を基にして算定されるため、同じ不動産を「実勢価格」で売却したのちに、現金として相続するよりも節税になります。
また、この節税対策をさらに積極的に利用して、相続財産となる資産に多額の現金がある場合には、都会の不動産を「実勢価格」で購入し、「実勢価格」よりもはるかに安い「相続税評価額」で算定された相続税を支払ったのち、「実勢価格」で売却して現金を相続するという方法を取ることも可能です。
一方で、相続財産となる資産に地方の不動産がある場合、「実勢価格」が「相続税評価額」よりも安い場合があります。このような場合には、都会の不動産と逆に実際の不動産の「実勢価格」よりも「相続税評価額」が高いために、実際の価格で算定した額よりも高い相続税が課せられることになり、結果、相続税が支払うことができず、自己破産をする場合さえあり得ます。
このような場合には、相続が起こる前に不動産を売却して現金に換えておき、そのうえで相続税を支払う方が経済的には有利になります。
さらに進んで、「実勢価格」よりも「相続税評価額」の方が高い地方の不動産が相続財産にある場合には、地方の不動産を売却して現金に換え、その現金で都会の不動産を購入しておくのが経済的には最も有利だと言えます。
ただ、いわゆるタワマン節税のように、あまりに節税額が高額かつその手法が露骨な場合には、税負担の公平性の観点から、裁判でも否認された事例もありますので、その点は注意が必要です。
不動産相続の手続きや流れ
不動産の遺産相続が発生した場合に、どのような手続きが必要かということを理解しておくことは、いざ、相続が起こったときに、慌てずに着実に不動産の遺産相続を進めるためには重要です。
知らずに進めてしまうと、相続人の間で不要な争いごとが起こったり、協議がまとまらず手戻りが発生したりする可能性があります。
ここでは、不動産相続の手続きや流れを見ていきます。
遺言書の有無の確認
相続が発生した場合、最初にするべきことは、亡くなった被相続人の遺言書があるかどうかの確認です。残された遺産はそもそも被相続人のものですから、その遺産を誰にどれだけ相続させたいかという被相続人の意思が尊重されます。
このため、相続が発生した時は、まず被相続人の遺言書の有無を確認します。遺言書の確認をせず、相続人の間で遺産分割協議がまとまったとしても、その後に適法な遺言書が見つかれば、すべてやり直しになってしまいます。
遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があり、被相続人本人が保管していた「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、検認という家庭裁判所での遺言書の内容や状態を確認する作業が必要となります。法務局で保管されていた「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」には検認作業は必要ありません。
相続人の確認
相続が始まり、遺言書の有無の確認をした後、次は誰が法定相続人なのかを確認する必要があります。死亡した被相続人の法定相続人を正確に把握するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認しなければなりません。
被相続人の元配偶者との子供や認知した子供なども法定相続人となりますので、このような人たちすべてを確認するためには、被相続人が亡くなった時点の戸籍だけではなく、被相続人に関係する戸籍謄本を取り寄せてすべて確認する必要があります。
戸籍は転居や婚姻などによって転籍することがあります。よって、すべての戸籍を取り寄せるためには、まず、被相続人の死亡した戸籍謄本から過去に遡っていく必要があります。
その取り寄せた戸籍をすべて確認することによって、被相続人の法定相続人を確定させることができます。
相続財産の確認
次に、被相続人が死亡した時にどれだけの財産があったのか、すなわち、相続財産の確認をする必要があります。これを一般的には相続財産調査といい、紛争が想定されるような場合には、弁護士など専門家に依頼することも考えなければなりません。
不動産の相続財産については、被相続人宛に届いていた固定資産税明細書や、被相続人の遺産の不動産が存在する市町村で入手できる被相続人名義の固定資産評価証明書を取得することで、確認ができます。
遺産分割協議の実施
遺産分割協議は、相続人全員で被相続人の財産をどのように分配するのかを決める手続きです。
被相続人の遺言書の有無、相続人の確認、相続財産の確認ができれば、相続人全員の同意で被相続人の遺産を誰がどれだけ引き継ぐのかを決めます。その際に、作成されるのが遺産分割協議書です。
この相続人全員参加による遺産分割協議の合意によって、相続人それぞれに遺産が分配されることになります。
相続財産の名義変更
被相続人の遺産のうち、不動産を引き継ぐことに決まった相続人は、相続登記の手続きを行って不動産の名義変更を行います。
不動産は登記をすることでその所有者を公示することとなっており、相続によって正式な所有者となったことを世間一般に示すために登記の名義変更が必要になります。
相続税の申告・納付
相続が発生したことを知った日から10か月以内に、相続人は相続税の申告・納付を行わなければなりません。
仮に被相続人の遺産を誰がどれだけ相続するのかが決まっていない場合でも、相続税の納付が遅れれば、延滞税や加算税が課されます。
よって、遺産相続の協議がまとまらないような場合には、とりあえず法定相続割合に応じて法定相続人が相続税を負担しあい、のちに分割協議で清算するなどの方法が採られることもあります。
不動産相続に必要な書類
被相続人が亡くなって、不動産相続を行う際に必要となる書類は以下のものとなります。不動産相続を行う場合には、すべての書類が必要になります。
被相続人や相続人の中に住んでいる場所が遠いなど、取り寄せるための郵送などに時間を要することも想定されるので、できるだけ早期に集める必要があります。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まですべて)
- 被相続人の住民票の除票
- 遺言書もしくは遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
不動産相続にかかる費用
被相続人の不動産を相続する場合には、様々な費用がかかります。この点は、現金・預金を相続する際にかかる費用が、基本的には相続税だけなのとは違う点です。
遺産分割協議を行う際には、不動産相続には様々な費用がかかるということを考慮して合意しておく必要があります。
相続税
相続税は、被相続人の遺産を引き受ける相続人が納める税金です。基礎控除額を超える財産を相続する場合には相続税を納税する必要があります。
基礎控除額は、「3,000万円+(相続人の人数×600万円)」の計算式で算出されます。よって、例えば相続人が2人の場合には、「3,000万円+(2×600万円)=4,200万円」を超える財産が相続される場合には相続税が発生します。
相続税を算出する時の遺産の不動産の価値は、前述の不動産の評価方法のところで説明したとおり、相続税評価額で計算します。
登録免許税
不動産を相続した場合、登記の名義変更をする必要があります。この不動産の名義変更を行う際にかかってくるのが登録免許税です。
登録免許税は、「課税標準×税率」の計算式で算出されます。課税標準は、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書で知ることができます。
税率は、相続による登記の名義変更の場合は、1000分の4ですが、税制改正によって免税が受けられることもあるので、相続が発生した時点での税率と免税対象などを調べる必要があります。
不動産取得税
不動産取得税は、売買などによって不動産を取得した時に課税される国税です。基本的には、相続の場合には不動産取得税は課税されません。その理由は、相続による不動産所有者の変更は、売買や贈与と異なり、「形式的な所有権の移転」にすぎないと考えられているからです。
ただし、相続の場合でも「この不動産を誰々に」という具体的な形で特定の不動産の遺贈が遺言によって行われる、「特定遺贈」の場合のみ不動産取得税が課せられることになります。
その他の費用
被相続人の遺産である不動産を相続する場合、上記の費用の他にも費用がかかることが想定されます。
具体的には、登記の名義変更などを行うための住民票や戸籍謄本、登記事項証明書などの書類を取得するための費用や郵送代があります。
さらに、手続きを弁護士や司法書士に依頼するのであれば、その報酬も費用としてかかってくることになります。
生前贈与による不動産の譲渡
被相続人が亡くなったあと、配偶者や子供など相続人が遺産を受け継ぐことが相続です。一方、被相続人になる人が亡くなる前に相続人になる人にその財産を譲渡することを生前贈与と言います。
相続の場合には、円滑に財産を引き継ぐためには、遺産分割協議や相続税の納税など、様々な手続きを比較的短期間で行う必要があります。
一方で、生前贈与の場合には、比較的長期間で計画的に財産を引き継ぐことができるというメリットがあります。特に基礎控除額を超えるような財産がある場合、長期にわたって免税の範囲内で徐々に財産を譲渡していく方が税金などの節約になる可能性があります。
不動産に関しては、夫婦間で住居用の不動産を贈与した場合の2000万円の配偶者控除や60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与した場合に、2,500万円までは贈与税が控除されるという制度を利用するということも有効な場合があります。
しかし、生前贈与をした後に、配偶者と離婚したり、子供が相続欠格にあたったり、相続人から排除したいと思っても、すでに贈与したものについては返還されることはないということについては注意が必要です。
まとめ
今回は、被相続人が亡くなった後の、特に不動産を遺産分割の方法について説明しました。これまで説明してきたとおり、不動産の遺産分割の際には、様々な書類を集めたり、手続きを行ったりする必要があります。
このため、あらかじめ必要な手続きについて理解し、相続が発生した場合にはできるだけ早く手続きを進めることが肝要です。正確かつ円満、迅速に不動産の遺産分割を進めるためには、弁護士などの専門家の下で遺産分割を進めるのも有効な方法だと言えます。