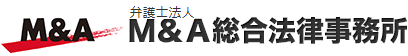賃貸物件を相続する流れとは?評価方法や遺産分割方法をわかりやすく解説

アパートやマンションなどの賃貸物件を所有している人が亡くなった場合、その賃貸物件は相続の対象となります。
賃貸物件を相続することになった場合、相続税などの税金や遺産分割などの問題で難しいイメージを持たれる方は多いと思われます。
この記事では、賃貸物件の相続について解説します。
相続する際の手続きの流れや必要書類、相続人が複数いる場合の遺産分割方法や相続したときにかかる税金などを詳しく説明するのでぜひ参考にしてください。
賃貸物件を相続するときの流れ
賃貸物件を相続するときの手続きの流れは以下のとおりです。
- 賃貸物件の残債務を確認する
- 賃貸物件の管理状況や修繕状況を確認する
- 賃貸物件の相続人を決定する
- 相続登記を行う
- 管理会社や保険会社の契約内容を変更する
- 相続税の申告と確定申告を行う
まずは、それぞれの手続きを詳しく解説していきます。
賃貸物件の残債務を確認する
賃貸物件を相続した場合、まずはその物件にローンなどの残債務がないかを確認します。
被相続人がマンションやアパートなどを現金で一括購入しているケースは少なく、多くの場合はローンを組んで物件を運用しています。
賃貸物件にローンが残っていた場合、相続人は、引き続き返済を継続していかなければなりません。
そのため、返済先の金融機関や毎月の支払金額、支払い期日などをあらかじめ確認しておく必要があるのです。
この時点で、賃貸物件の残債務が多すぎて、家賃収入を加味しても債務の返済が難しい場合は相続放棄を検討するとよいでしょう。
ただし相続放棄すると、ローンなどのマイナス財産だけでなくプラスの財産も放棄することになり、また放棄した遺産は二度と手に入れられなくなるため、慎重に検討する必要があります。
賃貸物件の管理状況や修繕状況を確認する
賃貸物件を相続したら、その物件の管理状況や修繕状況を確認しなければなりません。
賃貸物件の管理を管理会社に委託している場合は、毎月固定で管理手数料を支払わなければなりません。そのため、所有者が亡くなったことを管理会社に連絡し、毎月の管理費を把握する必要があります。
また原則、賃貸物件の修繕費用は所有者負担となります。仮に大規模な修繕の予定がある場合、相続人はその修繕費用を確保しておかなければならないため、早い段階で確認することをおすすめします。
賃貸物件の相続人を決定する
賃貸物件の状況を確認できたら、相続人を決定します。
亡くなった所有者が遺言書を残している場合は、その内容に従って相続人を決めます。
一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が賃貸物件を相続するかを相続人間で協議します。
また、単独相続にするのか、共有名義にするのか、共有名義であれば持分をどうするのか、なども遺産分割協議時に決定します。
後ほど詳しく説明しますが、遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあり、どの方法で相続するかも話し合います。
この段階で十分に協議しておかないと、後々相続トラブルになることがあるため、きちんと話し合い、他の相続人の納得を得ておくことが重要です。
相続登記を行う
遺言書や遺産分割協議などで相続人が決定したら、法務局で相続登記を行います。
不動産の所有者が亡くなった場合は、その不動産の登記名義人を相続人に変更する必要があります。
相続登記を怠ると「被相続人の名義のままで賃貸物件の売却や抵当権の設定ができない」などの後々不便が生じる可能性があるためです。
遺産分割協議が整ったら、忘れないうちになるべく早く手続きすることをおすすめします。
また、2024年4月より相続登記は義務化され、相続人が不動産を取得することを知った日から3年以内に登記手続きを行わなければなりません。
正当な理由なく相続登記を行わないと10万円の過料を課される可能性があるため、注意しましょう。
管理会社や保険会社の契約内容を変更する
賃貸物件の相続人が決定したら、火災保険や管理会社との契約の名義を相続人に変更します。
賃貸物件を所有している場合、保険会社や管理会社と契約していることがほとんどです。
そのため、保険会社や管理会社に連絡し、契約名義の変更手続きが必要となります。
特に火災保険に関しては、「名義人が被相続人のままであったために保証金を受け取れなかった」というトラブルを避けるためにも必ず名義変更を行うようにしましょう。
相続税の申告を行う
賃貸物件を相続すると、当然相続税が発生します。
そのため、相続税の申告の要否を確認し、必要な場合は税務署に相続税の申告を行わなければなりません。
相続税は、遺産総額のうち基礎控除金額を超えた部分に課されるため、遺産総額が基礎控除金額以下の場合は相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数で算出され、例えば法定相続人が、配偶者と子供の合計2人の場合は、3,000万円+600万円×2人で、4,200万円が基礎控除額となります。
このケースで、遺産総額が4,200万円以下であれば申告は不要であり、4,200万円を超えた場合は申告が必要となります。
また、相続税の申告は、被相続人の死亡が確認された日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。申告漏れが起きないよう、申告手続きもなるべく早い段階で行うことをおすすめします。
賃貸物件を相続するときの必要書類
先述したとおり、賃貸物件を相続するときは相続登記を行う必要があります。
その際、以下の書類を集める必要があります。
- 賃貸物件の登記事項証明書
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 亡くなった人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 賃貸物件の相続人の住民票
- 賃貸物件の固定資産評価証明書または評価通知書
それぞれの書類について詳しく見ていきましょう。
賃貸物件の登記事項証明書
登記事項証明書は、相続登記の添付書類ではありませんが、登記申請書や遺産分割協議書を正確に作成するために取得します。
登記申請書
相続登記を申請するために必要な書類です。
法務局のホームページに記載例があります。
遺産分割協議書
取得した登記事項証明書をもとに、登記する賃貸物件の情報や遺産分割協議の結果を記載します。また、相続人全員が実印で押印します。
亡くなった人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
遺産分割協議書に押印した相続人以外に相続人が存在しないか確認するため、亡くなった人の出生してから死亡するまでの連続する戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。
亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
亡くなった人の最後の居住地がわかる住民票の除票または戸籍の附票が必要です。
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員が生存していることを確認するため、戸籍謄本を取得する必要があります。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書の相続人の押印が実印であることを証明するために印鑑証明書が必要です。
賃貸物件の相続人の住民票
賃貸物件の新しい所有者の住所を登記するため、賃貸物件の相続人の住民票が必要です。
賃貸物件の固定資産評価証明書または評価通知書
賃貸物件の相続登記を行うときは、賃貸物件の固定資産税評価額の1,000分の4の額の登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税を正確に算出するために、賃貸物件の固定資産評価証明書または評価通知書が必要となります。
賃貸物件を相続したときの相続税評価
賃貸物件と居住用物件を相続したときとでは相続税評価額が大きく異なります。
一般的に、賃貸物件を相続するときは居住用物件よりも相続税評価額が低く算出され、新築時の物件価格の約6~7割程度とされています。
人に賃貸している分、相続人が自由に物件を売却したり修繕したりすることが難しく融通が利きにくいため、その分低く算出されるのです。
不動産の相続税評価を算出する際は、土地と建物を分けて考えます。
土地の相続税評価の方法には、路線価方式と倍率方式の2つがあります。
路線価方式は、市街地で一般的に使われる方法で、路線価(所有地に面した道路に割り当てられた1㎡あたりの価格)によって算出します。一方、路線価が定められていない郊外部などの地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて相続税評価額を算出する倍率方式が使われます。
また、建物の相続税評価額は固定資産税評価額をもとに算出されます。
先述したとおり、賃貸物件の場合は所有者による自由な処分や使用収益が妨げられるため、上記で算出した評価額から減額措置を受けることができ、賃貸物件の土地・建物の相続税評価額は以下の計算で算出できます。
賃貸物件の土地の評価額=自用地の評価額-(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
賃貸物件の建物の評価額=固定資産税評価額-(1-借家権割合×賃貸割合)
借地権割合:路線価図で確認でき、地域によって30~90%で定められる
借家権割合:賃貸物件の評価に利用される割合で、一律30%と決まっている
賃貸割合:実際に貸し出している面積の割合
賃貸物件を相続するときの遺産分割方法
相続人が複数人おり、遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議が必要となります。
賃貸物件を相続するときの遺産分割方法には、大きく現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。
ここからは、それぞれの分割方法を詳しく解説します。
現物分割
現物分割は、不動産や車などの財産をそのまま相続する遺産分割方法です。
例えば、「賃貸物件Aは妻が相続し、賃貸物件Bを長男が相続し、車と預金は長女が相続する」という例が挙げられます。
最もシンプルな分割方法ですが、相続人の数だけ相続物件があったり、物件の価値が同等であったりすることは少ないため、平等に分割することは難しいと考えられます。
代償分割
代償分割とは、相続人の1人が物件を取得し、他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。
例えば、「賃貸物件(評価額3,000万円)を長男が相続する代わりに、次男と三男には1,000万円ずつ支払う」という例が挙げられます。
同等の価値のある相続物件が相続人の数だけ相続物件がない場合に選択できるメリットがあります。
一方で、賃貸物件の相続人が、他の相続人に代償金を支払うための金銭を確保する必要があることや、期日になっても代償金が支払われずトラブルになる可能性があるなどの注意点があります。
換価分割
換価分割とは、相続財産を換価して金銭を分割する遺産分割方法です。
例えば、「相続した賃貸物件を売却して、売却代金を複数の相続人で分ける」という例が挙げられます。
財産を平等に分けやすいメリットがありますが、賃貸物件を手放さなければならないことや、売却によって譲渡所得税がかかることには注意が必要です。
賃貸物件を相続したときにかかる税金
賃貸物件を相続する際、相続税以外にかかる主な税金は、不動産取得税、固定資産税・都市計画税、所得税・住民税です。
ここからは、それぞれの税金について詳しく解説します。
不動産取得税
賃貸物件を相続したときは不動産取得税がかかります。
不動産取得税は、賃貸物件かどうかにかかわらず不動産を取得したときに課せられる税金です。
不動産取得税は、土地・建物にかかわらず税率が4%で、
不動産取得税=不動産の固定資産税評価額×4% の計算で算出できます。
ただし、2024年3月31日までに取得した不動産に関しては、軽減税率で税率が3%となります。また、土地に関しては固定資産税評価額が2分の1に軽減される措置もあります。
固定資産税・都市計画税
固定資産税や都市計画税は、土地や建物を所有しているときにかかる税金です。
都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有しているときに課されるもので、一般的に固定資産税と一緒に納めます。
その年の1月1日時点の所有者に対して、その所在地の市町村から課税されます。
固定資産税評価額をもとに課税標準額が算出され、
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)、都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)の計算で算出できます。
所得税・住民税
所得税と住民税は、個人の1年間の所得に対して課される税金です。
そのため、賃貸物件を相続して家賃収入が発生した場合は、その収入から必要経費を差し引いた不動産所得にも所得税や住民税が課されます。
必要経費には、主に賃貸物件に係る固定資産税や都市計画税、事業税、修繕費や保険料、広告宣伝費などが挙げられます。
まず、所得税は、5%~45%の7段階に分かれ、各段階の所定金額を超えた部分に対してそれぞれの税率が適用されます。
例えば、課税所得金額が650万円の場合、195万円までに対しては税率5%、195万円~330万円までに対しては税率10%、330万円~650万円までに対しては税率20%が課税されるのです。
つまり計算すると、195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(650万円-330万円)×20%で、87万2,500円が所得税額となります。
次に、住民税については自治体によって多少異なりますが、所得金額の10%程度となります。
そのため、所得金額が650万円であれば、650万円×10%で、約65万円が住民税となります。
賃貸物件を相続するときの注意点
賃貸物件を相続するときは、以下の2つに注意する必要があります。
- 共有名義にするとトラブルになりやすいこと
- 敷金や修繕費を確保すること
ここからは、それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。
共有名義にするとトラブルになりやすいこと
1つ目は、相続した賃貸物件を相続人間で共有名義にすると、トラブルに発展することがあることです。
賃貸借契約を締結するときや、将来的に賃貸物件を売却するときなどに、共有名義人全員の同意が必要となるためです。
例えば、親から相続した賃貸物件を長男と次男の共有名義にしたものの、しばらくして、長男は賃貸物件の売却を提案したが、次男はこのまま賃貸を続けたいと意見が分かれるケースが挙げられます。
共有名義にすると、賃貸物件の相続を誰か1人に決めなくて良いメリットがありますが、将来的に意見が分かれてトラブルに発展するリスクがあるので注意しましょう。
敷金や修繕費を確保すること
2つ目は、敷金や修繕費などの費用を確保しておく必要があることです。
賃貸物件を所有している場合、敷金や保証金を預かっていることがほとんどです。
借主との賃貸借契約が解除され、借主が退去する際、相続人が物件の修繕費などの費用を差し引いた金額を借主に返還しなければなりません。
また。原則として経年劣化や通常損耗の修繕費用は貸主が負担する必要があります。物件状況によっては大規模な修繕が必要となり、多額の費用がかかることもあります。
そのため、賃貸物件の相続人は、あらかじめ敷金や保証金、修繕費用などの資金を確保しておく必要があるのです。
賃貸物件の相続に関するまとめ
賃貸物件の場合、行うべき手続きや相続税評価の方法などが居住用物件と異なります。
所有者が亡くなった後、相続人が賃貸物件のオーナーとして運用を継続できるのか、どのように運用していくのが最適かなどをよく検討しなければなりません。
また、不動産の相続は親族間でトラブルになりやすいため、遺産分割協議などの手続きを慎重に進める必要があります。
相続手続きに不安がある場合や、悩んだ場合は弁護士に相談することをおすすめします。
トラブルに発展しにくい方法で、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。