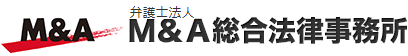会社を相続する際の流れを徹底解説!経営権を引き継ぐ時のトラブルや対策方法も紹介
お困りではありませんか?

会社を経営している方、特に中小企業の経営者にとって、年齢を重ねると大きな課題となるのが「会社を誰にどのように引き継ぐか」という問題です。後継者を子どもや家族に任せたいと考える方も多いでしょう。
一方で、経営者の子どもの立場からすると「親が亡くなったら自分が会社を相続して事業を継がなければならないのでは」と不安を感じているケースも少なくありません。
このように、会社相続は経営者側と家族側の双方にとって避けては通れないテーマです。実際には、相続税の問題や後継者選び、株式の承継など、複雑でトラブルにつながりやすい点もあります。
そこで本記事では、会社を相続する際によく起こる問題や、スムーズに事業承継を進めるための流れ、あらかじめ取っておくべき対策について、わかりやすく解説します。
会社の相続とは
「会社を相続する」と言っても、実際には大きく二つのパターンがあります。
それは、個人事業主として営んでいた事業を引き継ぐ場合と、法人(株式会社など)の株式を引き継ぐ場合です。どちらに該当するかによって、必要となる手続きや相続財産の範囲が大きく変わるため、まずは違いを理解しておくことが大切です。
個人事業主の場合
親が個人事業主として会社を営んでいた場合、その「会社」を相続するというのは、実際には個人の財産を相続することを意味します。
例えば、事業で使用していた以下のような財産は、すべて経営者個人の所有物として扱われます。
-
事業用に利用していた不動産(事務所、店舗、工場など)
-
事業資金としての預金
-
機械や設備、車両
-
パソコンや什器備品など
これらは通常の相続と同じように遺産分割協議の対象となり、相続税の課税対象にも含まれます。つまり、事業をそのまま引き継ぎたい相続人がいる場合でも、遺産分割の過程で他の相続人と調整が必要になるのです。
特に注意が必要なのは、事業用資産が多い場合です。例えば、工場や店舗など不動産の割合が大きいと、相続人間で分けにくいためトラブルになりやすい傾向があります。この場合は、事前に遺言書で承継方法を指定しておく、または事業承継税制を活用して税負担を軽減するなどの対策が有効です。
法人(株式会社など)の場合
一方、株式会社などの法人を相続する場合、考え方は大きく異なります。
法人が保有する不動産や預金、設備などはすべて「会社」という法人格に帰属しており、経営者個人の財産ではありません。そのため、経営者が亡くなったからといって、会社の財産そのものが相続人に引き継がれることはありません。
この場合に相続の対象となるのは、会社の株式です。株式を相続することで、経営権や配当を受ける権利を承継することになります。つまり、会社を引き継ぐというのは、実質的には「株式を承継すること」を意味します。
ここで重要なのが、株式の分配方法です。例えば、後継者が経営を引き継ぐためには過半数以上の株式を相続する必要がありますが、複数の相続人で株式を分割してしまうと、経営権が分散して意思決定が難しくなる可能性があります。そのため、遺言や事業承継計画を通じて、株式をどのように承継するかを明確にしておくことが重要です。
非上場会社の株式を確認する方法
中小企業の多くは非上場会社であり、株式が市場で取引されていないため、所在の確認が必要になります。特に、株券を発行していない会社も多いため、相続の際には「そもそも株式がどこにあるのか」を確認することから始めなければなりません。
具体的には、以下の資料を確認するのが有効です。
-
株主名簿:株主と持株数が記載されている最も基本的な資料
-
株主総会の招集通知:株主に送られる書面から、株主であったことを確認可能
-
配当通知書:配当金を受け取っていた場合、その証憑が手掛かりになる
-
確定申告書の控え:申告時に配当所得を計上していれば株式保有の証拠になる
これらの資料をもとに、発行会社に照会して株式の所在を確認することが必要です。もし、株式の所在が不明なまま相続を進めてしまうと、承継後の経営権が不安定になり、予期せぬトラブルに発展しかねません。
会社を相続する方法
会社を相続する際は、主に「財産的な承継」と「経営権の承継」の2つの側面を考慮することが重要です。
財産的な承継:株式の相続
株式会社の場合、会社を相続するということは、会社の株式を相続することを意味します。相続する株式の割合によって、後継者が会社を支配できる度合いが変わってきます。
例えば、後継者が会社の株式を100%相続できれば、会社を完全に支配することが可能です。
しかし、複数の相続人がいて株式が分散すると、後継者の経営権が弱まるため、円滑な事業承継のためには後継者に株式を集約させる必要があります。
経営権の承継:役職の引き継ぎ
会社を相続するということは、単に株式を保有するだけでなく、実際の会社経営を引き継ぐことも意味します。
具体的には、先代の経営者が務めていた代表取締役などの役職を後継者が引き継ぎ、会社の業務を遂行することです。
株式を相続していても、役員に就任しなければ実際の経営には関われません。そのため、株主総会や取締役会での手続きを通じて、後継者を経営の中心に据えることが必要です。財産の相続と経営権の承継が両輪となって、真の意味で事業承継が成立します。
会社を相続する流れ
会社を相続する流れは主に以下のとおりです。
- 後継者の決定と承継計画の策定
- 株式・経営権の承継手続き
- 相続税対策と登記などの法的手続き
- 承継後の経営体制の整備
それぞれ詳しく解説します。
1.後継者の決定と承継計画の策定
会社を相続するにあたって、最初に取り組むべき最重要ステップは後継者の決定です。
相続人の中から誰が会社を引き継ぐのかを早期に明確にしておくことで、株式や経営権の承継をスムーズに進められます。後継者を選ぶ際には、本人に「経営意欲や能力があるかどうか」「従業員や取引先からの信頼を得られるかどうか」といった点を判断して検討しましょう。
また、相続が発生する前から承継計画を立て、徐々に権限を委譲していくことも重要です。中小企業における会社相続では、後継者が経営に慣れるための準備期間が特に重要となるため、時間をかけた承継スケジュールを設計することがトラブル回避にもつながります。
2.株式・経営権の承継手続き
後継者が決まったら、次に行うべきは会社の株式と経営権の承継です。
会社の支配権は株式の保有割合によって決まるため、できるだけ後継者に株式を集中させる必要があります。複数の相続人が株式を分散して所有すると、経営判断に支障が出たり、株主間の対立につながったりする可能性があります。そのため、遺言や遺産分割協議を通じて、後継者に株式を集約する工夫が重要です。
また、株式の承継に合わせて、代表取締役などの役職についても変更登記を行う必要があります。これにより、法的にも後継者が正式な経営者として認められ、会社経営を安定して継続できます。
3.相続税対策と登記などの法的手続き
会社を相続する際には、株式の評価額に応じて高額な相続税が発生するケースがあります。
特に中小企業のオーナー経営者の場合、会社株式が財産の大部分を占めるため、納税資金の確保が大きな課題となります。そのため、事前に事業承継税制や贈与税の特例措置を活用し、相続税の負担を軽減する対策が必須です。
さらに、相続発生後には相続登記や代表者変更登記、税務署への申告などの法的手続きも行う必要があります。これらを怠ると、会社の運営に支障をきたす恐れがあるため、税理士や弁護士と連携して計画的に進めることが求められます。
4.承継後の経営体制の整備
株式や役職が正式に承継された後も、すぐに安定した経営が実現するわけではありません。後継者が経営者としての信頼を築くためには、従業員や取引先に対して承継後の経営方針を明確に示し、信頼関係を継続することが重要です。
また、先代経営者からのノウハウの引き継ぎや社内体制の見直しを行い、新しい経営環境に対応できる仕組みを整えなければなりません。特に、中小企業では後継者のリーダーシップが企業存続に直結するため、承継後の経営基盤を強化する必要があります。
円滑な承継のためには、相続発生前から関係者に周知し、移行期間を設けてスムーズに経営を引き継ぐことが重要です。
会社の相続税評価
前述のとおり、株式会社などの法人の会社を相続する場合に、その会社の財産的な評価、特に株式の評価が問題となります。
会社の相続の場合、まず具体的にその評価による価値が重要になるのは、相続をする際に発生する相続税の評価です。
特に中小企業の株式を相続する際には、どのように評価するかによって、実際に発生する相続税の金額が大きく変わります。ここでは、株式評価の基本的な考え方と代表的な算定方法を解説します。
上場企業と非上場企業の違い
相続税評価においては、上場企業と非上場企業で大きな違いがあります。
上場企業の場合は、市場での株価が明確に分かるため、その時価を基に評価するのは比較的容易です。しかし、実際に会社の相続が行われるのは、中小規模の非上場企業がほとんどです。
非上場企業は株式市場で取引されないため、株価を直接算定することができず、特別な評価方法を使う必要があります。
非上場会社の株式評価方法
非上場会社の株式を相続する場合には、主に以下の評価方法が用いられます。
- 類似業種比準価額方式
- 純資産価額方式
- 折衷方式
それぞれ分けて解説します。
類似業種比準価額方式
類似した業種の上場企業の株価や配当、純資産、利益などを基準にして、対象会社の株式の価値を推定する方法です。
例えば、同じ業界で上場している会社の株価がわかれば、それを基にして非上場企業の適正な株価を算定します。ただし、会社ごとに規模や経営状況が異なるため、それらの要素を加味して調整する必要があります。規模が大きい会社ほど、この方式の比重が高まります。
純資産価額方式
純資産価額方式は、会社が現在解散した場合に株主に分配される資産額、いわゆる「解散価値」に基づいて算定する方法です。
具体的には、仮に現時点で会社が解散した場合に、株主に対して分配される会社が持っている純粋資産価額で評価します。
具体的には、貸借対照表を基に資産(現金・土地・設備など)を時価で算定し、そこから負債を差し引いて純資産額を求めます。その純資産を発行株式数で割ることで、1株あたりの評価額を算出します。土地や設備を多く保有する企業では、この方式を使うと高い評価額になりやすい傾向があります。
この純資産価額を発行株式数で割ると1株あたりの株式の価格が算出できるというのが純資産価額方式による株式の評価です。
折衷方式
類似業種比準価額方式と純資産価額方式を一定割合で組み合わせる方法です。
折衷方式を使う際に、類似業種比準価額方式と純資産価額方式をそれぞれどれぐらいの割合で算出するかは、会社の規模によって、決まっています。例えば、「中会社の中」と呼ばれる規模の会社では、類似業種比準価額方式を75%、純資産価額方式を25%使って算出します。
そして、実際に相続税の算定のための非上場企業の株式評価をする場合、会社の種類や規模によって、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、折衷方式のどの方式で算出した額を株式評価額とするかが税務上決まっているので、それに従って税務上の株式評価額が決まります。
規模が大きくなるほど、類似業種比準価額方式の割合が増え、逆に小規模な会社ほど純資産価額方式の割合が高くなります。
その他の評価方式
上記以外にも、状況に応じて適用される方法があります。
- 配当還元方式
少数株主が相続する場合に使われる方式で、実際に得られる配当金を基準に評価します。この方式を用いると、一般的に他の方式よりも低い株価評価になることが多く、少数株主にとっては有利です。
- 特定会社の評価
「土地保有特定会社」や「株式保有特定会社」に該当すると、資産価値を基準に評価されるため、通常よりも高い評価額となるケースがあります。特に土地や株式を多く保有している会社は、この点に注意が必要です。
会社を相続する後継者
会社を相続する後継者は、できるだけ先代の経営者と同じ状況で会社を引き継ぎたいと考えると思います。例えば、会社の創業者である経営者であれば、会社の役職的にも株式数でも、会社を統率する権利が本人に集約されていて、円滑に経営判断できる状況にあることが多いです。
それを相続する後継者が、できるだけその状態をそのまま承継して先代の経営者と同様に経営をすることが、会社を引き継ぐ先代の経営者も、引き継ぐ後継者も双方が望むことという場合が多いです。ここでは、先代経営者の後継者選定をどのように進めればいいのかを見ていきます。
会社を相続する方法の選択肢
会社を承継する選択肢としては、大きく3つの方法があると考えられます。
1つ目は、株式を相続する相続人である家族などとは関係なく、会社の事業などをよくわかっている従業員や役員から後継者を選択する方法です。この場合、会社を支配する株式は経営者の相続人である家族などに承継されますが、日々の経営は、株主総会で承認された代表取締役などである後継者が行うことになります。
2つ目は、会社の株式を相続する子供などの家族に、経営も合わせて承継する方法です。中小企業の会社相続の場合には、この方法が多いと考えられます。この承継では、株式の承継をすると同時に会社内での経営者としての立場の承継も考慮する必要があります。この選択肢については次の項目で詳しく説明します。
最後に3つ目は、会社ごと売却してしまうM&Aによって、他の会社に事業を売却してしまう方法です。この選択肢は事業の後継者が見つからない場合や、株式を相続する相続人が、先代経営者が亡くなった後の会社との関りを望まない場合などの選択肢と考えられます。
もっとも、相続は会社の承認を要せず自動的に発生しますが、その後の株式売却や譲渡は会社の承認が必要となる点に留意が必要です。譲渡が不承認となった場合、会社や指定買取人に株式を売却しなければならず、価格が折り合わなければ裁判所に「売買価格決定の申立て」を行うこともあります。
相続による後継者を決める方法
前項で説明したとおり、会社の相続による承継は、前述の会社承継の3つの選択肢のうち2つ目の先代経営者の相続人である子供などの家族に引き継ぐことを指すことになります。よって、会社相続による後継者選びの進め方について見ていきます。
会社の相続による後継者選びの進め方で最初に行うべきことは、後継者を誰にするのかを決めるということです。会社相続による後継者は子供などの相続人の中から選ぶことになりますが、本人に会社を継承する意思があるのか、また会社を経営していく素質や能力があるのかなどを考慮して、子供などの相続人の中から後継者を決めることになると思います。
最初に会社相続の後継者を決めるべき理由は、相続による会社承継の場合、会社株式の承継や経営者の地位の承継をスムーズに行うためには一定の時間を要するからです。早く後継者を決めれば、その後継者への権限の集約を、時間をかけて行うことができます。
会社相続による後継者選びの場合、財産として相続される先代経営者の会社の株式をどのように引き継ぐかということと、会社の中での先代経営者の役割である代表取締役などの役職をどのように引き継ぐのかの両方を考える必要があります。
財産的な会社の承継である会社の株式の承継については、先代経営者の全財産の中で、承継させる会社の株式をできるだけ後継者となる相続人に集約し、そのほかの財産を他の相続人に割り当てるなど、会社支配の権限をできるだけ後継者の相続人に集中させる工夫をする必要があります。
一方で、代表取締役などの会社の中での役割の承継は、後継者である子供などの相続人の経営者としての判断能力の習得や会社の中で従業員や取引先などの信頼を得るというような面もありますから、一定の時間をかけて承継していくということが一般的です。
会社相続で起こりやすいトラブルと注意点
会社を相続する際には、さまざまなトラブルが発生することがあります。相続人への事業承継を考えている先代の経営者、経営者である親から会社を相続する予定の子供などの後継者としては、想定されるトラブルに対してどのように対応するのか対策しておくのが賢明です。ここからは、会社を相続する時に考えられるトラブルについて見ていきます。
後継者が決まらない場合のリスク
会社を相続するというのは、一般的に先代経営者が所有する会社の株式や代表取締役などの地位を、子供などの家族が承継するということです。しかし、相続人である子供たちの誰もが会社を引き継ぐ意思がないなど、後継者が決まらない場合は、会社を相続すること自体ができません。
このような場合でも、会社を継続させたいのであれば、会社を相続することは断念せざるを得ません。会社の相続以外で、先代経営者が取り得る方法としては、会社の株式は先代経営者の家族が相続して株主として会社を支配し、日々の会社経営は家族以外の他の役員や従業員、全く他の会社からヘッドハンティングして後継者を選出するか、M&Aなどによって会社自体を売却するという方法を取ることになります。
株式承継に伴う相続税の負担
会社の先代の経営者である親が亡くなって、子供などに会社の株式を相続する場合、相続税が発生します。株式評価額の総額が多額になる一方で、先代経営者に預金などの他の資産があまりないような場合には、その相続税をどのように負担するのかが現実的な問題となります。
会社経営の安定のために、会社の後継者になる特定の子供などに株式を集約したくても、その後継者がすべての株式に対する相続税が支払えない場合、株式の集約が難しくなります。
かといって、先代経営者が存命中に後継者に株式を贈与すれば、同様に多額の贈与税がかかることになります。
このため、親などの先代経営者は、後継者をできるだけ早期に決め、相続税対策も含めて円滑に会社の株式が後継者の特定の子供などに集約されるように、計画的に引き渡しの対策をする必要があります。
具体的には、後述の「会社を相続する場合に生前にすべきこと」の項目で挙げられているいくつかの対策を行うことを検討します。
さらに、非上場株式は現金化が難しいため、相続税の納税資金や、複数相続人間で代償分割を行う場合の現金確保が大きな問題になります。相続税額は高額でも、株式自体をすぐに売却できないことから、後継者の一時的な資金負担が重くなるケースも少なくありません。
非上場株式の相続放棄
非上場株式は評価が高くても換金が難しく、納税や経営の負担から相続放棄が選ばれる場合があります。ただし相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要で、全財産を放棄することになる点に注意が必要です。
相続放棄を検討する際には、税務や経営の観点を含めてさまざまな影響の確認が必要となりますので、専門家に相談することが望ましいといえます。
非上場株式の相続を放棄する方法とは?相続するデメリットや放棄の流れをわかりやすく解説
株式相続や不動産相続にお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら 故人が経営者であったり、経営者と知人・友人関係であったりして株式を引…
株式が分散して経営権が弱まるケース
会社の先代経営者である親などが、後継者への会社の相続の対策を充分に行っていなかったり、突然亡くなってしまったりした場合には、会社の株式を複数の人が相続することが起こり得ます。
後継者が相続した会社の経営を円滑に継続するためには、会社の重要な事項を決める株主総会での議決権を多数持っていることが必須です。
株主総会の決議で経営者の意思を問題なく可決するためには、会社を相続する後継者は、普通決議で2分の1超、特別決議などで3分の2超の議決権、すなわち会社の株式を持っている必要があります。
このことを考えると、最低でも相続する会社の2分の1超、望ましいのは3分の2超の株式が、会社を相続する後継者に渡るようにしておきたいところです。
これらの対策がなされずに、法定相続分では株式が分散してしまう場合には、相続協議で、相続する会社の株式を後継者に集約する一方で、先代経営者の預金などの財産を他の相続人に割り当てたり、一旦、分散して相続した後に後継者が会社の株式を買い取ったりするなどの手続きを検討する必要があります。
取引先から取引を打ち切られるリスク
相続する会社の取引先には、先代の経営者との個人的なつながりで取引を行っていたという会社もあるかも知れません。会社の事業規模からすると、他の会社であれば取引を行わないのだけれども、先代の経営者には、過去に個人的にお世話になったので取引をしていた、というような場合が典型的です。
このような場合、先代の経営者から会社が相続され、子供などの後継者が経営者になった途端に取引の打ち切りを申し出てくるということがあります。その取引先が相続した会社の事業の中心的な部分に関わるような場合には、会社の円滑な事業継続に大きな影響が出てしまいます。
このようなことが起こらないようにするには、先代の経営者の時代から、後継者も重要な取引先とは親密な関係性を築き、信頼を得ておく必要があります。そうすれば、会社を相続して後継者が経営を始めたからと言って、突然取引先が関係性を絶つというようなことは起こりにくくなります。
従業員などの理解が得られない問題
取引先と同様、相続で会社を引き継ぐ後継者について、自分の会社の経営者として受け入れられないと従業員が考えたような場合には、後継者の会社経営に従業員が反発することが予想されます。
例えば、従業員の中にも先代の経営者の人柄やカリスマ性などを理由に会社で働いている人もいるかもしれません。あるいは、充分な引継ぎ期間もなく会社の相続をし、会社の事情もよくわかっていない後継者が経営をすることに抵抗がある従業員が出てくることも想定されます。
このようなことを回避するためには、相続で後継者となる先代経営者の子供などは、例えば大学や大学院で経営学を学ぶ、MBAなどの資格を取得する、同業他社や大企業に一旦就職して経験を積むなどの後継経営者としての説得性を持つとともに、相続する会社で一定期間、先代経営者の下で働くなど、従業員が後継経営者として納得できるような実績を積むことが望ましいと考えられます。
会社を相続する場合に生前にすべきこと
これまで見てきたとおり、会社の相続がスムーズに行われるためには、先代の経営者が存命のうちから、ある程度長期間をかけて計画的に行うことが肝要です。
ここからは、会社を相続する場合に、先代の経営者が生前に行っておくべきことについて説明します。
遺言による会社株式の承継方法
先代の経営者が会社を特定の子供などに承継させたい場合、遺言で会社の株式を後継者となる子供に集中させておくことが、後継者が問題なく会社の経営を引き継ぐためには重要です。
よって、会社支配的に先代経営者と同様な状況にするためには、後継者には、先代経営者が持っている会社の株式をできればすべての株式を相続させたいところです。
しかし、後継者以外にも法定相続人がいる場合には、後継者と他の相続人の間に争いが起きないように、他の法定相続人の財産相続も考慮する必要があります。
少なくとも、他の法定相続人に認められる最低限相続できる財産割合である遺留分については株式以外の財産で賄うなどの配慮をしておく方が良いでしょう。
後継者以外の法定相続人の遺留分を侵害している場合、先代経営者の死後、後継者以外の法定相続人から遺留分侵害請求訴訟が提起される虞もあります。
このようなことを考えて、先代経営者は会社を相続する後継者に対して、自身が所有する会社の株式のできるだけ多くの部分を遺贈でき、他の相続人も納得できるような遺言を残すことは、適切に後継者に会社株式を引き継ぐためには必要だと考えられます。
生前贈与を活用した会社相続対策
先代の経営者が、既に確実に会社の相続をさせる後継者を決めているのであれば、先代の経営者自身が亡くなったときに会社の株式の移転が起こる遺言ではなく、存命中に生前贈与して確実に移転をさせるという方法を取ることもできます。
この方法を取れば、他の法定相続人にも明確に先代の経営者が誰に会社を相続させたいのかを示すことができるので、先代経営者が亡くなった後での家族内の揉めごとを回避できる可能性が高いと考えられます。
一方で、他の法定相続人の不満が出ないようにするために、株式を生前贈与される後継者以外の法定相続人などにも、先代の経営者の株式以外の財産の分与をどのようにするのかも、できるだけ明確に示す方が良いと考えられます。特に、他の法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮することは重要です。
後継者への会社の相続のための株式譲渡は、贈与税と相続税の関係を考慮する必要はありますが、遺贈であっても生前贈与であっても、経営承継円滑化法に基づく事業承継税制などの優遇措置もあるので、これらの制度も活用して、計画的に先代経営者から後継者への株式の移転を進めることは有効だと考えられます。
家族信託
先代の経営者から後継者への会社相続の手段として、家族信託の制度を利用するという方法も考えられます。先代の経営者を委託者及び受益者、後継者の子供などを受託者として家族信託の制度を利用し、先代の経営者が亡くなった後はその所有している財産が受託者である後継者に移転するという契約にしておくと、先代経営者が亡くなった後は、実質的に会社の株式が後継者に継承されます。
家族信託を利用した会社株式の承継は、経営承継円滑化法に基づく事業承継税制などの優遇措置の対象ではなく、節税の効果はあまり期待できませんが、家族信託で受託した後継者以降の後継者も指定できるなど、メリットもあります。
一方で、先代経営者が所有していた財産から発生する利益の受益権は、先代経営者が亡くなった後は通常の財産と同様に先代経営者の遺産として考えられますので、他の法定相続人の遺留分を侵害しないように考慮される必要があります。
会社の経営者としての役割の承継立場
以上は、先代経営者から後継者への財産的な承継について、生前に行っておくべき対策ですが、一方で会社内での先代経営者としての役割についても、一定の期間をかけて先代の経営者から後継者である子供などに引き継いでいくことも重要です。
これを怠ると、先代経営者から後継者に経営者が変わったときに、「会社を相続する時に考えられるトラブル」の項目でも挙げた「取引先が取引を打ち切る」、「従業員などの理解が得られない」などの問題が発生する可能性があります。
事業承継税制の活用
さらに、事業承継税制の活用も有効です。一定の要件を満たす後継者であれば、相続や贈与により取得した株式に関して相続税や贈与税の納税が猶予・免除される制度があります。また、ホールディングス化により株価の評価方法を工夫する、死亡退職金を活用して相続財産を圧縮する、拒否権付種類株式を導入して経営権を守りつつ財産権を分散させるなど、組織再編や種類株式の活用といった対策も検討に値します。
会社の相続のまとめ
今回は、会社の相続について説明をしました。先代経営者から子供などの後継者へスムーズな会社経営の引継ぎを行うためには、会社株式の相続の仕方や代表取締役などの立場の継承など、さまざまなことを考慮して計画的に進める必要があります。
また、突然、会社相続が起こると、それ以降に取れる対策も限られてしまい、トラブルが発生することにもなりかねません。よって、まだまだ先代経営者の会社経営に問題がない時期からでも、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けながら、いずれは行わなければならない時期が来る会社の相続について、日ごろから検討を進めておくことも重要だと言えます。
お困りではありませんか?