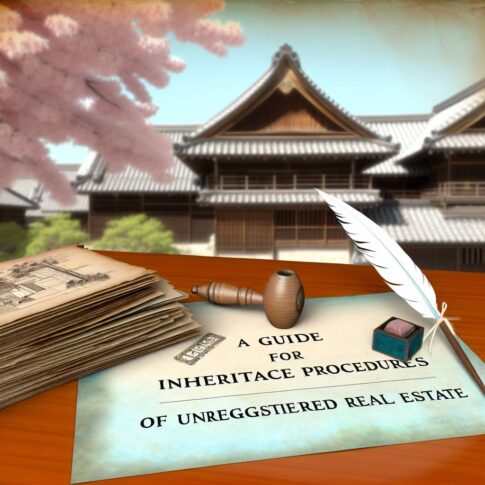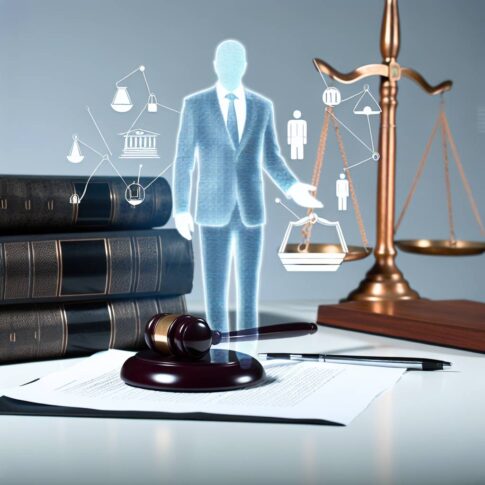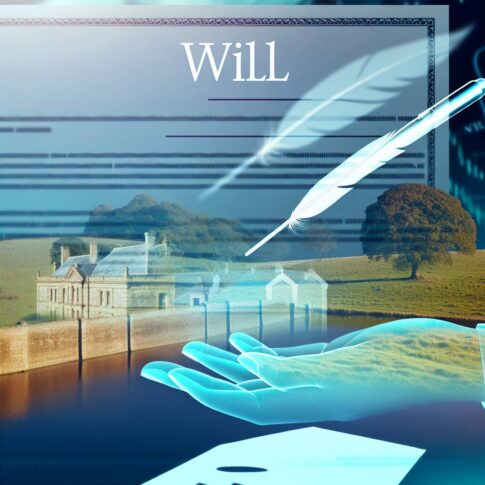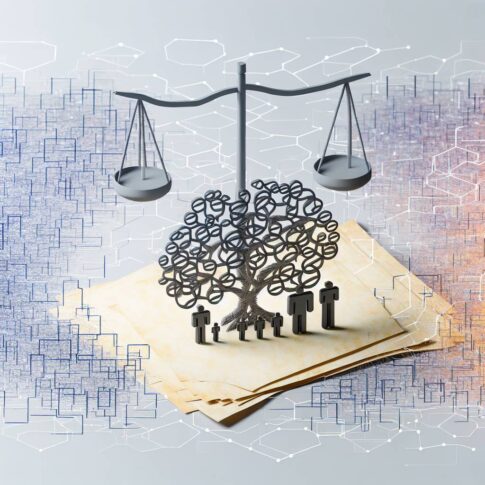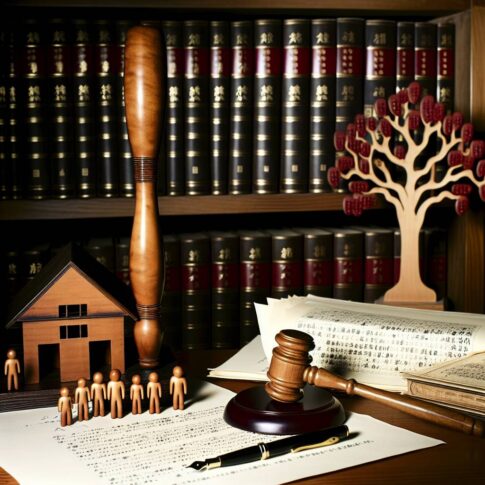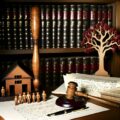相続税の申告は、多くの人にとって初めての経験であり、不安や疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。この記事では、税務署が提供する情報をもとに、相続税の申告方法を分かりやすく解説いたします。適切な申告を行うために、ぜひ参考にしてください。
まず、相続税とは、故人(被相続人)が残した財産を相続した際に課される税金です。相続税の申告が必要な場合、故人の死亡を知った翌日から10か月以内に申告を行う必要があります。期限内に申告を行わないと、ペナルティが発生する可能性がありますので、注意が必要です。
1. 相続税の基礎控除額を確認する
相続税には基礎控除があり、これを超えた分に対して課税されます。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円になります。この金額を超えた財産についてのみ、相続税が課されます。
2. 財産の評価
相続税の対象となる財産には、不動産、現金、株式、貴金属などが含まれます。それぞれの財産は、相続時の時価で評価されます。不動産の場合、路線価や固定資産税評価額を基に評価を行います。財産の評価は専門的な知識が必要になる場合もあるため、税理士に相談することをお勧めします。
3. 税額の計算
評価した財産の合計額から基礎控除額を差し引き、残った金額に対して相続税率を適用して税額を計算します。税率は、相続額が大きくなるほど高くなる累進課税制度が採用されています。
4. 必要書類の準備と申告書の作成
相続税の申告書を作成するには、故人の戸籍謄本、遺産分割協議書、財産の評価に関する資料などが必要です。これらの書類を準備し、税務署の指示に従って申告書を作成します。
5. 申告と納税
作成した申告書を所轄の税務署に提出し、相続税を納付します。納付は申告期限までに行う必要がありますが、資金が不足している場合は、延納や物納の制度を検討することも可能です。
相続税の申告は複雑で手間がかかる作業ですが、税務署のウェブサイトや窓口では、詳細なガイドラインや相談窓口を提供しています。不明点がある場合は、これらのリソースを活用しながら進めていくと安心です。また、相続税の専門家である税理士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
相続税の申告を正しく行うことで、家族に負担をかけずに円滑な相続を進めることができます。この記事を参考に、しっかりと準備を進めていきましょう。