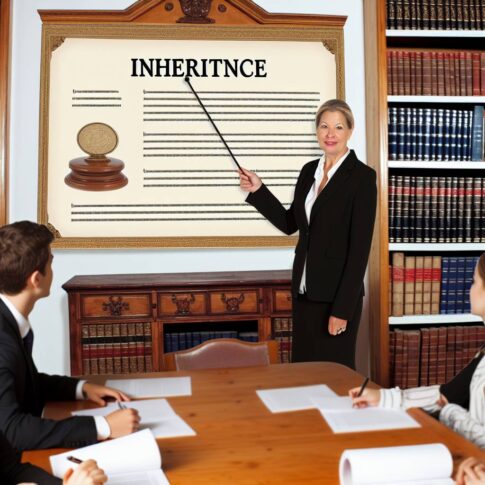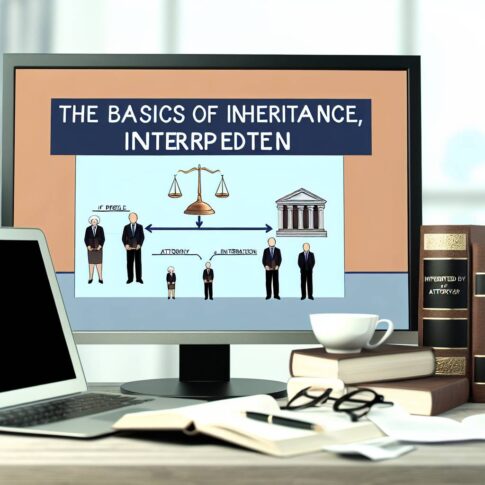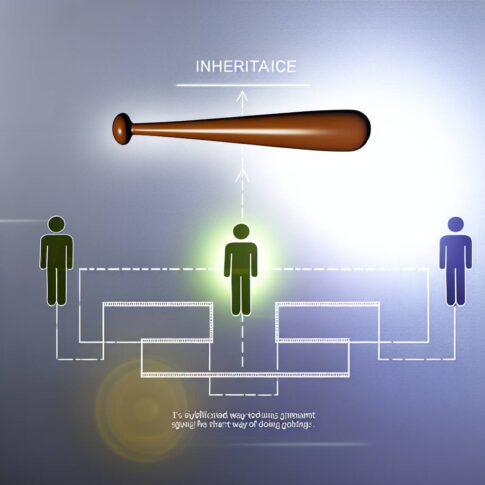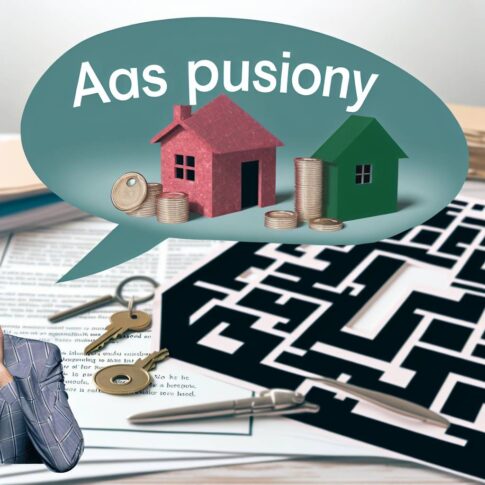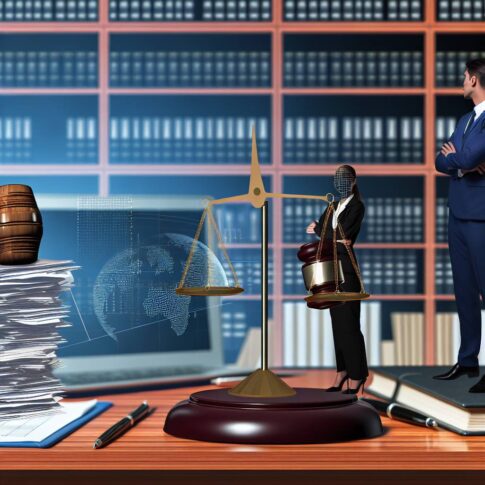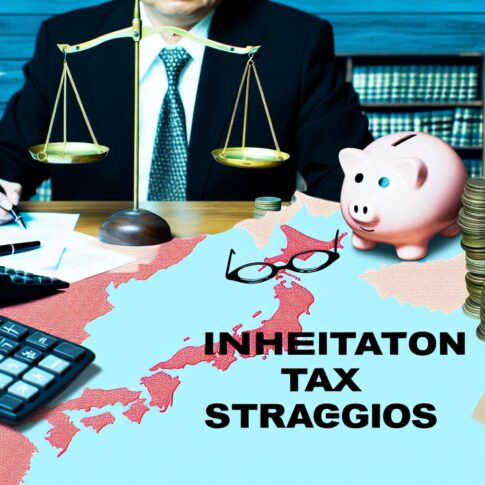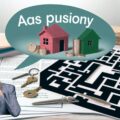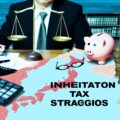タイトル: 相続税の計算方法を弁護士がわかりやすく教えます
本文:
相続税は、大切な家族が亡くなった後に遺産を受け取る際に避けて通れない問題です。しかし、その計算方法は非常に複雑で、多くの人が戸惑うことでしょう。この記事では、弁護士が相続税の基本的な計算方法をわかりやすく解説いたします。
1. 相続税の基本概念
相続税は、遺産を受け取る際に発生する税金です。遺産総額から基礎控除額を差し引いた残りの金額に対して課税されます。基礎控除額は「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」で計算されます。
2. 遺産総額の把握
まず、遺産総額を把握することが必要です。遺産には、現金、預貯金、不動産、有価証券、保険金などが含まれます。これらの評価額を正確に計算し、合計します。
3. 基礎控除額の計算
次に、基礎控除額を計算します。例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円」となります。
4. 課税遺産総額の計算
遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額です。例えば、遺産総額が1億円で基礎控除額が4,800万円の場合、課税遺産総額は「1億円 – 4,800万円 = 5,200万円」となります。
5. 税率の適用
課税遺産総額に対して相続税率を適用します。税率は段階的に設定されており、課税遺産総額が高くなるほど税率も高くなります。具体的な税率は国税庁の公式サイトで確認できます。
6. 分割計算
相続税は、法定相続分に基づいて各相続人に配分されます。各相続人が受け取る遺産額に対して税率を適用し、最終的な相続税額を計算します。
7. 相続税の申告と納付
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。期限内に申告と納付を行わないと、延滞税や加算税が発生することがあります。
8. 専門家の活用
相続税の計算は複雑で専門知識が必要です。正確な計算や節税対策を行うためには、弁護士や税理士といった専門家の助言を受けることをお勧めします。
相続税の計算方法を理解することで、遺産を適切に受け取る準備が整います。ぜひ、この記事を参考にして、スムーズな相続手続きを進めてください。