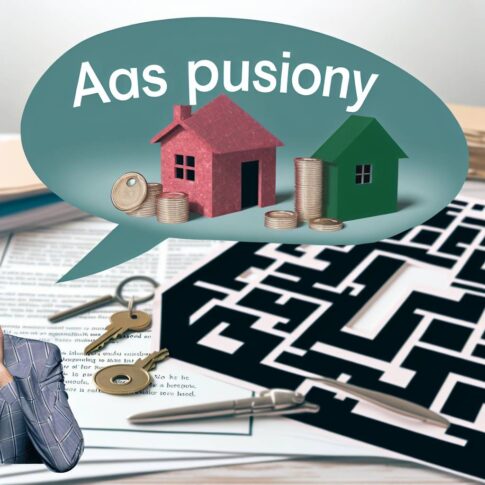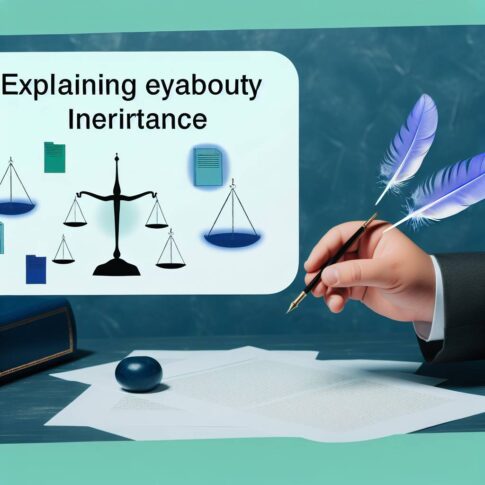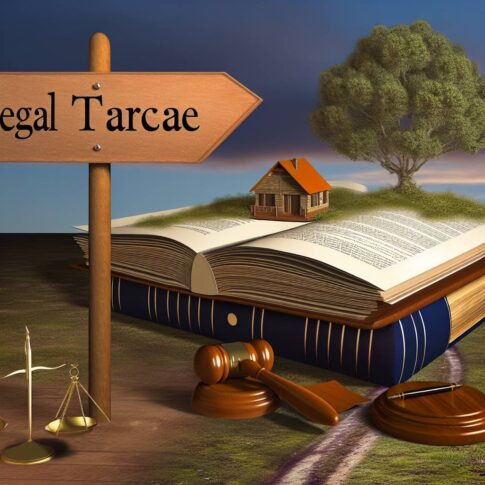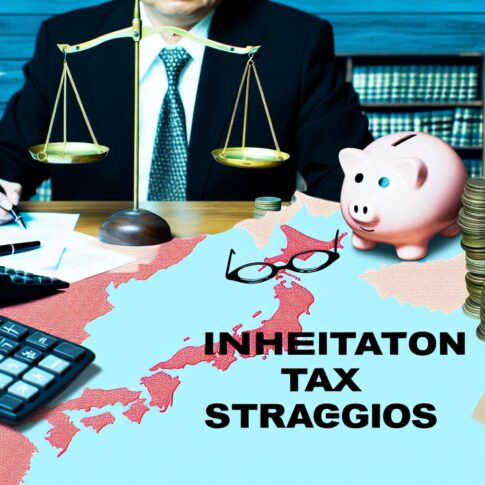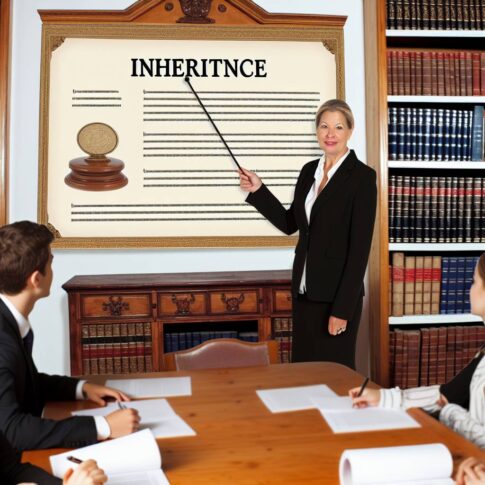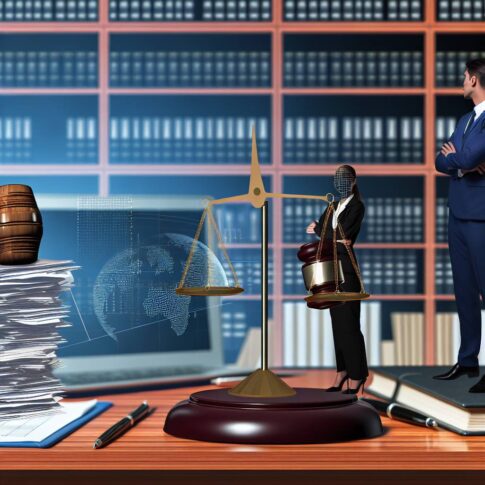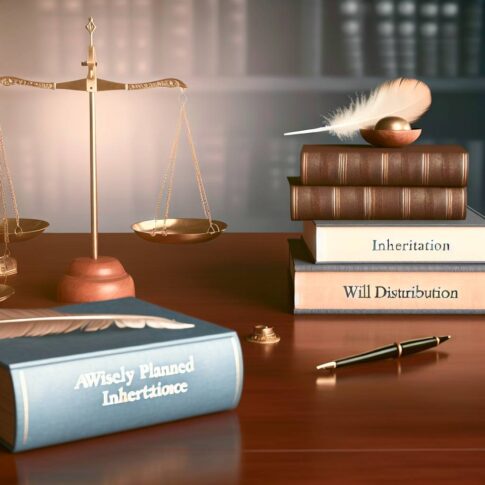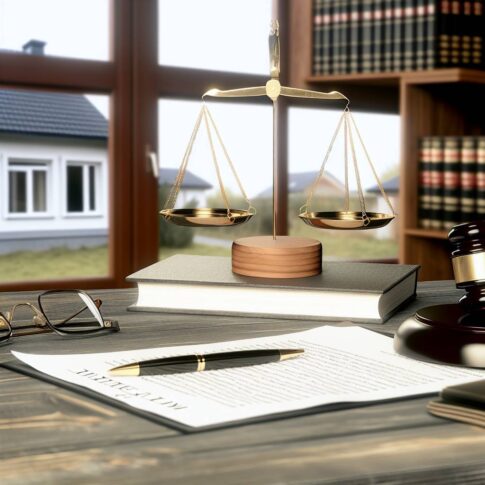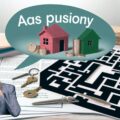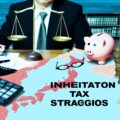相続問題は家族間での重要なテーマです。特に養子縁組が絡む場合、その影響は多岐にわたります。今回は、相続における養子縁組の具体的な影響について、法律の専門家である弁護士が詳しく解説します。
まず、養子縁組とは何かを理解することが重要です。養子縁組は、血縁関係がない人を法的に親子関係とする手続きのことを指します。この縁組が成立すると、養子は法律上、実子と同様に扱われます。これには相続権も含まれます。
相続において、養子縁組は相続人の範囲や相続分に直接影響を与えます。養子縁組をした場合、その養子も他の子どもたちと同じように相続人となります。これにより、遺産分割の際に考慮すべき相続人の数が増えることになります。例えば、遺言が存在しない場合、法定相続分に基づいて遺産が分配されるため、養子の存在は各相続人の取り分に影響を及ぼします。
また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。普通養子縁組では、養子は実親との関係を維持しつつ養親との関係を築きます。一方、特別養子縁組では、実親との法的な親子関係が完全に断たれるため、相続においては養親のみが親として扱われます。
さらに、養子縁組は税務面でも影響を及ぼします。相続税法上、養子には相続税の控除枠が適用されますが、この控除枠には上限があります。養子の数が多い場合、控除枠を超えると税負担が増える可能性がありますので、事前の計画が不可欠です。
相続における養子縁組の影響は、家族の意向や法律の状況によりさまざまです。養子縁組を検討中の方、または既に養子縁組を行っている方は、相続に関する専門的な知識を持つ弁護士に相談することをお勧めします。正しい手続きと計画を立てることが、家族全員にとって最良の結果をもたらすでしょう。