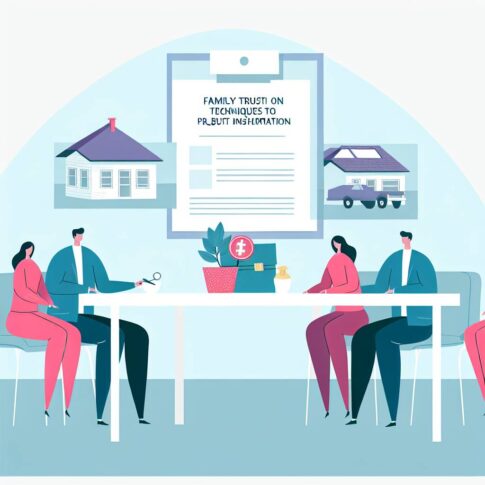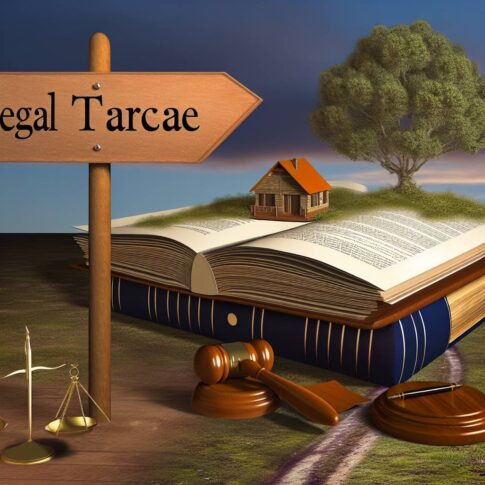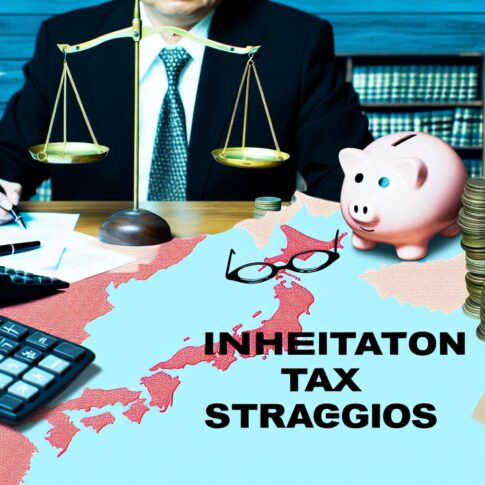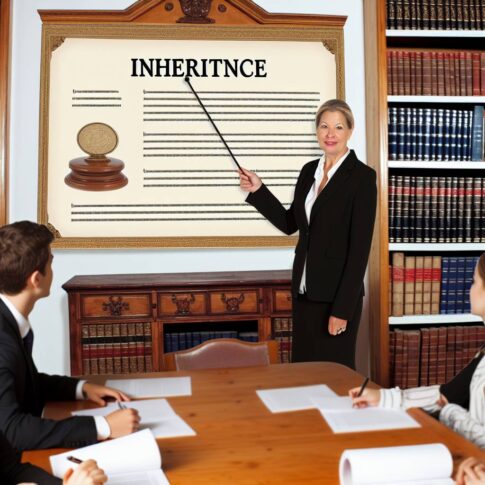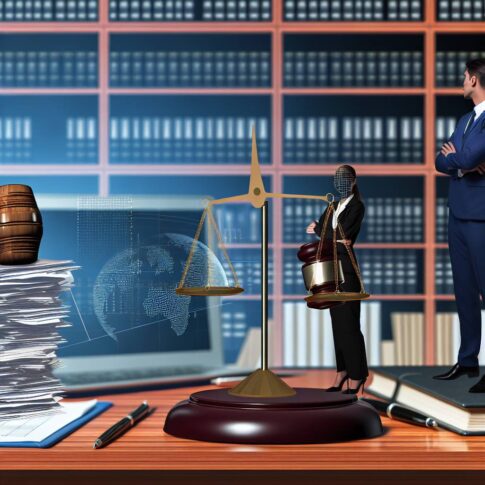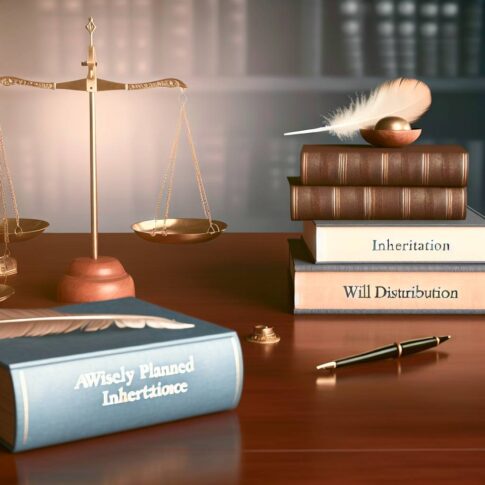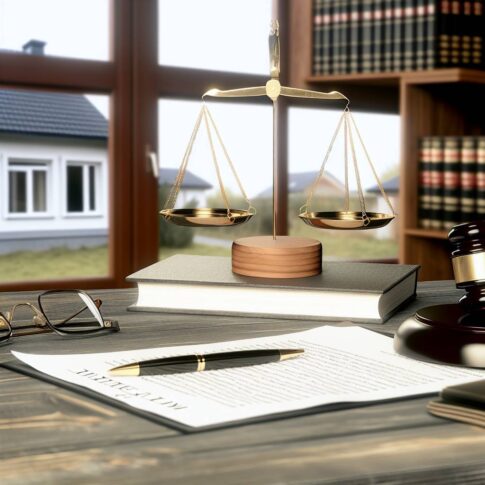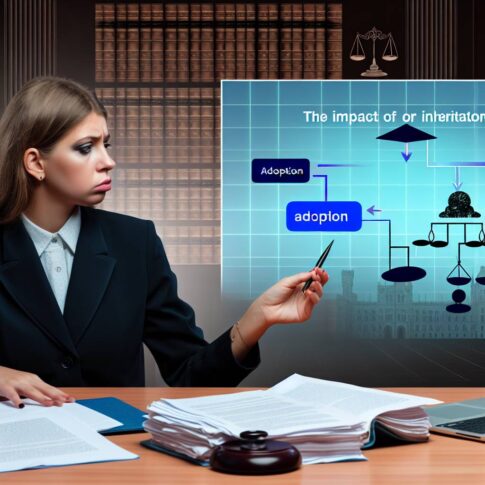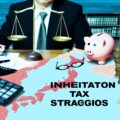近年、家族信託という言葉を耳にする機会が増えています。特に高齢化が進む中で、自分の財産をどのように管理し、次世代に引き継ぐかを考えることは重要な課題となっています。この記事では、家族信託のメリットとデメリットについて、弁護士の視点から詳しく解説いたします。
家族信託とは?
家族信託とは、個人の財産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう制度です。信託契約を通じて、受託者(財産を管理する人)に財産の管理権を移すことで、委託者(財産を託す人)の意向に沿った財産運用が可能になります。
メリット
1. 柔軟な財産管理
家族信託を利用することで、委託者の意向に沿った柔軟な財産管理が可能です。特に認知症などで判断能力が低下した場合でも、事前に決めた信託契約に基づいて受託者が適切に財産を管理できます。
2. 相続対策
家族信託は、相続税対策としても有効です。特に不動産などの資産を持つ家庭では、信託を利用することで相続税の負担を軽減し、円滑な相続が期待できます。
3. 安心感の提供
信託を通じて財産の運用や管理が行われるため、委託者は自分の意志が確実に実行されるという安心感を得ることができます。
デメリット
1. 初期費用と手続きの煩雑さ
家族信託を設定するためには、専門家に頼る必要があり、その際の費用が発生します。また、信託契約の内容を詳細に決めるための手続きが煩雑になることもあります。
2. 運用と管理の責任
受託者には財産の管理責任が生じます。適切な管理が行われなかった場合、信託者や他の家族との間でトラブルが発生する可能性があります。
3. 法律の理解が必要
信託に関する法律や税制は複雑であり、誤解や間違った解釈が問題を引き起こすこともあります。信託を行う際は、弁護士など専門家の助言が不可欠です。
まとめ
家族信託は、財産管理や相続において非常に有用な手段となり得ますが、実際に導入する際にはメリットとデメリットを十分に理解し、慎重に検討することが重要です。法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けながら、自分の状況に最適な信託契約を構築することが、将来の安心につながります。